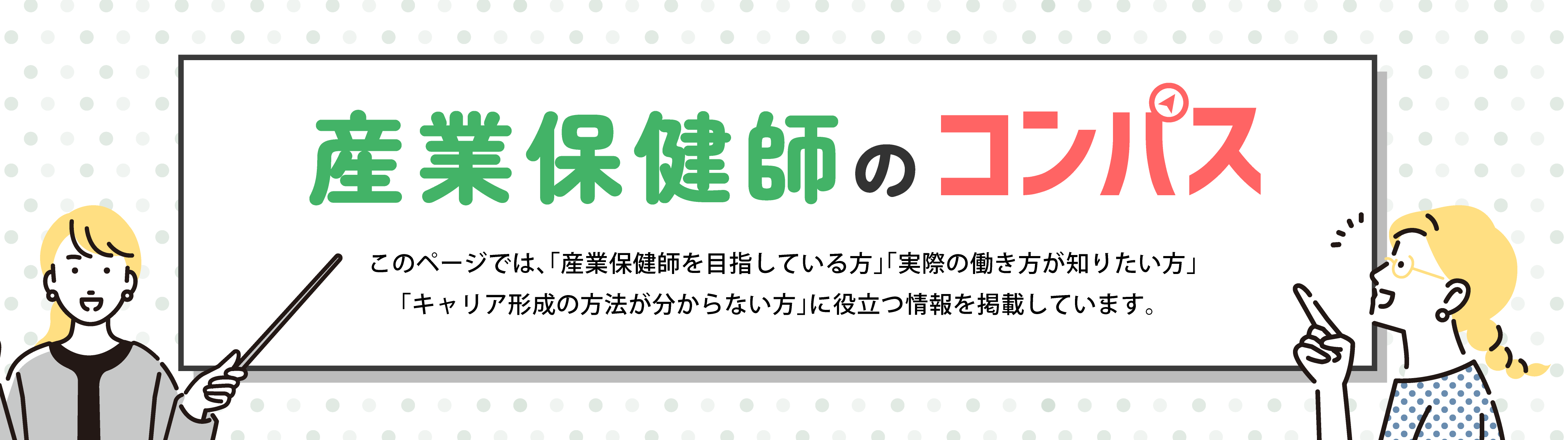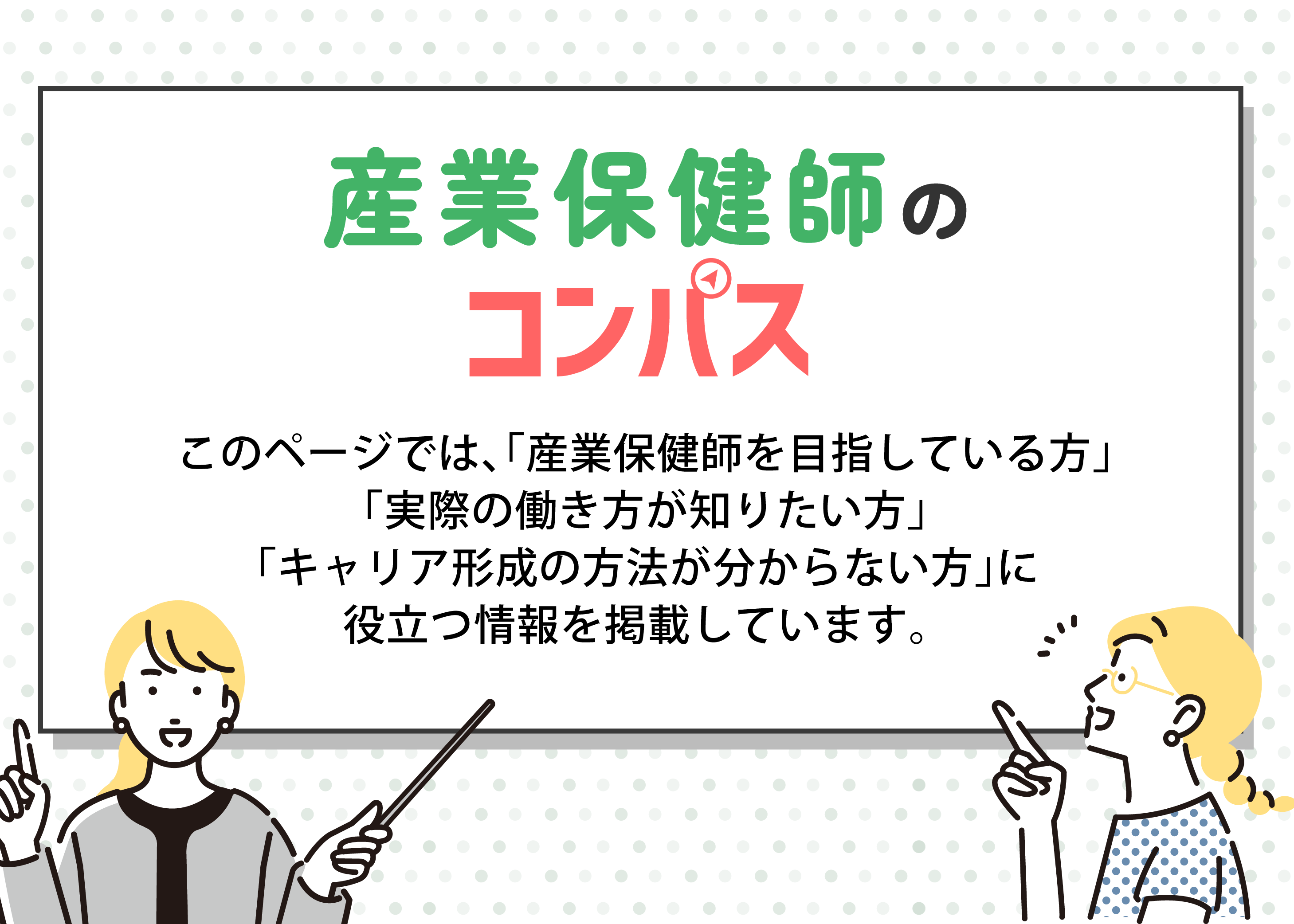産業保健師のコンパス
03 産業保健師として「レベルアップ」するための学び方
Part1. まずは保健師活動と事業場を知ろう
新任の「産業保健師」として入職し、基本的な業務に慣れてきた皆さん。キャリアをスタートしたばかりの時期は、日々の業務をこなすだけで精一杯だと思います。
しかし、ふと「自分のいる場所や進む道はこれで良いのかな?」と思い悩んだりすることはありませんか? 自己成長の道筋が見えにくい環境で仕事をしている方も多いのではないでしょうか?
産業保健師として着実に学習してレベルアップしていくためには、「基本」を疎かにはできません。このページでは、保健師活動の基本と、産業保健師のフィールドである「事業場※」について解説します。
※事業場:産業保健師が所属するのは会社や健康保険組合、労働衛生機関・健診機関、保健指導(受託)機関等、さまざまです。
本稿では、産業保健師の所属組織を総称して「事業場」とします。
保健師活動の「基本」
基本その1:現場を知ること

保健師活動の基本は、 現場を知ることです。
現場を知るとは、対象とする人々(社員)や、人々のいる場所(職場)に実際に足を運び、そこではどのようなことが行われ、どのような特徴があるのか確かめてみることです。地区踏査や職場診断などと称される場合もあります。
そうする中から、個人や集団の健康課題を見つけることができ、適切なタイミングでその課題に取り組んだり、解決に向けた対策をチームで検討し、計画した施策を進めたりすることができます。
保健師としての自分が実施したい対策を、上司や事業場の理解を得て実行するためには、現場の皆さんから聞いた声や、現場のデータによる裏付けが、とても大切です。自分なりにどんなに一生懸命頑張っていても、「現場」の問題が反映されていなければ、説得力は持たせられません。
基本その2:公衆衛生看護の視点
また、その際に重要となるのが、公衆衛生看護の視点です。
これは単に目の前の問題に対処するだけではなく、その背景にある要因も把握・分析し、根本的な解決策まで見出す姿勢を意味します。
個々の対応をする中で「同じ職場の、他の人はどうなんだろう」「この組織では、いま問題が起きているのかもしれない」「もしかすると、こんな状況なのかもしれない」といったところまで思いを馳せ、場合によっては周辺の人から話を聞いたり、職場巡視の際に様子を見たりしながら、真因を見つけて解決の糸口を探すことも、大事な活動となってきます。
「事業場」と保健師活動
まずは「事業場」を知ろう

言うまでもなく、産業保健師の活動の場は、会社や健康保険組合をはじめとした「事業場」です。「保健師」である以前に「事業場の一員」であることを忘れてはなりません。
企業活動の最大の目的は「利益の追求」です。この中で実施される「産業保健活動」は、すべての雇用者の健康を守り、生産性の向上に貢献する役割を担っています。
そのため、産業保健師は事業場の経営理念や事業内容、組織構造、企業文化などの情報を十分に収集する必要があります。そして、それらから産業保健活動に生かせそうな「事業場の特徴」や「社員の強み」をアセスメントできるようになると、事業場の理解も得られやすい活動がしやすくなるかもしれません。
具体的に意識したいポイント
- 所属組織の事業内容や経営方針を把握する
- 職種や部門ごとの業務内容や特性を理解する
- 歴史や社風、企業文化を知る
- 安全衛生に関する事業場の方針や体制を把握する
上記を基に、事業場の強み・弱み、産業保健活動に生かせそうなリソースをチェック!
「事業場」の中で必要な保健師活動
産業保健師の役割は事業場によって異なりますが、一般的には以下のような活動を行います。
産業保健師の役割
- 健康診断の実施と事後措置
- 過重労働対策
- 職場環境改善(快適職場形成支援)
- 生活習慣病予防
- 健康教育・健康増進活動
- メンタルヘルス対策
- 復職支援
これらの活動を効果的に行うためには、事業場の特性や従業員のニーズを踏まえたうえで、事業場の「安全衛生年間計画」に基づく「産業保健計画」を策定し、優先順位を付けて戦略的に取り組むことも重要です。
事業場によっては、産業保健師が重要と考える活動と、組織が重視する業務が異なる場合が多々あります。そのような時は、まずは組織人として組織の指示命令に従い活動をしながら、保健師が考える重要な活動についての情報収集やそのまとめなどができる時間も捻出できるよう工夫しましょう。
こうして日頃から課題をまとめ提案策を準備しておけば、年度区切りや上司との面談などの「ちょうど良いタイミング」を見計らい、相談提案してみることも可能となります。
~川下から川上の問題を捉える~
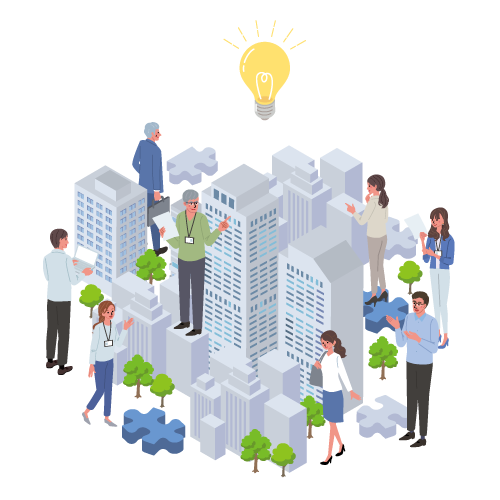
公衆衛生看護の視点を持つ保健師活動として特徴的なことの一つに「川下から川上へ」という考え方があります。
これは、現在表面化している健康問題(川下)から、その原因となっている組織的・環境的要因等(川上)を探り、川下だけではなく川上においても対策を講じるというアプローチです。
たとえば、転倒による労働災害が増加している職場があるとします。
川下の対応としては、労災が発生した付近に注意喚起を掲示したり、負傷者への個別対応がありますが、川上の対応としては作業環境(滑りやすい個所、躓きやすい個所がないか等)や作業(作業中の衣服や靴、作業内容や時間等)の見直し、労働者の健康状態・傾向の把握(労働者の年代、貧血の有所見率)などが考えられます。
産業保健師として成長するためには、この「川下から川上へ」の視点を常に意識し、一人の問題は多数の人の問題でもないかという視点を持ちながら、一人で行動することなく、関係者と課題を共有・検討し、実践することが重要です。
制作:「産業保健師のコンパス」編集チーム