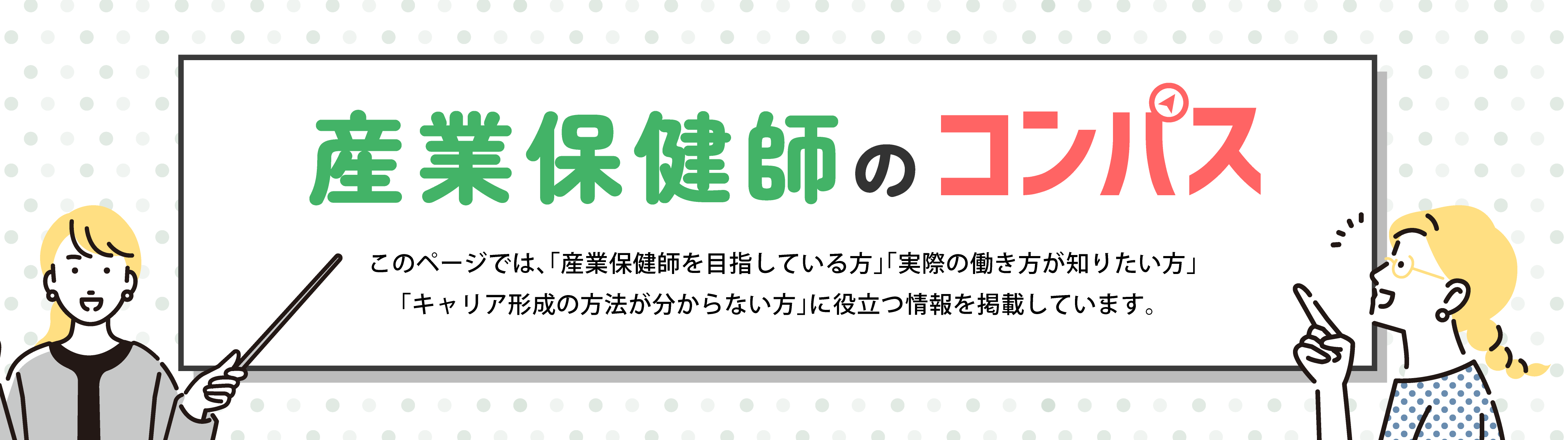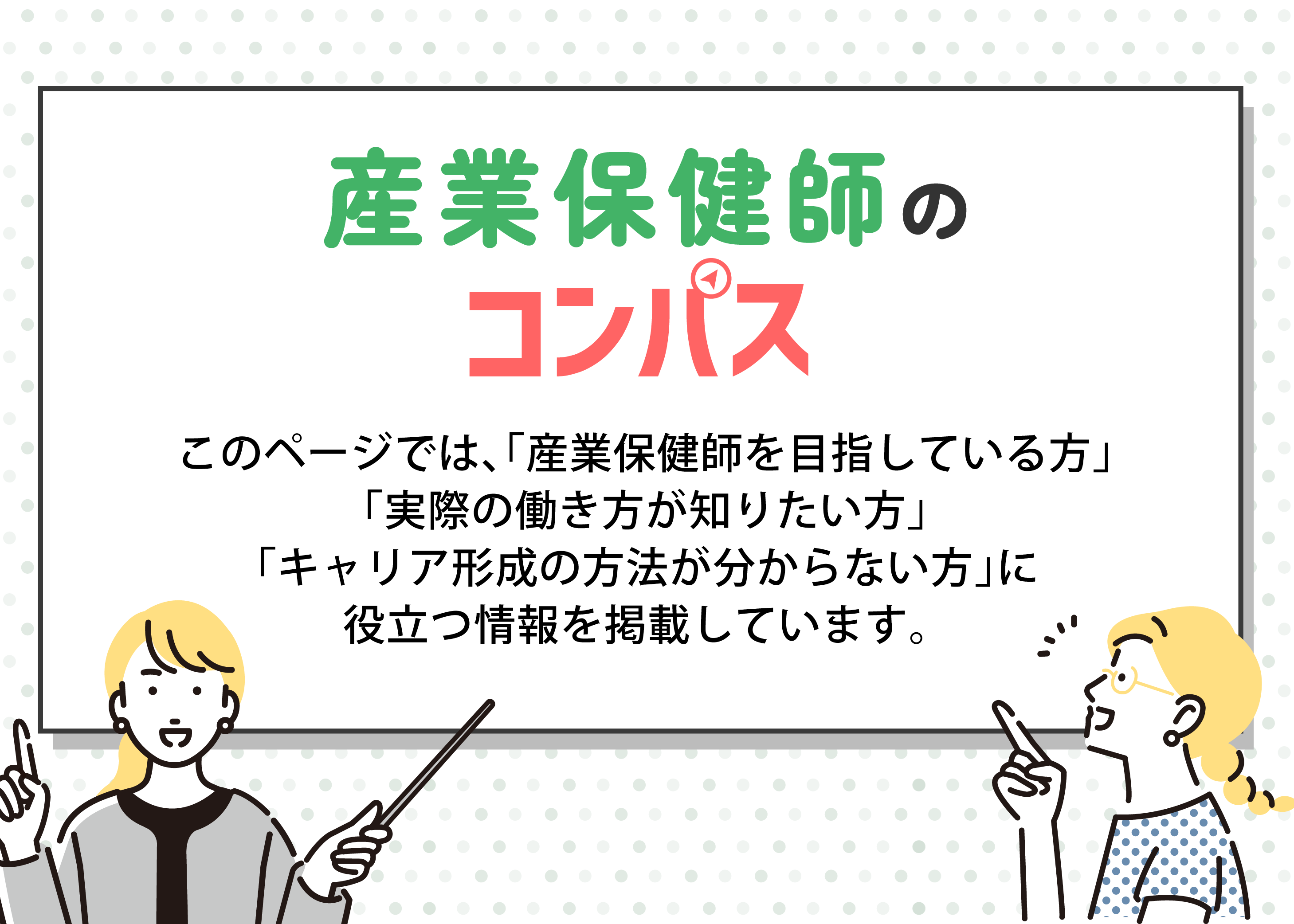産業保健師のコンパス
03 産業保健師として「レベルアップ」するための学び方
Part2. キャリアを描く産業保健師の学び方:悩みを越えて成長するヒント
産業保健師として成長したいと思っても、実際には自己学習が難しい状況に直面することが少なくありません。その理由を考えると共に、自己学習の道しるべとなるキャリアラダーや学習の機会をご紹介します。
産業保健師の自己学習が難しい理由
ひとり職場問題について
多くの産業保健師は「ひとり職場」で働いています。つまり、同じ職場に先輩保健師や同僚保健師がいないケースが多いです。これにより以下のような問題が生じることが考えられます。
- 専門的な知識やスキルを直接学ぶ機会が少ない
- 業務上の疑問や課題に対する自身のアプローチが的確かどうか、客観的な指導や意見が得られない
- 業務上の不安や悩みを相談できる相手がいない
- 自分の活動を評価してもらえる機会が限られている
- 専門職としてのアイデンティティを確立しにくい
また、このような状況では「独自路線(独りよがり)」になることも懸念されます。その解決のためには外部のネットワーク(仲間、同業の先輩など)や研修・勉強会などを積極的に活用することが重要です。
「事業場」における保健師活動ならではの難しさ
企業内での保健師活動には、以下のような特有の難しさがあります。
- 利益追求と健康管理の両立
- 多様な職種・部門との連携
- 経営層への活動の価値の説明
- 限られた人員や予算内での活動
- 「予防」における成果の可視化の難しさ
これらの課題に対応するためには、保健師の基礎教育だけでは十分に習得できない能力も必要となります。
- 組織構造の理解:他組織との連携を図るためには、まず上司の理解を得る必要があることなど
- 企業活動の理解:企業の目的と産業保健の目的は必ずしも一致するものではないことなど
- コミュニケーション能力:情報収集のために必須であるばかりではなく、チームで活動するために重要
- マネジメントスキル:仕事に対する責任感を持ちチームをまとめ目標に向かって進んでいく戦略や意思決定ができる
- データ分析能力:目的に沿った適切な情報を集め、分析し戦略や構想の根拠が作れる など
「キャリアラダー」活用のススメ
自分を育成するための「フレームワーク」
自己成長の道筋を明確にするためには、「キャリアラダー」の活用がおすすめです。キャリアラダーとは「キャリア(経歴)」と「ラダー(はしご)」のふたつの言葉を組み合わせた言葉で、自己評価や成長の目安を把握するために使うことができます。
キャリアラダーを活用するメリット
- 現在の自分のレベルを客観的に把握できる
- 自分の得意分野・不得意分野を確認できる
- 次に目指すべき目標が明確になる
- 必要な知識やスキルが具体的にわかる
- 計画的に学習や経験を積むことができる
産業保健師として必要なスキルや経験は「さまざま」です。段階的に積み上げていくことができるものもあれば、道筋や視点を変えてアプローチしなければならないものも多々あります。
そして、職場の環境や業務内容の違いなど、産業保健師の置かれる立場は、まさに「人それぞれ」です。
つまり、スキルや経験を培っていく道のりは、一本道ではありません!
ジャングルジムでてっぺん(ゴール)を目指す時に、いろいろなルートが選択できることを思い浮かべるとイメージしやすいかもしれません。
「キャリアラダー」は、専門職におけるスキルや経験の段階的な進展を、大枠として捉えるための「フレームワーク」として活用することができます。
自分の状況を俯瞰的に見渡すことで、現在の自分に必要な能力がどの程度、身についているかを自己評価し、不足している部分を補うための学習計画を立てるために非常に有用です。
ポイント:「スキルチェック」「キャリアラダー」を適材適所で組み合わせよう
「スキルチェック」は、ツールやテストで「専門職が持っているスキル・知識」を具体的に評価することにより、個々のスキルレベルを把握する時に有用です。つまり、細分化が得意と言えます。
「木を見て、森を見ない」ということわざがありますが、木と森、どちらも見ることができるのが、産業保健師の理想像といえるでしょう。
スキル・知識を大枠で捉えられるキャリアラダーと、細分化して把握できるスキルチェック。適材適所で組み合わせて「いいとこ取り」ができるように活用しましょう!
厚生労働省「自治体保健師のためのキャリアラダー」
厚生労働省が平成28年に公表した「自治体保健師の標準的なキャリアラダー」を紹介します。その名の通り「自治体」保健師向けですが、保健師活動の基本的な指標として、産業保健師に参考にすることができます。
新任期保健師も使用できる「専門的能力に係るキャリアラダー」では、キャリアレベルの定義として、以下の3つがA-1~A-5までの5段階のキャリアレベルで表現されています。
- 所属組織における役割
- 責任を持つ業務の範囲
- 専門技術の到達レベル
(クリックすると、大きな画像が表示されます)
 出典:厚生労働省「保健師に係る研修のあり方等に関する検討会最終とりまとめ(概要)」より
出典:厚生労働省「保健師に係る研修のあり方等に関する検討会最終とりまとめ(概要)」より
そして、以下の6つの能力が5段階で評価されています。
- 対人支援活動
- 地域支援活動
- 事業化・施策化のための活動
- 健康危機管理に関する活動
- 管理的活動
- 保健師の活動基盤
また、さらにレベルアップした「管理職保健師に向けた能力に係るキャリアラダー」も作成されており、管理的活動に焦点を当てた「B-1~B-4」レベルが策定されています。
「保健師に係る研修のあり方等に関する検討会最終とりまとめ~自治体保健師の人材育成体制構築の推進に向けて~」の公表(厚生労働省)
日本産業保健師会「産業保健師版キャリアラダー」について
産業保健師の職能団体・日本産業保健師会が定期的に開催している「新任期産業保健師養成研修」では、同会が制作した「産業保健師版キャリアラダー」が紹介されています。
このキャリアラダーは「行政保健師のためのキャリアラダー」を参考に、産業保健師のフィールドにあわせて「組織」での活動を見据えた内容となっています。
詳しく内容を知りたい方は、ぜひこの研修会に参加してみてください!
トピックス・レポート「2022年度『新任期産業保健師養成研修』『産業保健師リーダー養成研修』」(保健指導リソースガイド)
より詳しく知りたい方にオススメの研修
自己学習を補完するための研修についてご紹介します。外部の研修に参加することで、新しい知識を得るだけでなく、他の産業保健師とのネットワークを構築する機会にもなります。
産業保健総合支援センターで実施している研修
各都道府県の産業保健総合支援センターでは、産業保健関係者向けの様々な研修が無料で提供されています。産業保健師に特化した研修だけでなく、メンタルヘルス、過重労働対策、健康保持増進など、幅広いテーマの研修が行われています。
産業保健専門職育成現場レポート① 埼玉産業保健総合支援センター「産業看護職交流研究会」(保健指導リソースガイド)
日本産業保健師会 新任期養成研修
日本産業保健師会では、入職1~3年目の産業保健師を対象とした「新任期養成研修」を定期的に開催しています。この研修では、以下のような内容が学べます。
- 産業保健師の役割と基本活動
- 産業保健計画の立案
研修は講義だけでなく、前期・後期の2回構成を活かしたケーススタディや、グループワークも含まれており、実践的な学びの場となっています。また、同じ立場の新任期の産業保健師との交流の機会にもなります。
その他にも、日本産業衛生学会や日本看護協会などでも有益な研修が開催されていますので、積極的に参加することをオススメします。
まとめ
産業保健師として成長していく道のりは決して一本道ではなく、自身の立ち位置や環境に応じた柔軟な学びが求められます。キャリアラダーやスキルチェックで現在地を把握し、外部の研修やネットワーク等を活用することで、新たな視点や気づきを得ることが可能となります。
迷ったときこそ、自分を俯瞰し、学び直す機会と捉えることが、次の一歩につながるはずです。本章が、今後の活動のための参考になれば幸いです。
制作:「産業保健師のコンパス」編集チーム