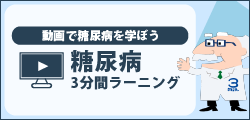No.1 老年期の医療と介護をつなぐには
ノンフィクション・ライター
中澤 まゆみ
この3月に『おひとりさまでも最期まで在宅』という本を出しました。認知症になった15歳年上の友人の介護を引き受け、その過程で"おひとりさまシリーズ"を書き続けるなかで、老齢期の医療のことがずっと気になっていたからです。
誰でもそうでしょうが、介護の当初は動顛、驚愕、七転八倒の毎日です。私の場合は「患者の権利」や「当事者の尊厳」をなまじ知っていた、少々頭でっかちのライターでしたから、理想と現実のギャップにおおいに悩みました。
認知症や「老年医学」についてさまざまな本を買い込み、これからの彼女にはパーツごとではなく「からだ丸ごと」の医療が必要・・・と、近隣の医療機関を当たりましたが、彼女は「先生が若いからイヤ」「病院が大きすぎるからイヤ」「遠いからイヤ」のイヤイヤづくし。しかも、地域の医療機関についての情報はなかなか見つかりません。
いま思えば彼女は、「なぜ自分が認知症に」という怒りや不条理感、「これからどう生きていったらいいのか」という不安、「記憶がなくなる」ことの恐怖など、一気に押し寄せてくる混乱と葛藤を、私にぶつけていたのでしょう。とはいえ、ヘルパーも拒否、デイサービスも拒否、お弁当も文句たらたら・・・。
彼女を支える自信がなくなって、「有料老人ホームに行かない?」と勧めたことも何度かありましたが、「集団生活はイヤ」と言い張られ、「お願いだから家にいさせて」と泣きつかれる始末。半ば根負け、半ば「それなら、とことん」の覚悟で、彼女の在宅生活を支えることになりました。
知人の協力で優秀なケアマネジャーに出会い、二人三脚の呼吸も合って介護はうまく回るようになったものの、問題は医療でした。老年期の病気はドミノ倒しのようにやってきますが、彼女の場合も例外ではありません。ようやく老年医療に慣れた「内科」と「精神科」のある小規模病院を見つけましたが、「精神科」は近隣の大病院からの出向で医師が毎年変わるので、毎回いちから出直しです。
心筋症になった彼女が入院した地域の中核病院には、「精神科」を含めたさまざまな診療科がありました。「ここなら、からだ丸ごとOKかも」と期待を抱いたのですが、肝心の「精神科」は若い患者が中心。認知症の人の治療には不慣れだったので、とても彼女をまかせることはできませんでした。
入退院の環境の変化で認知症が進んだのか、退院後、「拒食状態」が深刻になってきたため「入院で状態改善を」と、退院先の病院を含め、近隣の病院を片っ端から当たりました。しかし、認知症の彼女を受け入れてくれる病院はありません。ようやく入院させてくれたのは都下の精神病院。「拒食」はなんとか落ちついたので、一息つきましたが、いい「かかりつけ医」は依然として見つかりません。