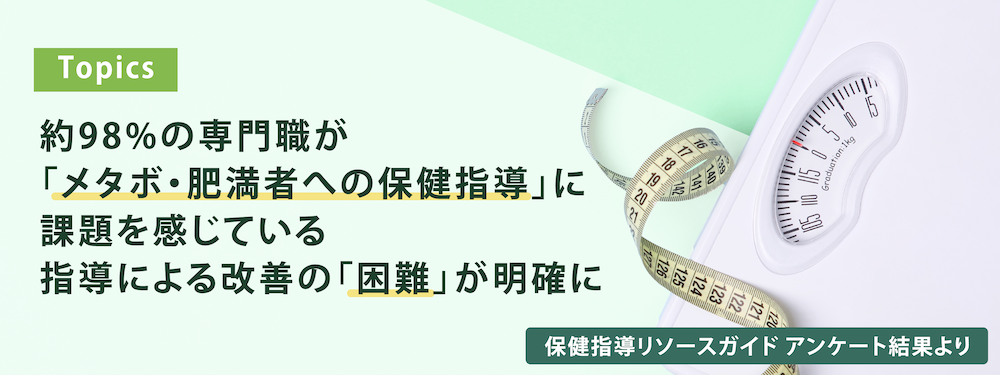オピニオン/保健指導あれこれ
食文化・食習慣
No.3 漬物に注目してみよう
医療・保健ジャーナリスト
2014年09月19日
なぜ漬ける、なぜ食べる?
皆さんは漬物に対してどのようなイメージをもっていますか?きっと多くの方に「減塩」の二文字が浮かんだのではないでしょうか。 確かに食塩の取りすぎは体によくないです。けれど漬物ほど地域の食文化も如実にあらわしているものもないわけで、目の敵にするだけでなく、冷静に自分の担当する地域でどのような漬物文化があるのか知っておくことも大切だと思います。 とくに若い世代の方々は、核家族化が進み、嗜好の違いもあって自分の生まれ育った地域の食文化を理解していないケースも多々あります。減塩しましょう、漬物を減らしましょう、とやみくもに口にするだけでなく、
・いつ、どのくらいの量を作っているのか
・どのような味付けなのか
・いつ、どのように食べているのか
・なぜ作るのか
・なぜ食べるのか
など、漬物文化の背景を理解したうえで対策を練ることが重要だと思うのです。 では、その文化をどこで知るのか?
私はやはり、スーパーマーケットをオススメします。それでは今回も、いくつかの地域のスーパーを見てみましょう。
北海道編
冬が長い北海道では、秋に大量の漬物を作る光景を見ることができます。写真は10月に上富良野町のスーパーマーケットで撮ったものですが、入口の真正面にどーんと鎮座していたのが漬物用品大集合と掲げられた特設コーナーでした。
そこには1袋2kg単位の酒粕をはじめ、中双糖(黄ざらめ)、米ぬか、こうじ、みりん。さらに漬物入れ用の容器がズラリ並ぶ様は、さぁ、皆さん、漬物の季節ですよ!といわんばかりの状態です。


「えっ、普通ですよね?」
お約束の答が返ってきたことは言うまでもありません。 しばらく観察していると、よく売れていました。お客さんたちも馴れたもので、多くの方々が軽トラックなどでお店に乗りつけ、お店の人に手伝ってもらいながら、これらの野菜を「どすん!」と積み込んで意気揚々と帰って行くのです。 あれだけ大量の野菜を漬けるなんていったい何人家族なのだろう?もしかすると、冬に野菜を食べるための習慣?
正確な理由は分からなかったものの、毎年同じような光景が繰り返されていることは理解できました。 つまり、この地で大量の漬物作りは大切な年中行事のひとつであり、作ること、食べることを制限するのはひと筋縄ではいかないことが分かります。安易に「漬物は体に悪いから」などと話をしても、簡単に受け入れてもらえないことも容易に想像つきますね。
長野編
北海道と同様、10月の長野県安曇野市のスーパーマーケットで見かけた売り場もご紹介しましょう。こちらも入口の真正面に漬物コーナーがありまして、お約束の漬樽から、いりぬか、みりん、中双糖、塩、キムチの元、唐辛子などが並んでいます。
また、漬物用の味噌や、味噌からとれる「みそたまり」と醤油を合わせた調味料もありまして、野沢菜をはじめ、肉や魚にも合うとのこと。実際の漬物を食べたわけではありませんが、なんだか味が濃そうだなぁーと思ってしまうのでした。



岐阜編
岐阜の高山といえば朝市が有名ですね。ここでは様々なものが売られていますが、冬場に目を引いたのは鮮やかな色合いの、赤カブ漬でした。それは見事な色をしています。


まとめ
食と健康を考える時、保健関係者はつい栄養成分重視になってしまいます。でも、それだけを理由に保健指導をしても煙たがられるだけです。冒頭でも書いたように、なぜそれを食べるのか、どのような歴史があるのか、しっかり理解したうえで、地域の人々と共に食と健康を考えるようにしたいものですね。
「食文化・食習慣」もくじ
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.
「地域保健」に関するニュース
- 2025年05月16日
- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善
- 2025年05月16日
- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少
- 2025年05月12日
- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要
- 2025年05月12日
- 都市に自然を増やすと健康増進につながり地球温暖化対策にも 木を植えて環境を改善すると赤ちゃんの体重も改善
- 2025年05月12日
- ビタミンDは女性の健康のために必要 多くの人が不足している ビタミンD不足が簡単に分かる質問票