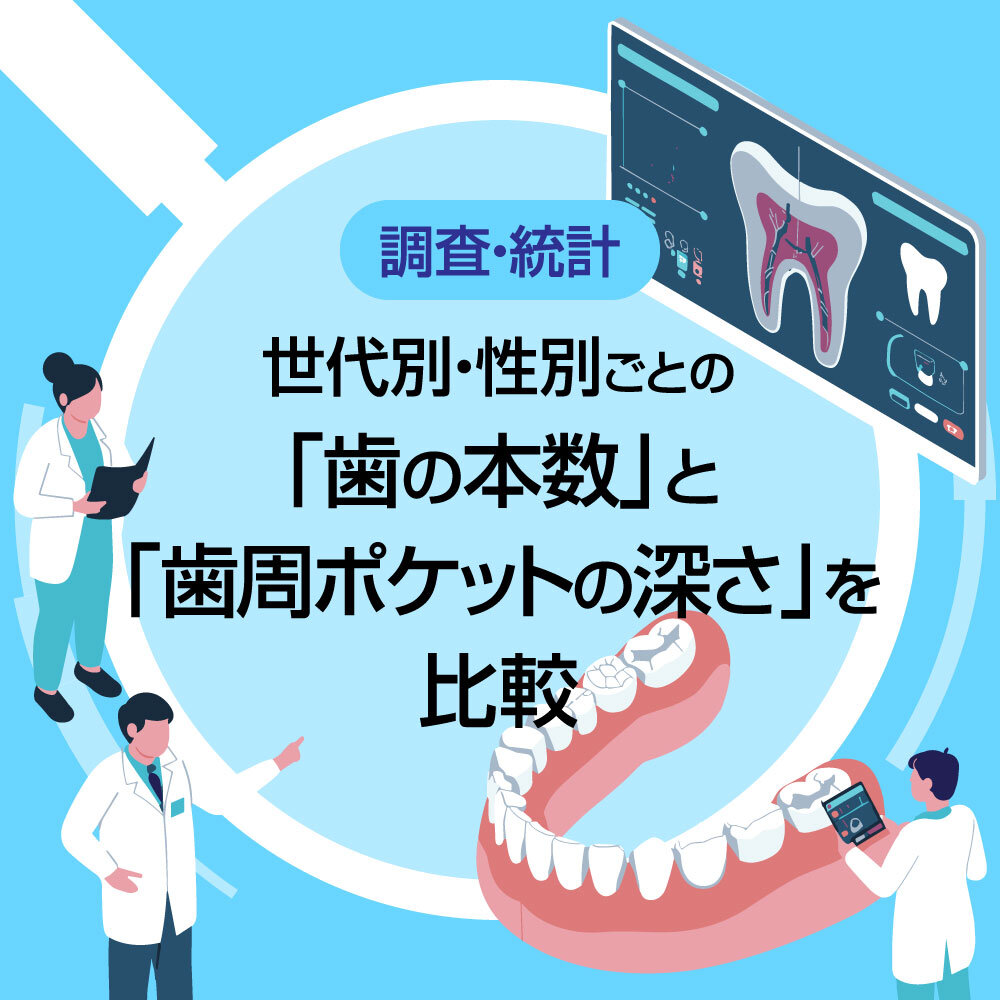オピニオン/保健指導あれこれ
保健師の活動と放射線について
No.2 保健師活動に必要な放射線に関する基礎知識とは
2015年06月25日
1. 私たちは放射線に関して知らないことを知る
|
菊地 透
前自治医科大学、原子力安全研究協会研究参与
|
|
経歴:
1949年に東京で生まれ、放射線防護に係って45年間が過ぎた。この間に東京大学原子力総合センター、自治医科大学医学部RIセンターに勤務。現在は、公益財団法人原子力安全研究協会研究参与、医療放射線防護連絡協議会総務理事を担当。また、福島原発災害に関連して、福島県及び隣県で多数講演し、「いまからできる放射線対策ハンドブック」(2012)を女子栄養大学の香川靖雄先生と出版。 |
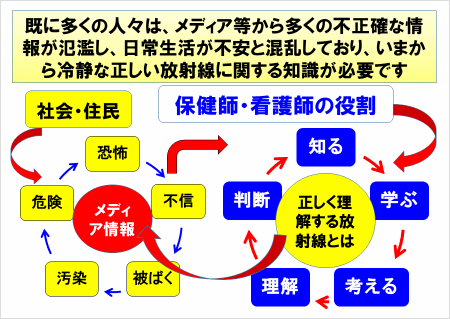
2. 放射線は知ることから始まります
(1)以外と知らない身の回りの放射線
私たちの地球は、大気層が宇宙放射線を1/100に減少する放射線から守られた惑星で、年間約0.4mSv(ミリ・シーベルト)の被ばくを宇宙放射線から受けています。
また、地球誕生時代から存在するウラン、トリウムや放射性カリウム等が、大地、空気、食べ物等に含まれており年間約2mSvで、合計すると年間平均2.4mSvの放射線を受けながら生活しております。なお、地球上では年間1~10mSvの放射線を絶えず受けながら私たちは太古の昔から生活しています。
そして、地球上の自然放射性物質は、飲食物を通じて私たちの体に取り込まれており、成人60kgの方は7000ベクレル程度を絶えず保有しています。
(2)放射線の人への影響と防護

3. おわりに
福島原発災害から4年経過して、私たちは放射線に関する基礎知識の無いままに図に示すとおり、多くの曖昧な放射線情報がメディア等から氾濫し、恐怖・不信・被ばく・汚染などから放射線は危険と認識されるようになりました。
このような曖昧情報に依存するのでなく放射線に対して正しく理解することが、今後の原子力災害の復旧・復興に不可欠であり、正しく学び、知って、考えて、自ら冷静に評価・判断する活動が社会・メディア情報から発信されることが重要です。
そのために保健師らが中心に住民と共に放射線防護活動を継続することから、住民の原子力災害に伴う健康影響から守る大きな役割と期待されます。
「保健師の活動と放射線について」もくじ
- No.1 原発事故後の復旧期における保健師活動―放射線防護文化をつくるために
- No.2 保健師活動に必要な放射線に関する基礎知識とは
- No.3 保健師の実践へのヒント(1) ベラルーシ視察報告から学ぶ
- No.4 保健師の実践へのヒント(2)川内村における放射線専門保健師の活動報告
- No.5 保健師の実践へのヒント(3)住民への放射線に関する支援(相談・教育)
- No.6 放射線と公衆衛生看護
- No.7 対象別協働実践報告(1) 母子
- No.8 対象者別協働実践報告(2) 高齢者
- No.9 対象別協働実践報告(3) 精神・社会的弱者
- No.10 対象別協働実践報告(4) 学校との協働実践
- No.11 保健師の健康支援に必要な情報と媒体
- No.12 保健師と看護学生に放射線を教える・学ぶ
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.
「地域保健」に関するニュース
- 2025年11月20日
- 世代別・性別ごとの「歯の本数」と「歯周ポケットの深さ」を比較-令和4年「歯科疾患実態調査」より(日本生活習慣病予防協会)
- 2025年11月13日
- 青少年の健康活動についてコロナ流行前〜後で社会経済格差を調査 琉球大学
- 2025年11月06日
- 日本人高齢者全体のフレイル割合は8.7% 実態を全国レベルで可視化
- 2025年10月16日
- 自治体向け『認知症発症/進行のリスク早期発見の手引き』公開 実証研究で明らかに
- 2025年10月16日
- 世代別・性別ごとの「飲酒量と頻度」を比較-令和4年(2022)「国民生活基礎調査」の概況より(日本生活習慣病予防協会)