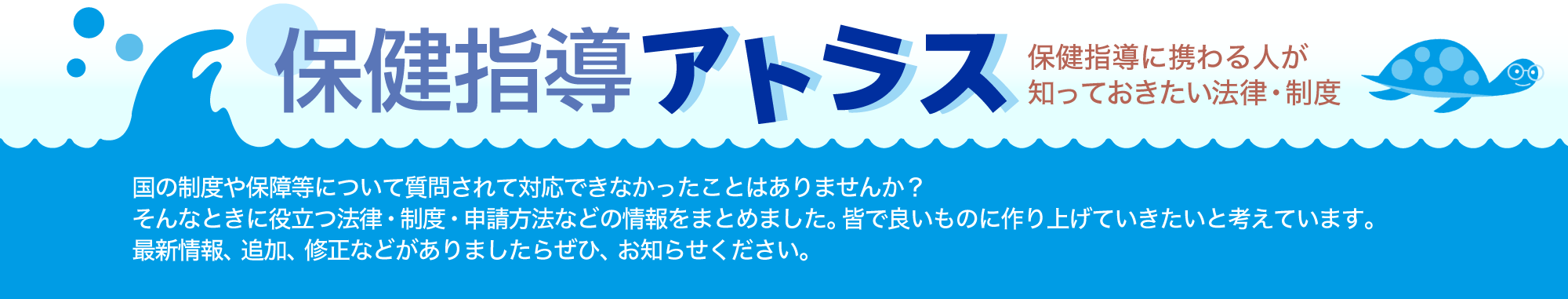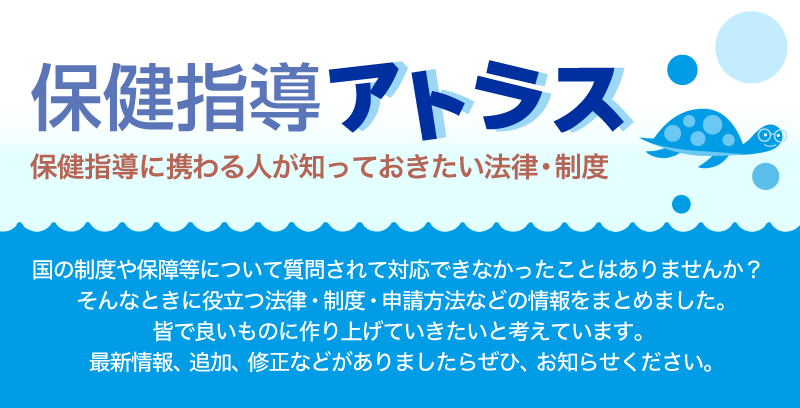産業保健
労働安全衛生法公布:昭和四十七年 最終改正:令和四年 施行日:令和七年六月一日
目 的
職場における労働者の安全と健康の確保と、快適な職場環境の形成の促進。
概 要
事業主及び労働者の責任・実施事項衛生委員会の設置、産業医の選任、健康診断の実施、就業上の措置等 労働基準法や労働安全法施行令・労働安全衛生規則等とも関連あり。
関連
・働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年) いわゆる働き方改革関連法。労働者が各々の事情に応じて多様な働き方を選べる社会の実現を目指し、以下の8つの法律を改正する旨が定められている。 ・労働基準法 ・労働安全衛生法 ・労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 ・じん肺法 ・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(旧 雇用対策法) ・労働契約法 ・短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法) ・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)参考
・働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成三十年政令) 施行日:令和二年四月一日 ・建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A(令和5年7月6日公表/厚生労働省労働基準局)情報源へリンク 2024年4月以降、建設業では、災害時における復旧及び復興の事業を除き、時間外労働の上限規制が原則通りに適用される。 災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されることとなる。
■関連適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト「はたらきかたススメ」
-
労働基準法や労働安全法施行令・労働安全衛生規則等とも関連があるよ。
労働基準法公布:昭和二十二年 最終改正:令和四年 施行日:令和七年六月一日
国家公務員等の一部を除く、日本国内のすべての労働者に原則適用。 労働条件の確保・改善、労働者の安全と健康の確保、的確な労災補償の実施、仕事と生活の調和の実現等について定められている。 労働に関する重要な法律。雇用や労務管理、母性保護に関し、妊産婦の就業禁止・就業制限や、本人が希望した場合の労働時間の制限、産前産後の休業等についても定められている。
参考
・労働基準法に関するQ&A(厚生労働省) ・年5日の年次有給休暇の確実な取得(厚生労働省)情報源へリンク 2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられた。
・自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)(厚生労働省) 施行日:令和6年4月1日情報源へリンク トラック、バスおよびタクシー・ハイヤーのドライバーの労働時間に関する上限などを定める基準。「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」により、改善基準告示が改正された。
・自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト 自動車運転者の長時間労働改善に向けた情報を掲載している。労働安全衛生規則公布:昭和四十七年 最終改正:令和六年 施行日:令和八年七月一日
情報源へリンク 労働安全衛生法及び労働安全衛生法施行令の規定に基づき、並びに同法を実施するため、労働安全衛生規則を次のように定められている。
関連
・化学物質による労働災害防止のための新たな規制について~「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」の公布~(厚生労働省/令和4年5月31日)情報源へリンク 化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く)の原因となった化学物質の多くは、化学物質関係の特別規則の規制の対象外となっている。 本改正は、これら規制の対象外であった有害な化学物質を主な対象として、国によるばく露の上限となる基準の策定、危険性・有害性情報の伝達の整備拡充等を前提として、事業者が、リスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入するもの。
参考
・「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」の報告書(厚生労働省/令和3年7月19日) ・一人親方等の安全衛生対策について(厚生労働省)情報源へリンク 2023年4月1日より、作業を請け負わせる一人親方等や同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられた。
じん肺法公布:昭和三十五年 最終改正:平成二十九年 施行日:令和二年四月一日
じん肺に関し、適正な予防及び健康管理その他必要な措置を講ずることにより、労働者の健康の保持その他福祉の増進に寄与することが目的。 健康管理(じん肺健康診断の実施、管理区分の決定、健康管理のための措置、政府の援助等について記載。
労働者災害補償保険法公布:昭和二十二年 最終改正:令和四年 施行日:令和七年六月一日
目 的
・業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して必要な保険給付を行い、労働者の社会復帰の促進、当該労働者とその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、労働者の福祉の増進に寄与することが目的。 ・政府が管掌。 ・業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行う。 ・業務災害に関する保険給付は、療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付 ・遺族補償給付 ・葬祭料・傷病補償年金・介護補償給付 。 ・二次健康診断給付 労働安全衛生法による定期健康診断の結果、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査で、省令で定めるものが行われた場合、その検査を受けた労働者がいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求に基づいて行うもの。内容は、医師による健康診断及び、医師・保健師による特定保健指導
関連
・労働者災害補償保険法の改正について(改正施行日:令和二年九月一日) 複数の会社等に雇用されている労働者への労災保険給付が変更された。 ■「労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~」(厚生労働省)・独立行政法人労働者健康安全機構法(公布:平成十四年 最終改正:令和四年 施行日:令和七年六月一日) 療養施設、健康診断施設及び労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営等を行う。 ※47都道府県の産業保健総合支援センターの設置・運営(委託)を行っている。
参考
・心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正について(改正施行日:令和五年九月一日) 近年の社会情勢の変化や労災請求件数の増加等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」において検討を行い、2023(令和5)年7月に報告書が取りまとめられたことを受け、認定基準の改正を行った。-
産業保健総合支援センターの研修は、無料で受けられるよ
雇用保険法公布:昭和四十九年 最終改正:令和六年 施行日:令和十年十月一日
失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることが目的。 ・政府が管掌。 ・失業給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金、育児休業給付金、介護休業給付金)等がある。 ・雇用安定事業として、高齢者や障害者を雇用する事業主への助成等も行う。 ・教育訓練給付は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合、受給できる。(在職中でも受給可能)関連
・平成29年改正(平成29年法律第14号) 失業等給付に係る雇用保険料率の引下げ、基本手当の拡充、育児休業給付の支給期間の延長、専門実践教育訓練給付の給付率の引上げ等の改正・令和2年改正(令和2年法律第14号) 高年齢雇用継続給付の給付率の見直し、複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者に対する雇用保険の適用、育児休業給付の位置づけの見直しと経理の明確化、2年間に限った雇用保険料率の引下げ等の改正
・新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和2年6月12日) 新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、休業手当を受けることができない労働者に関する新たな給付制度の創設、基本手当の給付日数の延長の特例及び雇用保険の安定的な財政運営の確保を図るための法律を制定した。
参考
・高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律) 公布:昭和四十六年 最終改正:令和四年 施行日:令和四年十月一日 少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律。2025年4月1日以降は希望者全員に65歳までの雇用機会の確保が義務付けられた。 高年齢者雇用安定法改正の概要~70歳までの就業機会の確保のために事業主が講ずべき措置(努力義務)等について~(厚生労働省)(改正施行:令和3年4月1日)-
雇用に関する国の動きは大きく変化しているため、時々は厚生労働省⇒政策について⇒分野別政策の一覧⇒雇用を眺めてみるとよいね。
育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)公布:平成三年 最終改正:令和六年 施行日:令和七年一〇月一日
目的
この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護等休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。