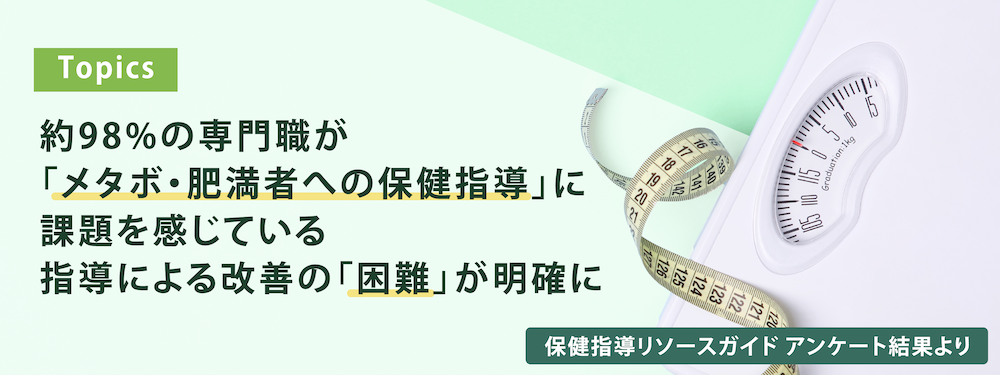ニュース
不妊治療と仕事の両立 9割の女性が「困難」 理解と支援が必要
2015年08月10日

働きながら不妊治療を受けた女性の92%は仕事と治療の両立は難しいと感じ、そのうち4割以上は退職、転職するなど勤務状況が変わったとの調査結果を、不妊で悩む人を支援するNPO法人「Fine(ファイン)」(松本亜樹子理事長)が発表した。
9割以上の女性は「不妊治療と仕事の両立は難しい」と回答
調査はFineが昨年5月から今年1月まで、不妊治療に関心がある2,265人(うち95%が不妊治療経験者)を対象にインターネットで行ったもの。
その結果、不妊治療を経験した2,152人中、仕事との両立が難しいと感じたことがあるのは1,978人(91.9%)であることが判明。
不妊治療では、治療の段階によってはいつ受診が必要になるか予測が立たないため、治療・通院のために仕事を遅刻・早退するなど、急遽スケジュールを変更せざるを得ない人が多くいるという。また理解やサポートが得られにくく、精神的な負担も大きいことが分かった。
治療と仕事の両立が難しいため、「退職」(527人)や「転職」(121人)、「休職」(104人)、「異動」(84人)など、勤務状況を変更した経験を多いことも判明。
就業状況が変わった理由は、「通院回数が多い」(568人)、「診察・通院に時間がかかる」(534人)、「精神的に負担が大きい」(446人)などだった。
また、働きながら治療をしている女性のうち、68.8%が「職場で治療をしていることを周囲に話しづらい」と回答。
「体外受精について伝えた際、『さっさと1回で成功させろ』と言われた。不妊で何年も悩む人が多い中、1回目を始めてもいないのにそういうことを言われてしまい、これから先毎回こういう精神的苦痛を伴うのかと思うと、絶望した」という回答も寄せられた。
仕事と治療の両立ができる環境が女性にとって必要
日本産科婦人科学会の調査によると、日本で体外受精や顕微授精などの生殖補助医療(ART)によって生まれた子供は、2012年は年間3万7,953人に上った。また、日本でARTにより生まれた子供は累計で34万1,750人に上る。
Fineは「出生児全体の約27人に1人がARTにより誕生している。いまや不妊治療をして子どもを授かることは、決して特別なことではなくなった」としている。
しかし、高度な治療には高額な費用がかかる。Fineが実施した調査によると、体外受精や顕微授精1周期あたりに、30~50万円ほどかかり、繰り返し治療を受けると高額な出費となる。
国や自治体による助成制度もあるが、1回の金額は15万円(治療内容によっては7万5,000円)で、回数や夫婦の合算所得制限等があり、さらに女性の年齢制限も設けられるなど、助成金だけで治療費が賄えるわけではないという。
夫婦で費用を工面するために、仕事と治療の両立ができる環境が、女性にとって必要とされている。企業に治療をサポートする制度はまだ非常に少なく、今回の調査でもサポート制度が「ある」と答えた人は、わずか5.9%にとどまった。
「高額な不妊治療費を捻出するために働き続ける当事者が多いが、不妊治療と仕事の両立には大きな困難を伴っており、当事者は板挟みになっている。また、政府も企業も女性の社会進出を推し進める一方で、それをサポートする制度が整っていない」と、Fineは指摘している。
「仕事をしながらでも安心して、妊娠・出産・育児、そして不妊治療ができるよう、国や地方自治体、企業からの理解と支援が必要とされている」と強調している。
NPO法人Fine(ファイン)
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.


「健診・検診」に関するニュース
- 2025年02月25日
- 【国際女性デー】妊娠に関連する健康リスク 産後の検査が不十分 乳がん検診も 女性の「機会損失」は深刻
- 2025年02月17日
- 働く中高年世代の全年齢でBMIが増加 日本でも肥満者は今後も増加 協会けんぽの815万人のデータを解析
- 2025年02月12日
-
肥満・メタボの割合が高いのは「建設業」 業態で健康状態に大きな差が
健保連「業態別にみた健康状態の調査分析」より - 2025年02月10日
- 【Web講演会を公開】毎年2月は「全国生活習慣病予防月間」2025年のテーマは「少酒~からだにやさしいお酒のたしなみ方」
- 2025年02月10日
- [高血圧・肥満・喫煙・糖尿病]は日本人の寿命を縮める要因 4つがあると健康寿命が10年短縮
- 2025年01月23日
- 高齢者の要介護化リスクを簡単な3つの体力テストで予測 体力を維持・向上するための保健指導や支援で活用
- 2025年01月14日
- 特定健診を受けた人は高血圧と糖尿病のリスクが低い 健診を受けることは予防対策として重要 29万人超を調査
- 2025年01月06日
-
【申込受付中】保健事業に関わる専門職・関係者必携
保健指導・健康事業用「教材・備品カタログ2025年版」 - 2024年12月24日
-
「2025年版保健指導ノート」刊行
~保健師など保健衛生に関わる方必携の手帳です~ - 2024年12月17日
-
子宮頸がん検診で横浜市が自治体初の「HPV検査」導入
70歳以上の精密検査無料化など、来年1月からがん対策強化へ