ニュース
「がん治療と仕事両立」を調査 がん発症後の仕事や働き方はどうなる?
2016年06月08日

がん治療と仕事の両立に関しては多くの課題があり、がん患者の多くが「休暇・休業が取りづらい」「収入の減少」といった悩みをもっている――三菱UFJリサーチ&コンサルティングが発表した「がん治療と仕事の両立に関する調査」で、このような実態が明らかになった。
がん罹患後の不安は「再発」「休暇・休業が取りづらい」「収入の減少」
がん患者の生存率上昇や入院期間の短縮傾向から、がん治療を継続しながら働くことへのニーズが高まっている。国の政策としても、2012年に閣議決定された「第二期がん対策推進基本計画」で、働く世代へのがん対策の充実が重点課題として位置づけられた。
しかし、社会の理解は十分とはいえず、がん治療と仕事の両立に関しては多くの課題がある。
正社員として働いていた時にがんにかかり、その後も仕事を続けている人は、再発への不安だけでなく「治療・経過観察・通院目的の休暇・休業が取りづらい」「働き方を変えたり、休職したりすることで収入が減少する」といった就業上の悩みが少なくない――。
三菱UFJリサーチ&コンサルティングが「がん治療と仕事の両立」について調べたところ、罹患後の転職では44%が非正規社員になっている実態が明らかになった。
この調査は、がん罹患時に正社員として働いており、現在も何らかの形で仕事に就いている65歳以下の男女978人(男性670人、女性308人)を対象に行ったもので、がん治療と仕事の両立についてや職場での働き方の変化、支援制度の利用状況などを調べた。
調査では、男性は50歳代での罹患がもっとも多く(51%)、40歳代(35%)を合わせると86%に上った。罹患時の役職は約半数(45%)が課長以上の管理職だった。女性は40代での罹患が約半数(48%)であり、30歳代(30%)を合わせると78%が40歳代以下での罹患だった。
がん進行度「2期以降」は体力面から働き続けるのが困難
勤務先は、罹患後も同じ職場で働いている人が86%。継続できた理由として多く挙げたのは「職場の上司の理解・協力があったため」「職場の同僚の協力があったため」で、上司や同僚の理解・協力が就業継続につながることが示された。
一方、退職の後に転職・再就職して現在も働いている人が14%だった。退職した理由でもっとも多かったのは、がんの進行度が「1期」以前では、「治療と仕事を両立するために活用できる制度が勤務先に整っていなかったため」がもっとも多く17%だった。「2期以降」になると「体力面等から継続して就労することが困難であったため」が多くなり33%に上った。
転職していない場合9割以上が正社員のままだったが、転職した場合は約4割が、正社員からパート・アルバイト、契約社員や派遣社員といった非正社員に変わっていた。
がん罹患後の労働時間を見ると、1年間は週あたり「40時間未満」が約4割を占めた。罹患後は一時的に労働時間を抑える傾向が多くみられた。職場では「軽微な業務への転換や作業の制限」(19%)、「勤務時間の短縮」(18%)、「所属部署の変更など、配置の変更」(10%)といった対応がとられている。
就業継続には上司・同僚の理解と協力が欠かせない
がん罹患後の就業継続には上司・同僚の理解と協力が欠かせないが、そのためには企業の両立支援制度が整っていることが必要だ。働いている企業の両立支援制度について、その有無を見ると企業の規模により大きな差がある。
両立支援制度は、規模の大きな企業ほど整備されている傾向がある。利用した制度などで上位に挙がっていたのは、「有給休暇」「半日・時間単位の休暇制度」「遅刻・早抜けなどの柔軟な対応」などだった。
例えば「半日・時間単位の休暇制度」は従業員1,000人以上の企業で68%が「あった」とする一方で、1~99人の企業では38%にとどまった。「治療目的の休暇・休業制度」は同50%に対して同28%。「失効年次有給休暇の積立制度」は同49%に対して同13%だった。
働き方の多様化 がん患者も安心して働ける社会を
勤務先からの必要な支援としては、「がん治療に関する費用の助成」(36%)、「休職からの復帰にあたっての支援」(22%)など、経済的な支援を求める声が多い。
さらに「出社・退社時刻を自分の都合で変えられる仕組み」(37%)、「残業をなくす」(23%)、「1日単位の傷病休暇の仕組み」(23%)、など、治療の状況に応じた柔軟な勤務を求める声が多い。
がん罹患後の仕事に対する患者の考え方では、「短い労働時間でも高い成果を出すように心がけている」(79%)、「仕事で必要とされている」(78%)が多かった。この項目では「がんのことで上司や同僚から気を遣われたくない」(69%)を回答する患者も多かった。
がん患者は増加しており、早期発見により「治る病気」になりつつあり、5年相対生存率も上昇している。今回の調査では、がん患者の約3人に1人は就業可能な年齢で罹患している。働き方の多様化が進み、がん患者も安心して働くことができる企業が増えることが望まれる。
三菱UFJリサーチ&コンサルティング
関連する法律・制度を確認
>>保健指導アトラス【がん対策基本法】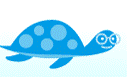 >>保健指導アトラス【医療・社会保障】
>>保健指導アトラス【医療・社会保障】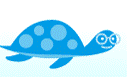 >>保健指導アトラス【労働基準法】
>>保健指導アトラス【労働基準法】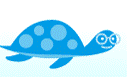
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.


「産業保健」に関するニュース
- 2025年08月21日
- 令和7年(1月~7月)の自殺者は11,143人 前年同期比で約10%減少(厚生労働省)
- 2025年08月21日
- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告
- 2025年08月20日
- 育休を「取りたい」若者は7割超 仕事と育児との両立で不安も 共に育てる社会の実現を目指す(厚生労働省)
- 2025年08月13日
-
小規模事業場と地域を支える保健師の役割―地域と職域のはざまをつなぐ支援活動の最前線―
【日本看護協会「産業保健に関わる保健師等の活動実態調査」】〈後編〉 - 2025年08月07日
- 世代別・性別ごとの「総患者数」を比較-「令和5年(2023)の患者調査」の結果より(日本生活習慣病予防協会)
- 2025年08月06日
-
産業保健師の実態と課題が明らかに―メンタルヘルス対応の最前線で奮闘も、非正規・単独配置など構造的課題も―
【日本看護協会「産業保健に関わる保健師等の活動実態調査」】〈前編〉 - 2025年08月05日
-
【インタビュー】2週間のデトックスで生産性が変わる?
大塚製薬の『アルコールチャレンジ』に学ぶ健康経営 - 2025年07月28日
- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善
- 2025年07月28日
- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減
- 2025年07月28日
- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由



















