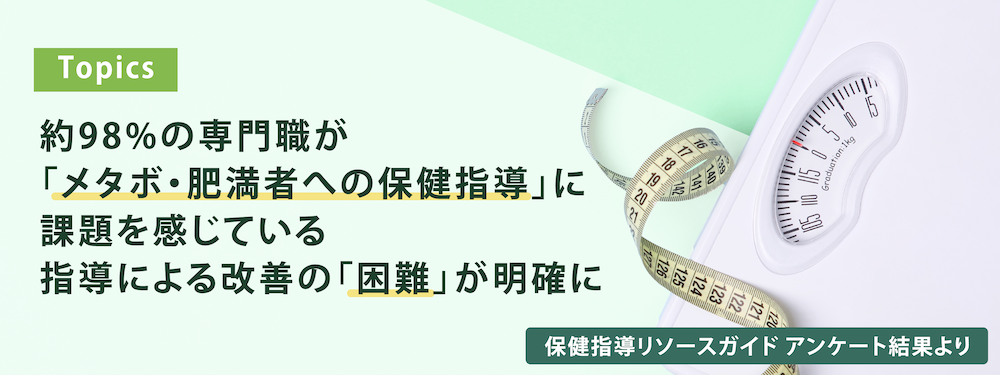ニュース
厚労省が配食事業の栄養管理に関するガイドラインを踏まえた参考事例集を公表
2019年02月26日
高齢化が進む中、自宅で暮らす高齢者が適切な栄養を取って健康に過ごせるよう、良質な配食事業のニーズが高まっている。
国は2017年3月、配食事業者向けの「地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理に関するガイドライン」(以下、ガイドライン)を公表。地域高齢者の健康支援を目的に、配食事業の栄養管理の在り方について整理したのは国として初めてのことだった。以来、ガイドラインの内容について普及・啓発が行われてきたが、さらなる啓発を図ろうと、このほど厚生労働省は取り組みの参考事例集をまとめ、公表した。
国は2017年3月、配食事業者向けの「地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理に関するガイドライン」(以下、ガイドライン)を公表。地域高齢者の健康支援を目的に、配食事業の栄養管理の在り方について整理したのは国として初めてのことだった。以来、ガイドラインの内容について普及・啓発が行われてきたが、さらなる啓発を図ろうと、このほど厚生労働省は取り組みの参考事例集をまとめ、公表した。
 ガイドラインは地域高齢者などの健康支援を推進するため、配食事業において望まれる栄養管理について事業者向けに作られたもの。平成28年6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」でガイドラインを作成し、2017年度からその内容に即した配食の普及を図る、と示されていた。
地域高齢者とは自宅などで暮らす65歳以上の人で、医療施設や介護保険施設に入所して医師や管理栄養士などの栄養管理を受けている人は除く。ガイドラインは地域高齢者と同様に健康支援が望まれる65歳未満の人も対象としている。
ガイドラインでは配食事業における商品管理の在り方に加え、配食利用者の身体的状況などをどう把握するかについても確認項目や留意事項が整理されている。
ガイドラインは地域高齢者などの健康支援を推進するため、配食事業において望まれる栄養管理について事業者向けに作られたもの。平成28年6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」でガイドラインを作成し、2017年度からその内容に即した配食の普及を図る、と示されていた。
地域高齢者とは自宅などで暮らす65歳以上の人で、医療施設や介護保険施設に入所して医師や管理栄養士などの栄養管理を受けている人は除く。ガイドラインは地域高齢者と同様に健康支援が望まれる65歳未満の人も対象としている。
ガイドラインでは配食事業における商品管理の在り方に加え、配食利用者の身体的状況などをどう把握するかについても確認項目や留意事項が整理されている。
利用者自身が栄養状態について考えるきっかけに
このたび作成された事例集は、ガイドラインを参考とする「一般食」、「栄養素等調整食」、「物性等調整食」、「自治体」の取り組み例をそれぞれ紹介するもの。
このうち一般食では、東京都世田谷区の社会福祉法人ふきのとうの会による「老人給食協力会ふきのとう」の事例を取り上げている。同会ではオリジナルのアセスメントシート「配食サービス利用者調査書」を使って、利用者の家族構成や健康状態などを把握。それぞれの状況にあった適切なメニューを提案してきた。
一方、ガイドラインでは配食注文時の確認項目例などが示されており、その内容を参考に同会ではアセスメントシートに体重の項目を新たに追加。このことで、より詳細に利用者の健康状態が把握できるようになったという。
また、体重の減少が見られたときなどに低栄養について話すことができ、利用者自身が栄養状態について考えるきっかけにつながっている。
実用に応じた取り組みを推進
自治体の例では、新潟県長岡地域振興局健康福祉環境部(新潟県長岡保健所)が取り上げられた。ガイドラインでは地域高齢者等の食事の選択肢や利便性が拡大し、健康の保持増進につながるよう、さまざまな支援を所管する部門が十分な連携を図りながら、地域の実用に応じた取り組みを推進するよう示している。
このことから同健康福祉環境部では関係者間での情報共有や連携体制の強化などを目的に検討会を開催。
管内市町の健康増進・介護予防・障害者福祉の各部門担当者、社会福祉協議会や栄養士会など多職種の関係者が一堂に会し、配食サービスによる地域高齢者等の栄養や食生活支援ついて意見交換を行ったという。
事例は今後も、順次、追加されていく予定。厚生労働省では、事例集を積極的に活用することで適切な栄養管理に基づく配食事業の普及が進み、地域高齢者等の食事の選択肢と利便性の拡大、また健康の保持増進が図られるよう期待している。
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.


「栄養」に関するニュース
- 2025年02月25日
- ストレスは「脂肪肝」のリスクを高める 肥満やメタボとも関連 孤独や社会的孤立も高リスク
- 2025年02月25日
- 緑茶を飲むと脂肪肝リスクが軽減 緑茶が脂肪燃焼を高める? 茶カテキンは新型コロナの予防にも役立つ可能性が
- 2025年02月17日
- 働く中高年世代の全年齢でBMIが増加 日本でも肥満者は今後も増加 協会けんぽの815万人のデータを解析
- 2025年02月17日
- 肥満やメタボの人に「不規則な生活」はなぜNG? 概日リズムが乱れて食べすぎに 太陽光を浴びて体内時計をリセット
- 2025年02月12日
-
肥満・メタボの割合が高いのは「建設業」 業態で健康状態に大きな差が
健保連「業態別にみた健康状態の調査分析」より - 2025年02月10日
- 緑茶やコーヒーを飲む習慣は認知症リスクの低下と関連 朝にコーヒーを飲むと心血管疾患リスクも低下
- 2025年02月10日
- [高血圧・肥満・喫煙・糖尿病]は日本人の寿命を縮める要因 4つがあると健康寿命が10年短縮
- 2025年02月03日
- 良い睡眠は肥満や高血圧のリスクを減らす 日本人の睡眠は足りていない 3つの方法で改善
- 2025年01月23日
- 大腸がんが50歳未満の若い人でも増加 肥満のある人は大腸がんリスクが高い 予防に役立つ3つの食品とは?
- 2025年01月23日
- 高齢者の要介護化リスクを簡単な3つの体力テストで予測 体力を維持・向上するための保健指導や支援で活用