多量飲酒者はコロナ禍を経て増えた?従業員との関係性が保健指導のカギ ―職域でのアルコール健康障害対策および飲酒に関する保健指導の実態調査PR
提供 大塚製薬株式会社
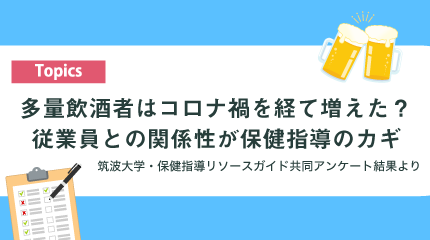
筑波大学と保健指導リソースガイドは「職域でのアルコール健康障害対策および飲酒に関する保健指導の実態調査」を共同実施し、403名の方からご回答をいただきました。
本調査では、特に現役世代と接することが多い、企業や健康保険組合に勤務する職域の保健指導専門職・医療従事者に、従業員や指導対象者の飲酒状況や指導の実態を詳細に伺いました。
「アルコール」「減酒」に関する職場教育や保健指導の実態、それらを推進するための要因や、そしてコロナ前後の多量飲酒者の傾向など、専門職ならではの視点から興味深い回答が集まりました。本記事では、この回答結果をご紹介します。
アンケート調査概要
- 回答期間:2024年7月31日~8月20日
- 回答対象者:保健指導専門職または医療従事者(特に職域で従事される方)
- 回答数:403名
回答者の属性
職種<n=403>
(複数回答)
資格取得後の経験年数<n=403>
平均:約16.6年(最大:52年 最小:1年)(単一回答)
勤務先<n=403>
勤務先は「企業」が最も多く(37.7%)、「健診機関」(9.4%)「病院」(6.9%)「市町村保健センター」(6.2%)と続き、「健康保険組合」は5.2%でした。(単一回答)
健康診断等を通じた「アルコール」「飲酒」のスクリーニング、指導状況
本アンケートでは、現役世代の「飲酒」状況を把握することを目的に実施しました。そのため、この世代と接する機会が多い、企業や健康保険組合に勤務する保健指導スタッフ・医療従事者に、ご自身の取組状況を詳細に伺いました。
所属企業の業種<n=173>
「製造業」が39.3%と最も多く、「卸売業、小売業」(9.8%)、「情報・通信業」「運輸業、郵便業」(ともに8.1%)、「建設業」(5.2%)と続きました。(単一回答)
定期健康診断の問診票で、習慣的な飲酒習慣がある者を確認していますか?<n=173>
- はい
- いいえ
(単一回答)
定期健康診断で肝機能異常、高血圧、脂質異常などアルコールに起因した異常がみられる者について、健康診断の問診票で習慣的な飲酒習慣があるかを確認していますか?<n=173>
- はい
- いいえ
(単一回答)
アルコール使用障害スクリーニングテスト(AUDIT:オーディット)を実施していますか?<n=173>
- はい
- いいえ
(単一回答)
「アルコール」に関する職場教育、指導の状況
企業や健康保険組合に勤務する保健指導スタッフ・医療従事者に、アルコールに関する職場教育や指導の実施状況を伺いました。
アルコールに関する職場教育は実施していますか?<n=173>
- はい
- いいえ
(単一回答)
(複数回答)
ご自身の業務の中で、減酒支援やアルコールに関する指導を実施したことがありますか?<n=173>
- はい
- いいえ
(単一回答)
(複数回答)
生活習慣の改善や減量、アルコールに起因する疾患の治療を目的とした保健指導・減酒支援が中心ですが、「飲酒ガイドライン」でも取り上げられた「酒類の純アルコール量の表示を使用した減酒指導」や、昨今数多くの製品が販売されている「『微アルコール飲料』『ノンアルコール飲料』の推奨」も半数近くの方が業務内に取り入れていることがわかりました。
本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。

