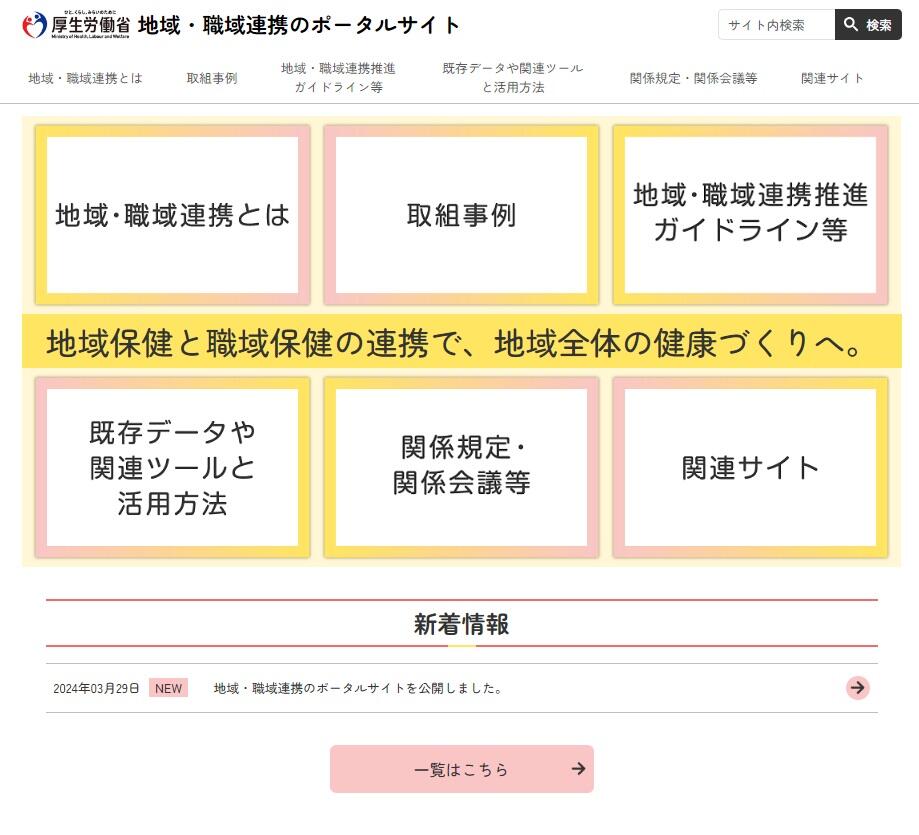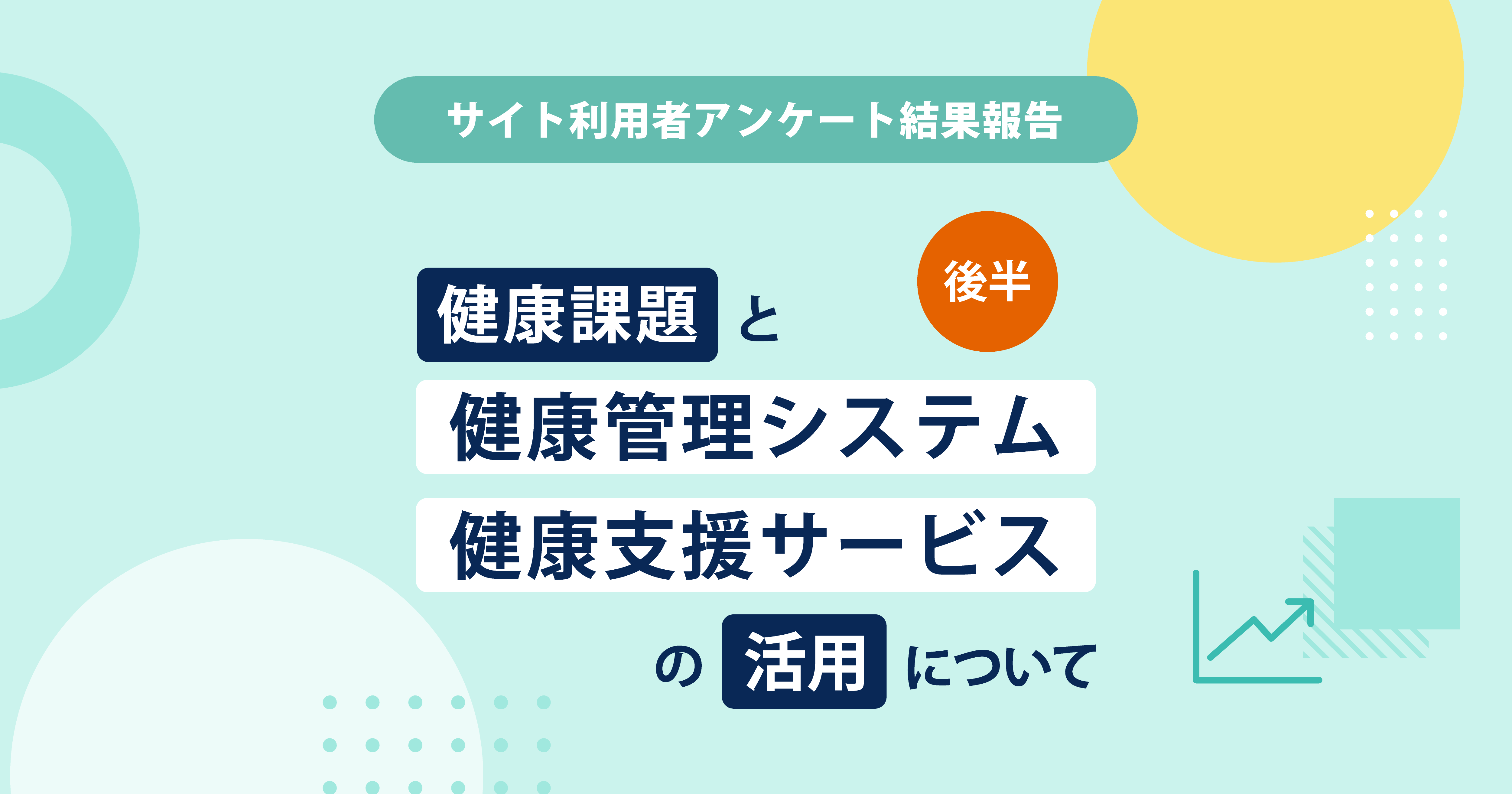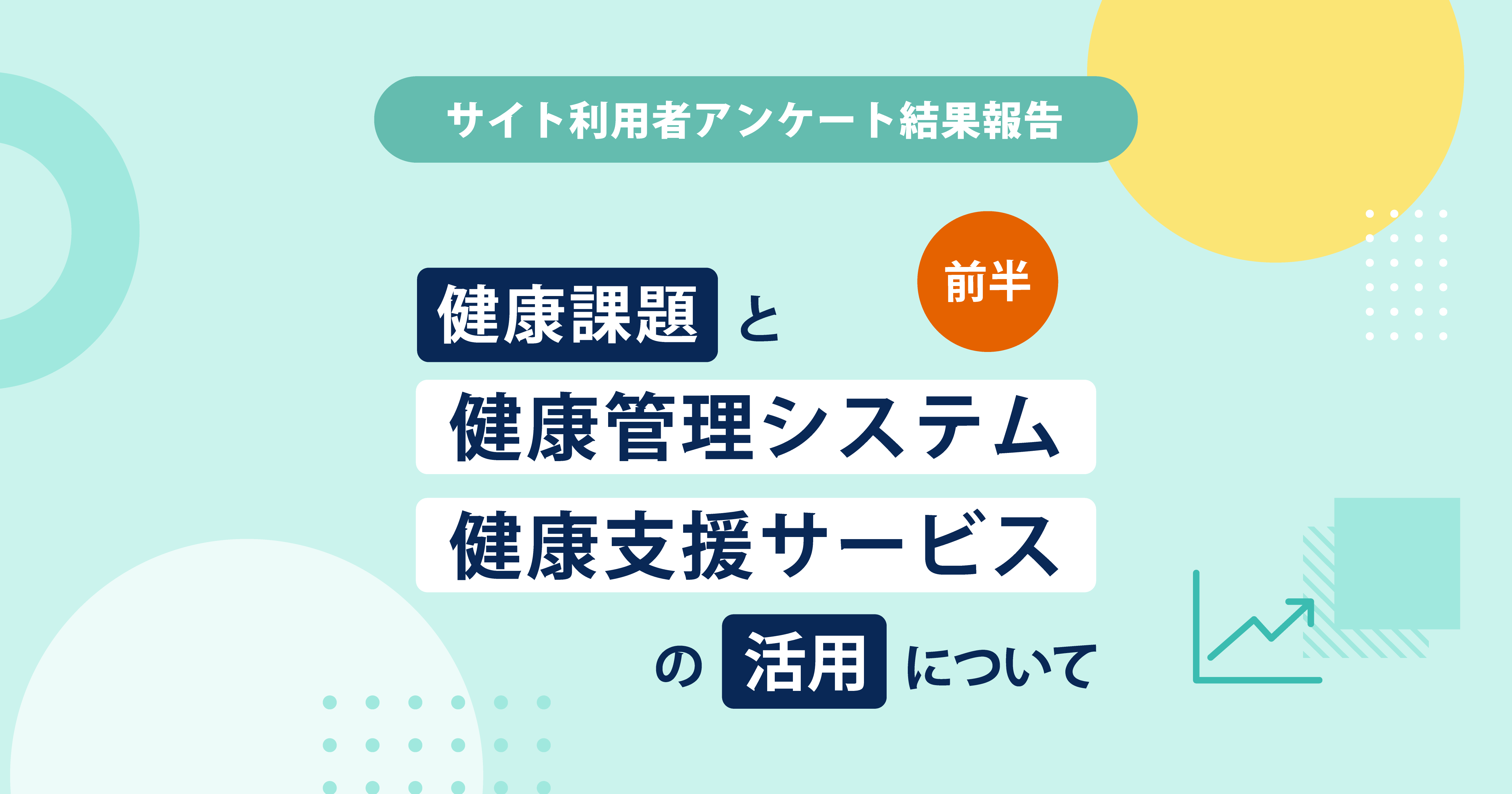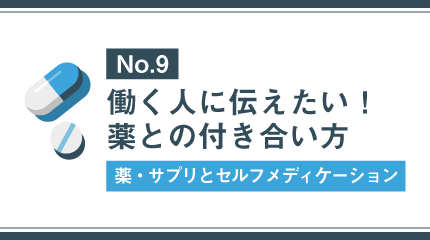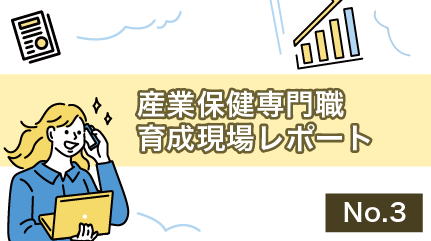オピニオン/保健指導あれこれ
もっとよく知ろう健診機関
No.1 後悔しない健診機関の選び方
HSプランニング 代表、保健師
2012年12月19日
2.健康管理を進める立場から
∼どのように健康管理をデザインするか∼
●健診委託の範囲∼どのように健康管理をデザインするか∼
健診実施機関には、ただ法定の健康診断だけを実施してもらえれば良いのか、それとも集団全体の健康管理を進める上での正確なデータが効率良く活用できるところまでを依頼するのか、あるいは保健指導までをも依頼するのか。つまり、一口に健診委託と言っても具体的にどこまでを委託したいのかを考えることが大切です。 社員や住民全体の健康課題を抽出し、保健指導の優先順位を決定したり、新たな保健事業を進めたりする場合、データの取りまとめや分析などが必要になります。こうしたことまで健診実施機関が対応可能か、それとも別のデータとりまとめ機関との契約をするのか、あるいはそれらを全て自分たちで行うのか―。健診機関決定後に追加の委託をしたくても予算が取れない、そもそも健診機関が対応不可能など、後から困ることがないように計画しましょう。 ●健診機関の質・健診データの精度管理の問題
そもそも、委託しようとしている健診実施機関は正確な健康診断をしてくれるところなのか―この判断は難しいところもありますが、健康診断の意味や法律を知らない機関(まだまだ存在するのです!)から、測定項目が抜けていたり、データそのものがあり得ない数値を示している結果表が返ってきたりすることもあります。さらには、受診した社員から「検査・測定方法が正確でない」と報告を受けたという例さえあります。 その機関はきちんとした研修教育を実施しているのか、情報収集をしっかりしているのか、などを確認すると良いでしょう。学会や専門機関等の認証を受けていること、あるいはホームページなどで精度管理についての情報があることなどが目安となります。 ●おわりに
そうは言っても、地方により健診機関が少なく選べない、何らかの事情があり最初から委託先は決まっているなど、現状では健診機関の選択肢がない場合もあります。ただ、そうした現状の中でも、健康管理の何を大切にしていくのかを考え、優先事項を決め、場合によっては委託先とじっくり話し合うことで、双方にとってより良い健康診断の仕組みが検討できるかもしれません。また、健診機関の営業担当者の中には、健康管理スタッフや健診事務担当者と一緒に、より良い健診をデザインしたいと考えている方もいます。入札や委託の前に、公平な立場で健診全般について詳しく知っている方と情報交換するのも良いでしょう。 大切な社員や住民の健康診断を健診機関に「丸投げ」せず、健診機関を有効に活用することが望まれます。
「もっとよく知ろう健診機関」もくじ
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2024 SOSHINSHA All Rights Reserved.
「健診・検診」に関するニュース
- 2024年04月25日
- 厚労省「地域・職域連携ポータルサイト」を開設 人生100年時代を迎え、保健事業の継続性は不可欠
- 2024年04月22日
- 【肺がん】進行した人は「健診やがん検診を受けていれば良かった」と後悔 早期発見できた人は生存率が高い
- 2024年04月18日
- 人口10万人あたりの「常勤保健師の配置状況」最多は島根県 「令和4年度地域保健・健康増進事業の報告」より
- 2024年04月18日
- 健康診査の受診者数が回復 前年比で約4,200人増加 「地域保健・健康増進事業の報告」より
- 2024年04月09日
- 子宮の日 もっと知ってほしい子宮頸がんワクチンのこと 予防啓発キャンペーンを展開