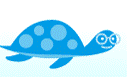千葉県は、がん患者の治療と仕事の両立を支援するために作成した「がん患者の就労支援に関する情報提供書」の公開をホームページで始めた。「がんと診断されたからといってすぐに退職を決めるのではなく、主治医とよく相談しながらご自身の治療計画に合わせて、就業計画を立てることが大切」と説明している。
がんは「長くつきあう慢性病」
働きながら治療できる環境を整備
現代の日本では、がんは必ずしも「命にかかわる病気」ではない。最新のデータを見ると、治療の目安とされる5年生存率は全がん平均で約7割に達し、中には甲状腺がん、精巣がん、乳がんのように8?9割を超える種類のがんもある。がんは、いまや「死に直結する病気」ではなく「長くつきあう慢性病」に変化している。
一方、日本では定年年齢の延長や再雇用の義務化、生産年齢人口の減少など、就労環境に変化が起きており、がんを発症する労働者は今後も増えていく。多くの労働力を「がんになったから」というだけで活用しないことは、社会全体にとって大きな損失となる。
2012年度から始まった国の政策である、第2期がん対策推進基本計画には、重点課題として、働くがん患者への支援が盛り込まれた。この基本計画の中には、「事業者は、がん患者が働きながら治療や療養できる環境の整備、さらに家族がんになった場合でも働き続けられるような配慮に努めることが望ましい。また、職場や採用選考時に、がん患者・経験者が差別を受けることのないよう十分に留意する必要がある」と明記されている。
千葉県がん患者に特化した情報提供書を公開
そこで千葉県は、がん患者の治療と仕事の両立を支援するために作成した「がん患者の就労支援に関する情報提供書」の公開をホームページで始めた。患者の雇用者と主治医らの間の情報交換を促進させて不要な離職を減少させるのが目的で、がん患者に特化した情報提供書を公開するこうした取り組みは、他都道府県や国を含めて全国ではじめてとみられる。
ホームページでは「がんと診断されたからといってすぐに退職を決めるのではなく、主治医とよく相談しながらご自身の治療計画に合わせて、就業計画を立てることが大切です。会社の就業規則を確認し、産業医や人事・給与・福利担当者と相談しましょう」と紹介されている。
県の調査によると、2011年度に県内で新たにがんに罹患した人は2万9,895人で、このうち65歳未満は3割を占める。国の調査では、罹患者の3人に1人が20?64歳で、肺がんや前立腺がんは55歳以上で発症し、女性では乳がんは30歳以上で、子宮頸がんは25歳以上で発症している。
こういった現状をふまえ、県は2013年3月に「県がん対策推進計画」を策定して就労支援部会を設置。県が実施した「がん患者の就労に関する実態調査」では、「病気や治療に関する見通しが分からない」「復職後の適正配置の判断が難しい」「代替要員の確保が難しい」といった声が多く寄せられた。
がん患者の就労支援について事業者や患者に理解してもらいたい
千葉県が進めているがん患者の就労支援では、事業者(産業医)から主治医へ従業員の業務内容などの勤務状況を伝えるための「復職・就労継続支援に関する情報提供依頼書」を記載する。患者の通勤形態や業務内容に加え、勤務時間の減少や配置転換といった対応可能な配慮などを記入する。
これを受けた主治医から事業者へ診断・治療の状況や就労継続についての意見を伝える「復職・就労継続支援に関する診断書」を提出。治療の状況や今後の見通しなどを書き、事業者側の可能な配慮をふまえて、患者が就労を継続することについての意見などを述べる。
情報提供依頼書については、患者本人の了解のもとに情報共有していることが確認できるよう、また、患者の知らないところでのやり取りにならないよう、患者の同意欄が様式内に設けられた。
県健康づくり支援課は「部会では、患者側からの『働けるのに働けない』と悩む声も集まっていた。情報提供書を周知し、多くの事業者や患者に就労支援について理解してもらいたい」と述べている。
がん患者の就労支援について(千葉県 2016年3月30日)
千葉県がん情報 「ちばがんなび」
がんと仕事のQ&A『がん就労者』支援マニュアル(働くがん患者と家族に 向けた包括的支援システムの構築に関する研究班)
関連する法律・制度を確認
>>
保健指導アトラス【がん対策基本法】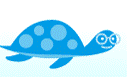
>>
保健指導アトラス【労働基準法】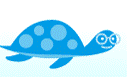

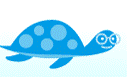 >>保健指導アトラス【労働基準法】
>>保健指導アトラス【労働基準法】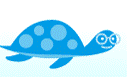

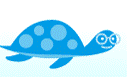 >>保健指導アトラス【労働基準法】
>>保健指導アトラス【労働基準法】