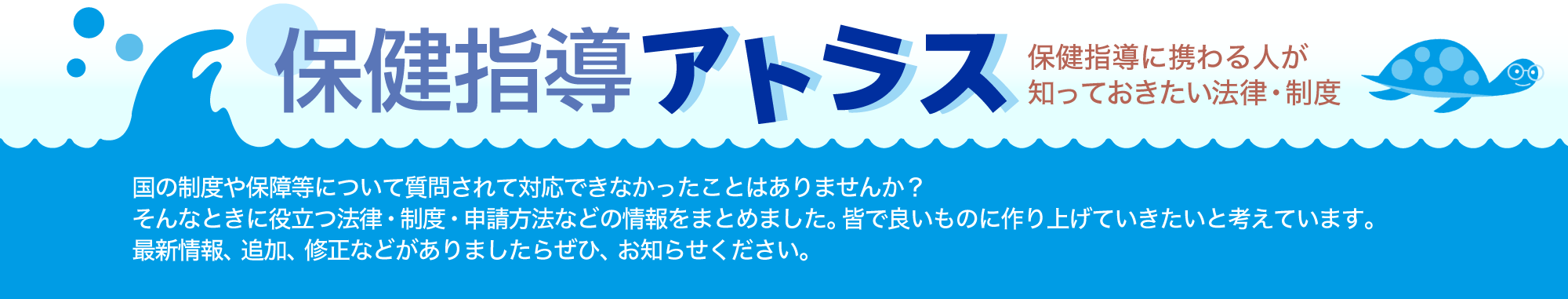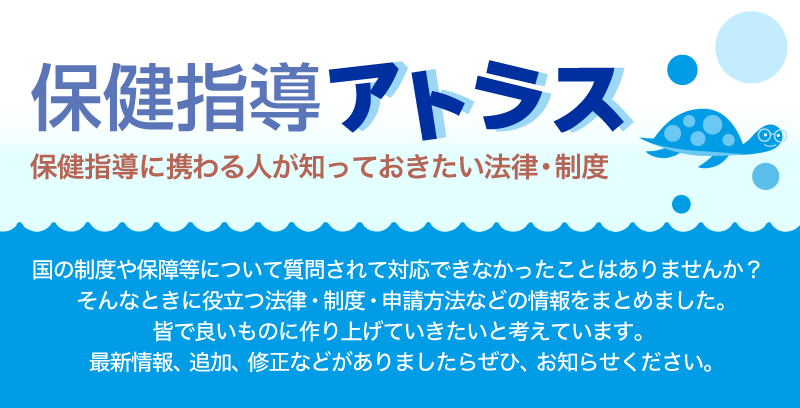母子保健
母子保健法公布:昭和四十年 最終改正:令和六年 施行日:令和六年九月十九日)
目 的
母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、国民保健の向上に寄与することが目的。
概 要
・新生児の訪問指導・乳幼児健康診査 母子保健法第12条及び第13条の規定により 市町村が乳幼児に対して行う健康診査。健診費用は健診費用が国や自治体負担となるため無料。
乳幼児健診の目的は「乳幼児の病気の予防と早期発見、および健康の保持・健康の増進」。 ※受けられる健診をはじめとしたサービスは、住んでいる市町村により異なるため、詳細は各住居地に確認する必要がある。
関 連
・「健やか親子21」※令和5年現在は第2次 (平成13年開始) 母子の健康水準を向上させるための様々な取組を推進する国民運動計画。 安心して子どもを産み、健やかに育てることの基礎となる少子化対策としての意義に加え、少子化社会において、国民が健康で明るく元気に生活できる社会の実現を図るための国民の健康づくり運動(健康日本21)の一翼を担うもので、平成27 年度から新たな計画(~平成36 年度)が始まる。 具体策は、切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策、学童期・思春期から成人期に向けた保健対策、子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり。 育てにくさを感じる親に寄り添う支援、妊娠期からの児童虐待防止対策を進める。 ■HP「健やか親子21(第2次)」(こども家庭庁)参考
■子ども・子育て支援新制度-「子ども・子育て支援新制度について」令和元年6月(内閣府) ・平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連3法に基づく制度。平成27年度本格施行。市町村が実施主体となり、地域の実情に応じた子育て支援拠点や放課後児童クラブなどの地域こども・子育て支援事業を実施など。
■育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律) (公布:平成三年 最終改正:令和六年 施行日:令和七年一〇月一日) ※育児・介護休業法の詳細は、「産業保健」のページに掲載しています。
こども基本法公布:令和四年 最終改正:令和六年 施行日:令和六年九月二五日
総則
日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。
関 連
・こども家庭庁設置法 (公布:令和四年 最終改正:新規制定 施行日:令和五年四月一日)情報源へリンク こども家庭庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
参考
■児童の権利に関する条約(1998年10月)
■いじめ防止対策に関するこども家庭庁の所掌事務、基本方針の記載 「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針(令和3年12月21日閣議決定)(抜粋)」 ・いじめに関し、こども家庭庁は、学校外でのいじめを含めたこどものいじめの防止を担い、関係機関や関係者からの情報収集を通じた事案の把握、いじめの防止に向けた地方自治体における具体的な取組や体制づくり等を推進する。また、重大ないじめ事案への対応について、必要な情報を文部科学省と共有するとともに、地方自治体での共有を促進し、学校の設置者等が行う調査における第三者性の確保や運用等についての改善などの必要な対策を文部科学省とともに講ずる。
児童福祉法公布:昭和二十二年 最終改正:令和六年 施行:令和八年四月一日
総則
国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、育成されるよう努めなければならない。 児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。概要
・児童相談所の設置、療育の指導 ・小児慢性特定疾病医療費の支給、療育の給付(医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給) ・障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 ・肢体不自由児通所医療費の支給 ・子育て支援事業、助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等 ・障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 ・要保護児童の保護措置等 【補足】 1997年(平成9)の第五〇次改正では、制定後50年の経過による環境の変化に対応するとともに、締約国に条約の実効に関する報告が義務づけられている「子どもの権利条約」批准後の大幅な改正があった。児童虐待の防止等に関する法律公布:平成十二年 最終改正:令和四年 施行:令和七年六月一日
児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、児童の権利利益の擁護に資することが目的。