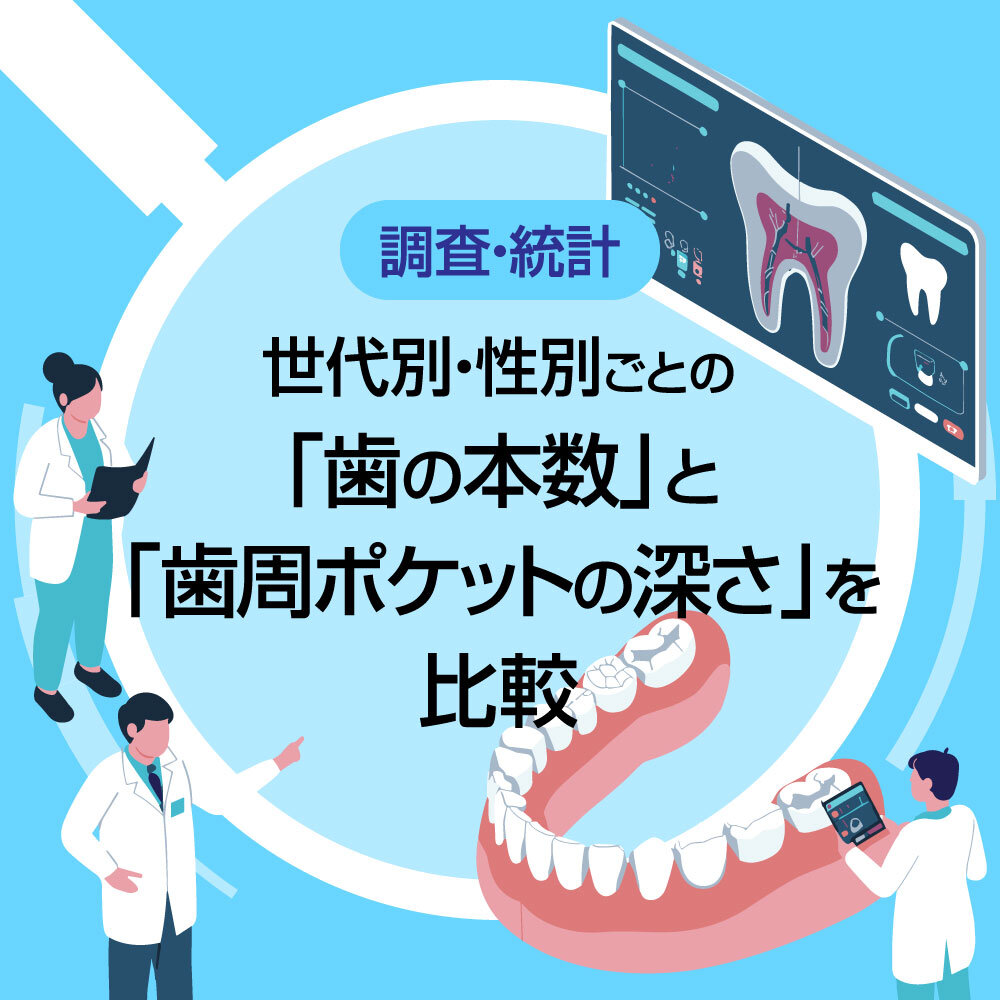ニュース
議論の整理案を提示 ~子どもの医療制度の在り方等に関する検討会
2016年03月10日
厚生労働省の「子どもの医療制度の在り方等に関する検討会」第4回会合がこのほど開かれ「これまでの議論の整理」(案)などを提示。子どもの医療費助成を行う市町村に対して実施されている国保の国庫負担金減額調整を廃止するかどうか、といった点などについて議論が深められた。
同検討会は受診状況や提供体制など「子どもの医療に関する現状」をふまえながら、子どもの医療のかかり方や医療提供体制、医療の自己負担の在り方、国保の国庫負担の在り方などを審議するために設置されている。
今回の会合で提示された「議論の整理」(案)は「子どもの医療のかかり方」、「子どもの医療の提供体制」、「子どもの医療に関わる制度」の3項目に分けてこれまでの意見を集約したもの。
医療保険各法における自己負担割合(70歳未満)は原則3割だが、義務教育就学前は2割と軽減されている。一方ですべての自治体では、乳幼児を中心に子どもを対象とした医療費助成制度を独自に設定。対象年齢や一部負担の有無などで制度の違いがみられ、子どもの医療費減免を子育て世帯の人口減少対策につなげている自治体も多い。
このような子どもの医療費負担減免に関する地方単独事業について、「議論の整理」(案)では「自治体間で拡大競争がなされている」との指摘に伴い「国として一定の線を引くべきできではないか」、「せめて未就学児については全国一律の制度としてどこに住んでいても同じであるべき」といった意見が列記されている。
また一部自治体で行われている医療費無償化については「過剰診断などモラルハザードを生じうる」可能性があるとして、一部負担を徴収したり償還払いにしたりすべきだと指摘。一方で無償になっても、院内で感染症に罹患するリスクを考えれば安易な受診を控える保護者が多い、といった意見や、過剰受診にならないよう保護者を啓発・教育すればある程度は防げるのではないか、という声も紹介している。
一般的には医療保険制度の給付率が低くなり、患者負担が増加すると受診日数が減少するため医療費の伸びが抑えられることが知られている。このような制度的な給付率の変更に伴い、医療費の水準が変化することを「長瀬効果」と呼んでいる。
そのため地方単独事業で小児に対する医療費助成が行われていると、一般的に医療費は増加。この波及増分は広く国民全体で補うのではなく、制度を実施している地方自治体の負担とすべき、という観点から、子どもの医療給付費には自己負担の割合に応じた調整率で国庫負担額を算出し、減額調整を行っている。
たとえば未就学児で通常2割の自己負担額を1割にした場合は0.9349、無償化にしている場合は0.8611という調整率が給付費に乗じられ、平成25年度の未就学児に対する減額調整額は1,395市町村で約79億円であった。
このような制度の仕組みは、限られた財源を公平に配分するためには「適切である」という意見がある一方、地方自治体が行っている子どもの医療費助成は本来、国がやるべき少子化対策の一環であり、減額調整措置の廃止を求める声もある。
そのため「議論の整理」(案)でも、「国として推し進める少子化対策に逆行」や「地方の取り組みに二重の負担を強いている」といった指摘に加え、「財政力の有無に関わらず全国的に子どもの医療費助成が行われていることから、減額調整措置を廃止すべき」といった意見を列記。一方で、国が進めている財政再建計画全体と整合性を図りながら減額調整措置の在り方について考えていく必要がある、ともしている。
ほかにも会合では、子どもの医療費助成を償還払いで実施している8県と現物給付都道府県との受診率の比較や、高校卒業まで無償化にした場合の医療保険の給付費は最大で8400億円の増加になる、との試算結果などもふまえ、さまざまな議論を行った。同検討会ではさらに議論を深め、今春の取りまとめを目指していく方針。
第4回子どもの医療制度の在り方等に関する検討会
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.


「地域保健」に関するニュース
- 2025年08月21日
- 令和7年(1月~7月)の自殺者は11,143人 前年同期比で約10%減少(厚生労働省)
- 2025年08月21日
- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告
- 2025年08月13日
-
小規模事業場と地域を支える保健師の役割―地域と職域のはざまをつなぐ支援活動の最前線―
【日本看護協会「産業保健に関わる保健師等の活動実態調査」】〈後編〉 - 2025年08月07日
- 世代別・性別ごとの「総患者数」を比較-「令和5年(2023)の患者調査」の結果より(日本生活習慣病予防協会)
- 2025年08月06日
-
産業保健師の実態と課題が明らかに―メンタルヘルス対応の最前線で奮闘も、非正規・単独配置など構造的課題も―
【日本看護協会「産業保健に関わる保健師等の活動実態調査」】〈前編〉 - 2025年07月28日
- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善
- 2025年07月28日
- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減
- 2025年07月28日
- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由
- 2025年07月28日
- 【妊産婦を支援】妊娠時に頼れる人の数が産後うつを軽減 妊婦を支える社会環境とメンタルヘルスを調査
- 2025年07月22日
- 【大人の食育】企業や食品事業者などの取り組み事例を紹介 官民の連携・協働も必要 大人の食育プラットフォームを立ち上げ