ニュース
「非空腹時の中性脂肪は175が上限」欧州の新基準 糖尿病でより重要
2017年04月24日
糖尿病があると高くなりやすい中性脂肪。その中性脂肪は血糖と同様に、食事をとると高くなり空腹時は低下する。中性脂肪を含む血清脂質の検査は現在、国内では空腹時に採血するが、欧州では最近、非空腹時の採血が推奨されるようになった。
血液検査の採血は、空腹時、それとも非空腹時?
健康診断などで血液検査を受ける前には絶食を指示され、採血前の10時間ほどは食事や水・お茶以外の水分をとることができない。この主な理由は2点あり、一つ目は代謝性疾患(糖尿病や脂質異常症など)の発見・診断に用いられる血糖や中性脂肪の検査値は食事の負荷によって変動するため、空腹時採血でないと結果判定が困難になること、そして二つ目は空腹時以外(非空腹時、随時)に採血した場合の診断基準値がないことだ。
しかし既に血糖に関しては、糖尿病合併症の中でも特に生命にかかわるような動脈硬化性疾患のリスクとの相関がより強いのは、空腹時ではなく食後の血糖値であることが明らかになっている。また近年の研究で中性脂肪に関しても同様のことが示唆されつつあり、この点は、糖尿病患者ではインスリン作用不足の影響などで中性脂肪が高くなりやすいことからも注目される。
さらに、そもそも生活習慣病の増加が問題となっている現在のような社会環境においては、ほとんどの人が一日の大半、非空腹の状態にあり、空腹はむしろ特殊な状況だとも言える。
絶食による空腹時採血を前提とした検査には上記の他にもいくつかの弱点が考慮されており、海外の医学会からは空腹時ではなく「非空腹時の脂質検査値の使用を推奨する」との声明も発表されている。
空腹時値が非空腹時値よりリスク評価に優れている、というエビデンスは存在しない
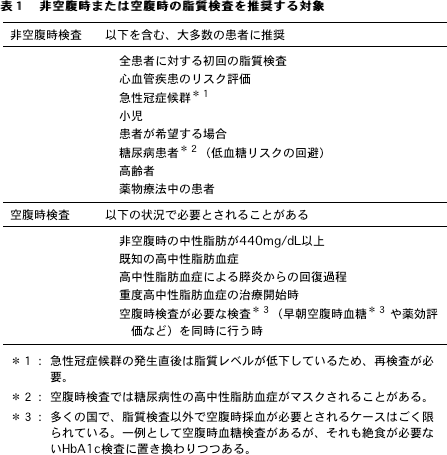 | |
異常と判定する中性脂肪値、空腹時は150mg/dL以上、非空腹時は175mg/dL以上
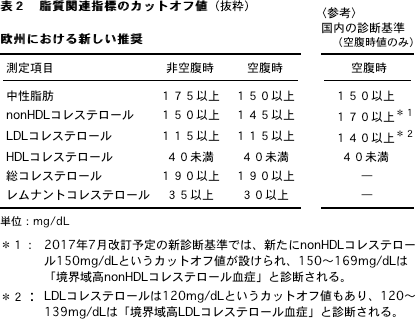 | |
非空腹時の脂質検査が必要とされるケースもある
一方、従来からの空腹時検査にもメリットがある。例えば、遺伝子変異による脂質異常症や非空腹時値が極めて高値の場合、あるいは脂質異常症として治療を始める前など、脂質レベルを正確に判定する必要があるケース、または膵炎の治療経過をみる際などだ。
本論文では非空腹時と空腹時の検査はそれぞれ補完的なものであり、互いに相いれないものではないとまとめると同時に、世界各地で非空腹時採血による脂質検査が日常的検査として採用されること、そしてこの声明が各国の公的機関に認識され脂質検査の標準となることが理想だと述べている。
関連ページ: Fasting is not routinely required for determination of a lipid profile: clinical and laboratory implications including flagging at desirable concentration cut-points?a joint consensus statement from the European Atherosclerosis Society and European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
〔Eur Heart J 37 (25):1944-1958, 2016〕
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.


「健診・検診」に関するニュース
- 2025年08月21日
- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告
- 2025年07月07日
- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市
- 2025年06月27日
-
2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%
過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日
-
【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ
対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日
- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】
- 2025年05月20日
-
【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築
―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日
- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善
- 2025年05月16日
- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少
- 2025年05月12日
- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要
- 2025年05月01日
- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】



















