敗血症性AKIにおける急性腎障害マーカー L-FABPの可能性
第45回 日本集中治療医学会 学術集会 教育セミナー23より
敗血症は急性腎障害(AKI)を併発することが多く、AKIを発症すると予後はさらに深刻となる。予後改善に向けより早期からの介入が必要だが、AKI診断のクライテリアである血清クレアチニン上昇や尿量低下は腎障害の結果として生ずる変化であるため、それだけでは介入の遅れを免れない。これに対し、新たなバイオマーカーが早期診断の一助となる可能性が示されつつある。
その最前線の研究から見えてきた敗血症性AKIの新たなパラダイムを、湘南鎌倉総合病院集中治療部医長の小室哲也先生に講演いただいた。

演者:小室 哲也 先生(医療法人沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院 麻酔科・集中治療部。現在:自治医科大学附属さいたま医療センター 集中治療部)

司会:野入 英世 先生(東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科)
Prologue AKIの見つけ方
東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科 野入 英世 先生
本講演では湘南鎌倉総合病院の小室先生をお迎えし敗血症性AKIの診断と治療について講演いただくが、その前に私からプロローグとして「AKI の見つけ方」を少しお話ししたい。
AKIを早期診断できていない
図1は、AKIが発生しGFRが90mL/分/1.73m2から10mL/分/1.73m2へ一気 に低下した際、血清クレアチニンがどのように変化するかをシミュレーションしたものだ。24時間経過した時点で血清クレアチニンは2mg/dL、48時間で4、それぞれの時点のeGFRは38、18mL/分/1.73m2となる。そして7日後にようやく血清クレアチニン7、eGFR 10に至る。本来は直ちにGFRが10に落ちたことがわからなければいけないにもかかわらず、これだけのタイムラグがあるということだ。血清クレアチニンは腎機能評価のゴールドスタンダードではあるが、それだけでは介入のタイミングを失しかねない。
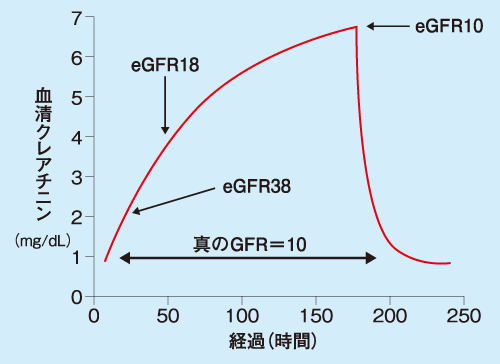
早期診断はICUではノイズにもなり得る
この問題に対応し、これまでにL-FABP(liver-type fatty acid-binding protein)やNGAL(neutrophil gelatinase-associated lipocalin)などさまざまなバイオマーカーが開発されてきた。しかし、ERにおける各種バイオマーカーのAKI診断能を比較した報告などから、いずれのマーカーも陰性的中率が非常に高い反面、陽性的中率がやや低いことが知られている1)。もちろん、バイオマーカーでAKIを否定できるということは、ERでは一つの利点となるだろう。しかしICUでは何らかの手段で陽性的中率も高めなければ治療に結び付けづらい。つまり、高い感度を保ちながらも、介入せずとも回復していくようなノイズを入り込ませない重症度判定が理想とされる。具体的には、ICUにおいてKDIGOのステージ1ではノイズが多く介入すべきポイントはさほど多くないことから、KDIGOステージ2以上が抽出すべき対象ではなかろうか。
RAIを用いてpersistent AKIを診断
こうした中、AKIが3日以上続き積極的な介入が必要となる可能性が高いと予測されるAKIの新たな定義として'persistent AKI'という概念が打ち出され、徐々に定着してきている2)。そのpersistent AKIの抽出法として、血清クレアチニンやGFRの変動幅に種々の患者背景をスコア化し乗算して算出する'Renal Angina Index('RAI)という指標が既に存在し、さらに的中率を高めるべく改良した計算式も複数提唱されている。我々もRAIの計算式にL-FABPを上乗せすることで、persistent AKIの診断能が有意に上昇することを報告している(図2)。このような手法によりpersistent AKIを早期に効率的に見出すことで、今後AKIの予後改善に向けた検討が可能になっていくだろう。
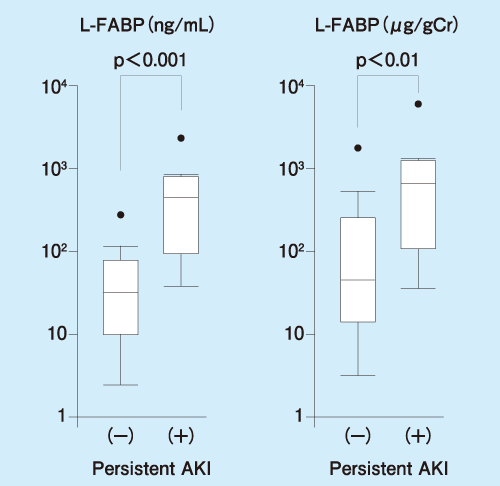


「健診・検診」に関するニュース
- 2025年06月02日
- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】
- 2025年05月20日
-
【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築
―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日
- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善
- 2025年05月16日
- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少
- 2025年05月12日
- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要
- 2025年05月01日
- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】
- 2025年05月01日
- 【デジタル技術を活用した血圧管理】産業保健・地域保健・健診の保健指導などでの活用を期待 日本高血圧学会
- 2025年04月17日
- 【検討会報告】保健師の未来像を2類型で提示―厚労省、2040年の地域保健を見据え議論
- 2025年04月14日
- 女性の健康のための検査・検診 日本の女性は知識不足 半数超の女性が「学校教育は不十分」と実感 「子宮の日」に調査
- 2025年03月03日
- ウォーキングなどの運動で肥満や高血圧など19種類の慢性疾患のリスクを減少 わずか5分の運動で認知症も予防



















