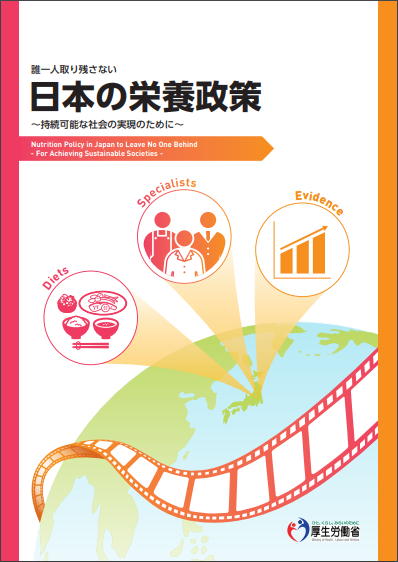厚生労働省は、12月に東京で開催する「栄養サミット2020」の詳細を公表した。日本政府が主催し、世界保健機関(WHO)、FAO(国連食糧農業機関)、国連世界食糧計画(WFP)、国際連合児童基金(UNICEF)、世界銀行などと共催し、各国の首脳、閣僚の出席が予定されている。
オリンピック・パラリンピックに合わせて開催
「栄養サミット」は、オリンピック・パラリンピックの機会を利用し、栄養改善に向けた国際的機運を高めるために開催される。
「栄養サミット」は、英国のシャルルボアで開催されたG7サミット(先進7ヵ国蔵相・中央銀行総裁会議)で決定され、2012年のロンドン・オリンピックの機会にはじめて開催された。2016年のリオデジャネイロ・オリンピックに合わせて2回目が開催され、ブラジル保健大臣、WHO(世界保健機関)事務局長、FAO(国連食糧農業機関)事務局長などが出席した。
この流れは、2020年の東京オリンピックにも引き継がれる。2020年は国際的な栄養目標の中間評価を行う重要な年であり、2012年に示された世界栄養目標の最終年にあたる。
世界栄養目標で示されているのは、主に次のことだ。
・ 少なくとも5億人の妊婦および2歳未満の子どもに効果的な栄養の介入がなされていることを確実にする。
・ 5歳未満の発育阻害の症状にある子どもの数を少なくとも2,000万人減らす。
・ 発育阻害を予防し、母乳育児を増やし、重度急性栄養不良の治療を増やすことによって、170万人の5歳未満の子どもの命を救う。
「栄養不良の二重負荷」が重要なテーマに
「東京栄養サミット2020」でははじめて、「栄養不良の二重負荷」への対策も打ち出される。日本を含むすべての国は何らかの栄養課題を抱え、この問題に直面している。
「栄養不良の二重負荷」とは、低栄養と過栄養が個人内・世帯内・集団内で同時にみられたり、一生涯の中で低栄養と過栄養の時期がそれぞれあるなど、低栄養と過栄養が併存する状態のこと。持続可能な社会の発展を阻害する地球規模の課題となっている。
減少していた世界の飢餓人口は2014年から増加に転じ、世界の9人に1人が飢餓に直面している。世界の5歳未満死亡率は出生1,000件中39件まで低下したが、依然として適切な栄養や完全母乳栄養育児などの介入が必要とされている。
一方、過体重や肥満も増加している。飢餓や栄養欠乏だけでなく、過体重や肥満などの栄養不良の解消もターゲットに含まれる。
がん・糖尿病・循環器疾患に対策
WHOが打ち出した、がん・糖尿病・循環器疾患・呼吸器疾患などの非感染性疾患(NCDs)への対策も重要な課題だ。これらの疾患は、不健康な食事や運動不足、喫煙、過度の飲酒などの原因が共通しており、生活習慣の改善により予防・改善が可能だ。
具体的には、▼食塩摂取量を30%減少する、▼高血圧を25%減少する、▼糖尿病と肥満の増加を阻止する――といった目標が掲げられている。
これらの議題について、首脳級・閣僚級の出席によるセッションにより、栄養課題の解決に向けたコミットメントの表明を目指す。
災害時に備えた栄養・食生活支援も
「東京栄養サミット2020」では、日本の栄養に対する取組みもパッケージとして発信する。日本の栄養政策での取組みの方向性を「見える化」し、栄養に関する国際貢献につなげていくことを目標とする。
(1) 戦後復興期から現代に至るまでの栄養政策の歩みと成果(いかにして健康長寿大国になり得たか)、
(2) 更なる少子高齢社会の進展に向けた栄養政策、
(3) 災害時でも住民の暮らしと命を支える防災栄養、
について有識者会議でとりまとめ、管理栄養士・栄養士、食生活改善推進員、栄養教諭などの専門職や、産官学連携の取組み例などを紹介する。
災害時に備えた栄養・食生活支援体制をあらわす「防災栄養」の強化も重要なテーマだ。各自治体で活用できる、地域の基本属性に合わせて災害時に備えるべき備蓄などがわかるような簡易ツールを作成する。
全国の栄養専門職による栄養改善の取組みも紹介
日本では管理栄養士・栄養士の配置が法律に規定されており、その対象となる施設は病院や学校、老人福祉施設など多岐にわたる。「地域保健法(旧:保健所法)」で規定されたことにはじまり、全国の保健所への栄養士の配置が確実に進められてきた。
栄養専門職は民間企業、研究機関などにも勤務し、各現場で栄養改善に取り組んでいる。サミットでは、日本各地のさまざまな現場での栄養改善の取組みが紹介される。
東京栄養サミットの開催概要
| 日程 | 2020年12月 |
| 主催 | 日本政府 |
| 共催(予定) | 英国、仏国(2024年オリンピック開催国)、国際機関(WHO、FAO、WFP、UNICEF、世銀など)、ビル&メリンダ・ゲイツ財団、NGOなど |
| 想定される出席者 | 首脳級、閣僚級、国際機関の長、市民社会、民間企業など |
| 目的 | 世界的な栄養改善の現状と課題を確認し、栄養課題に向けた各国の今後の国際的取組の促進を主導 |
| 主なテーマ | 健康:栄養のユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)への統合
食:健康的で持続可能なフード・システムの構築
強靭性:脆弱な状況下における栄養不良対策
説明責任:データに基づくモニタリング
財政:栄養改善のための財源確保 |
| 想定される成果 | Tokyo Nutrition for Growth Compact 2020 |
東京栄養サミット2020(厚生労働省)
第1回東京栄養サミット2020厚生労働省準備本部(厚生労働省 2020年1月16日)
栄養改善事業推進プラットフォーム(NJPPP)