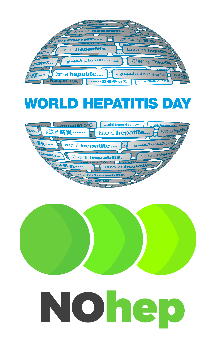7月28日は「世界肝炎デー」。世界的レベルでのウイルス性肝炎の拡大を防ぐために、世界保健機関(WHO)が2010年に定めた。
ウイルス性肝炎に感染していても、そのことに気付いていない人の数は、世界で2億9,000万人に上る。
C型またはB型のウイルス性肝炎を放置していると、やがて肝硬変になり、肝臓がんに進展しやすい。検査を受けて、早期に治療を開始することが大切だ。
厚生労働省は、肝炎ウイルス検査の受検率向上を目指して、「知って、肝炎プロジェクト」を展開している。
ウイルス性肝炎は肝臓がんの原因になる
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、炎症やがんがあっても初期には自覚症状がほとんどない。医療機関での定期的な検診や、糖尿病などの他の病気の検査のときなどに、肝炎が進展してしまってから発見されることも少なくない。
肝炎には、ウイルス性肝炎、アルコール性肝炎、非アルコール性脂肪肝炎などがあるが、大部分はウイルス性肝炎が占めている。これらによって、長期間にわたり炎症を起こした結果、肝臓が硬くなってしまった状態は肝硬変と呼ばれている。
肝硬変が進行すると、肝臓がんになりやすい。肝臓がんは治療が難しいがんで、再発することも多い。そのため肝硬変になる前の段階で、治療を開始するのが望ましい。健康診断などで肝機能の異常や肝炎ウイルスの感染などを指摘された際には、必ず受診するようにしたい。
肝炎ウイルス検査を受けることが大切
肝細胞がんの発生する主な要因は、B型肝炎ウイルスあるいはC型肝炎ウイルスの感染だ。肝炎ウイルスが体内にとどまることで、肝細胞の炎症と再生が繰り返され、がんになると考えられている。
C型またはB型のウイルスは、ごくふつうの日常生活を送っていれば、人から人に感染することはまずない(カミソリなど血液が付着する可能性のあるものの共用、消毒が不十分な状態でピアスなどをした場合などには感染する可能性がある)。肝炎ウイルスの主な感染経路は、輸血などの医療行為や性感染などだ。
肝細胞がんの予防は、「肝炎ウイルスの感染予防」と「ウイルス感染者に対する肝臓がん発生予防」が柱となる。肝炎を予防するためには、まず肝炎ウイルスに感染しないようにすることが大切だが、検査を受けて感染していることが分かったら、治療を開始することが重要となる。
厚生労働省は、肝炎ウイルス検査の受検率向上を目指して、「
知って、肝炎プロジェクト」を展開している。
プロジェクトの大使やスペシャルサポーターによる、リレー形式のメッセージ動画を公開している。
肝炎対策特別大使 伍代夏子さん
スペシャルサポーター EXILE 松本利夫さん
スペシャルサポーター コロッケさん
未診断の潜在患者はまだまだ多い
日本では多くの肝炎ウイルスの潜在患者が、感染の自覚がないまま日々を過ごしていると考えられている。日本肝臓学会の「肝がん白書」によると、B型肝炎の有病数は110~140万人、C型肝炎は190~230万人に上る。肝がんの患者数は4万7,300人(2015年)だ。
B型やC型の肝炎ウイルスに、気付かないうちに感染していることが多い。ウイルスに感染しているかどうかは検査を受けないと分からない。B型肝炎の患者数は17万人、C型肝炎は47万人。
国や自治体、マスコミなどにより肝炎ウイルス検査の必要性が呼びかけられた結果、検査を受けて感染が発見される人は増えているが、またまだ未診断の潜在患者は多いとみられている。
肝炎ウイルス検査を一度も受けたことがない人は、必ず一度は検査を受けよう。特に健康診断の肝機能の数値、「ALT(GPT)」「AST(GOT)」
*の項目が正常値より高い場合は、肝臓の病気が疑われるので、肝炎ウイルス検査を受けることが大切となる。
B型やC型の肝炎ウイルス検査の公的補助制度が、2001年にスタートした。20歳以上は初回は無料で検査を受けられ、自治体によっても無料で受けられる。簡単な血液検査なので、一度は受けてみよう。
*ALT(GPT)とAST(GOT)は肝細胞でつくられる酵素で、肝臓でアミノ酸の代謝にかかわる働きをしている。肝細胞が破壊されると血液中に放出されるため、その量によって肝機能を調べることができる。
ウイルス性肝炎の治療は進歩している
検査結果が陽性であれば、いずれかの肝炎ウイルスに感染している可能性が高く、さらに詳しい検査が行われる。感染していても肝炎を発症していない場合は、定期的に検査を受けて経過を観察しながら、発症がみられた時点で治療を開始する。
ウイルス性肝炎は今日では、多くの原因ウイルスと感染経路が判明し、発症の仕組みも解明され、さまざまな治療法が開発されている。
肝炎ウイルスに感染していても、早期に適切な治療を行うことで、肝炎を治癒し、あるいは肝硬変や肝がんへの悪化を予防することが可能だ。
患者数の多いC型肝炎の治療には、抗ウイルス薬の服用とインターフェロンの注射がある。C型肝炎ウイルスを完全に排除することを目的としている。
最初の治療として使われる抗ウイルス薬は、2014年以降、次々と新しいタイプが登場しており、かつてインターフェロン治療で改善しなかったような人もほぼ治せるようになってきた。適切な治療を行えば、C型肝炎ウイルスを肝臓から完全に排除することも可能になっている。
B型肝炎、C型肝炎ともに、医療費助成を利用すれば、自己負担額は毎月1万~2万円で済む。感染が確認された場合には、肝臓がんや家族への感染のリスクをなくすために、ぜひ治療を受けたい。
知って、肝炎プロジェクト(厚生労働省)
世界肝炎デー(World Hepatitis Day)