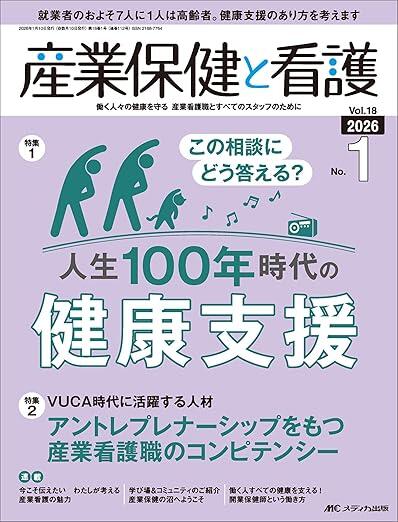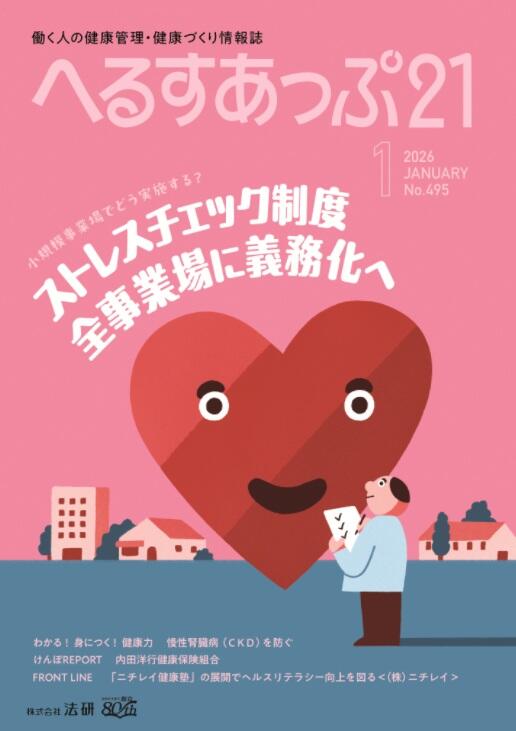ニュース
高齢者の所得格差と長生きの栄養指標・血清アルブミン値の関連が明らかに
2016年09月05日
世帯の所得など社会経済状況が寿命や健康状態に影響を及ぼしている―?
新潟県立大学の太田亜里美准教授らはこのほど、長生きの栄養指標とされる血清アルビミン値が世帯所得に関連していることを、高齢者を対象にしたアンケートや健診データから明らかにした。高齢者の血清アルブミンと社会経済状況の関連を示したのは、この研究が初めて。
血清アルビミンは血液中のたんぱく質の一種で、血しょうに含まれるたんぱく質の約6割を占める。血清アルビミン値は高齢者の栄養管理状態を評価する際、低栄養になっていないかを判断する指標になるのをはじめ、がんや肝障害などの病気、炎症などとも関連することから「長生きの栄養指標」とも呼ばれている。
これまでも高齢者の健康と所得など社会的経済状況の関連については指摘されていたが、血清アルビミン値と社会的経済状況との関連は明確になっていなかった。そこで、太田准教授らは2010年に実施された日本老年学的評価研究のうち、愛知県の4市町村で要介護認定を受けていない65歳以上の高齢者6,528人を対象にアンケートを実施。1年以内に行った健診データとアンケート結果を結合させ、分析を行った。
その結果、平均所得群と低所得群を比較すると、統計学的に明らかに低所得群の方が低い血清アルビミン値を示すことが判明。性別や年齢、教育、婚姻状況、家族構成、地域などといったほかの要因を取り除いても、この差異は残った。そのため、高齢者の血清アルビミン値は、世帯所得などの社会経済状況が関連していることが明確になった。このような研究結果が出るのは初めて。
さらに検討した結果、「(1)低所得である⇒肉・魚の摂取頻度が少ない⇒アルブミン値が低い」、「(2)低所得である⇒呼吸器疾患などの病気がある⇒アルブミン値が低い」という2つの流れを解明できたという。
太田准教授らは今後、低所得と呼吸器系の病気の増加についての関連を調べるなどして、高齢者の禁煙にも意味があることを伝えたい、などとしている。また、肉や魚の摂取が血清アルビミン値の維持につながり、健康寿命を促進させることを広く高齢者に知ってもらいたい、という。そのうえで低所得層が食料品を無理なく入手できるよう、食料品の減税や食料品券の提供など金銭的なサポートも重要であると締めくくっている。
高齢者の所得 長生きの栄養指標(血清アルブミン値)と関連
新潟県立大学の太田亜里美准教授らはこのほど、長生きの栄養指標とされる血清アルビミン値が世帯所得に関連していることを、高齢者を対象にしたアンケートや健診データから明らかにした。高齢者の血清アルブミンと社会経済状況の関連を示したのは、この研究が初めて。
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2026 SOSHINSHA All Rights Reserved.


「特定保健指導」に関するニュース
- 2025年07月28日
- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善
- 2025年07月28日
- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減
- 2025年07月28日
- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由
- 2025年07月28日
- 【妊産婦を支援】妊娠時に頼れる人の数が産後うつを軽減 妊婦を支える社会環境とメンタルヘルスを調査
- 2025年07月22日
- 【大人の食育】企業や食品事業者などの取り組み事例を紹介 官民の連携・協働も必要 大人の食育プラットフォームを立ち上げ
- 2025年07月22日
- 高齢者の社会参加を促すには「得より損」 ナッジを活用し関心を2倍に引き上げ 低コストで広く展開でき効果も高い 健康長寿医療センター
- 2025年07月18日
- 日本人労働者の3人に1人が仕事に影響する健康問題を経験 腰痛やメンタルヘルスなどが要因 働きながら生産性低下を防ぐ対策が必要
- 2025年07月18日
- 「サルコペニア」のリスクは40代から上昇 4つの方法で予防・改善 筋肉の減少を簡単に知る方法も
- 2025年07月14日
- 適度なアルコール摂取は健康的? 大量飲酒の習慣は悪影響をもたらす お酒との良い関係
- 2025年07月14日
- 暑い夏の運動は涼しい夕方や夜に ウォーキングなどの運動を夜に行うと睡眠の質は低下?