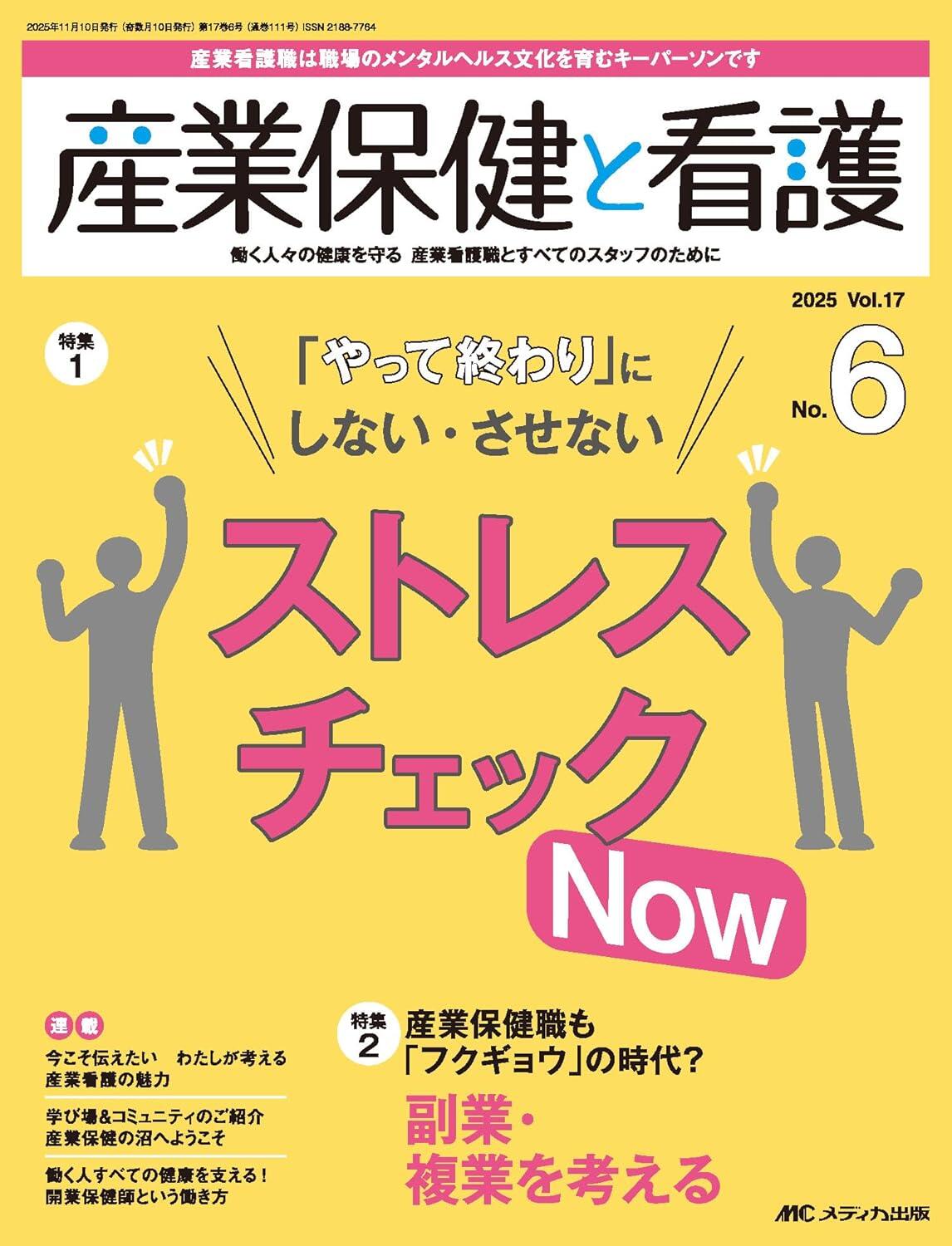ニュース
ビタミンCが「認知症」リスクを低下 女性でリスクが10分の1に低下
2018年05月30日

認知症の遺伝的な危険因子である「アポE4」をもつ女性は、血中ビタミンC濃度が高いと、将来の認知機能低下リスクを減少できる可能性があることを、日本医療研究開発機構(AMED)が世界ではじめて明らかにした。
「アポE4」遺伝子があるとアルツハイマー症を発症しやすい
アルツハイマー病による認知症の発症リスクの高い遺伝子をもつ女性は、ビタミンCを豊富に含む食品を摂取すると、認知機能低下のリスクを下げられる可能性があることが分かった。
この研究は、金沢大学医薬保健研究域医学系脳老化・神経病態学(神経内科学)の山田正仁教授、篠原もえ子特任准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、認知症専門誌「Journal of Alzheimer's Disease」に発表された。
認知症の急増は大きな社会問題となっている。認知症の原因疾患の過半数を占めるアルツハイマー病には、食事や運動などの生活習慣、それに関連する2型糖尿病や高血圧といった生活習慣病などの環境因子と、遺伝的因子の両者が関与すると考えられている。
中枢神経で脂質の代謝に関わっているタンパク質である「アポリポタンパクE(アポE)」は、遺伝子によって3つのタイプ(E2、E3、E4)があり、なかでも「アポE4」遺伝子をもっている人はアルツハイマー症を発症しやすいことが分かっている。
アルツハイマー型認知症の患者で、アポEをもっている人は6割くらいいると言われている。アポE4をもっているかどうかは遺伝子検査で調べることができる。
血中ビタミンC濃度が高いと認知症リスクが0.10倍に減少
日本人では、アポE4をもっている人(E3/E)4は、もっていないは人(E3/E3)に比べて、アルツハイマー病発症のリスクが約3.9倍になることが報告されている。女性では、アポE4をもっていることは、強力なアルツハイマー病発症の危険因子となると考えられている。しかし、認知機能の低下を防ぐ方法は分かっていなかった。
そこで研究チームは、認知症地域コホート研究で、アポ E4を保有していても認知機能の低下がみられない高齢者の栄養・食品摂取習慣に着目して、前向き縦断研究を行った。2007〜2008年の七尾市中島町研究の調査に参加した認知機能の正常な65歳以上の高齢者を対象に、平均7.8年後に追跡調査を行い、認知機能を評価した。
ベースライン調査時に抗酸化ビタミン(ビタミンC、E)の血中濃度とアポE表現型の測定を行い、ビタミンC、E血中濃度とアポE4保有と将来の認知機能との関連を解析した。
ビタミンC、Eの血中濃度を、男女別に、低い群、中間の群、高い群の3群に分けて解析したところ、アポE4を保有している女性では、血中ビタミンC濃度がもっとも高い群は、もっとも低い群と比べ、認知機能の低下(認知症または軽度認知障害の発症)のリスクが0.10倍(オッズ比)に減少することが判明した。

認知症の先制医療の確立を目指す
また、アポE4をもっていない男性では、血中ビタミンE濃度がもっとも低い群に比べて、ビタミンE濃度がもっとも高い群は将来の認知機能低下のリスクが0.19倍、中間の群は0.23倍に減少した。なお、女性ではビタミンE血中濃度と将来の認知症や認知機能の低下のリスクとの関連は示されなかった。
なお、アポE4をもっている男性は人数が少なく解析ができなかったという。なお、今回の研究の参加者は、ほとんどがビタミンC、Eのサプリメントを使用していなかった。
研究結果により、将来認知機能が低下するリスクが高いアポE4保有女性において、ビタミンCを豊富に含む食品を摂取することが認知機能低下リスクを下げる可能性が示された。
研究チームは今後も、アポE4遺伝子保有者におけるアルツハイマー病発症過程をビタミンCが抑制する作用機序の解明、さらに、アポE4保有者を対象に含むビタミンCによるアルツハイマー病に対する予防介入研究などを行い、認知症の先制医療の確立を目指していきたいとしている。
日本医療研究開発機構(AMED)金沢大学医薬保健研究域医学系脳老化・神経病態学
Higher Blood Vitamin C Levels are Associated with Reduction of Apolipoprotein E E4-related Risks of Cognitive Decline in Women: The Nakajima Study(Journal of Alzheimer's Disease 2018年5月11日)
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.


「健診・検診」に関するニュース
- 2025年08月21日
- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告
- 2025年07月07日
- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市
- 2025年06月27日
-
2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%
過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日
-
【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ
対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日
- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】
- 2025年05月20日
-
【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築
―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日
- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善
- 2025年05月16日
- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少
- 2025年05月12日
- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要
- 2025年05月01日
- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】