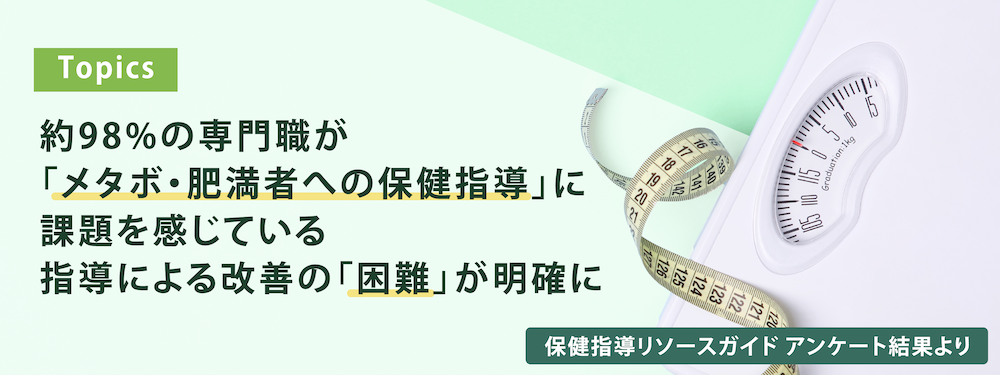ニュース
女性は50歳を越えると骨粗鬆症のリスクが上昇 「定期的に検査を」
2018年10月31日

50歳代女性の5割以上が骨粗鬆症の検査を受けていないが、「骨粗鬆症になる可能性があると思う」という女性が7割以上――女性に骨粗鬆症の検査を受けることの大切さを伝え、検査受診率を向上させる必要性があることが、ファイザーが全国の閉経後の女性3,168人を対象とした調査で浮き彫りになった。
女性の骨粗鬆症は50歳代から増加
10月20日は「世界骨粗鬆症デー」だった。国際骨粗鬆症財団(IOF)を中心に「骨粗鬆症による骨折をなくす」ことを目指す啓発イベントが世界規模で開催された。
国民生活基礎調査によると、日本では介護が必要となった主な原因の第3位は骨折・転倒で、骨粗鬆症がそのリスクを高める。日本骨粗鬆症学会によると骨粗鬆症の患者数は1,280万人に上る。女性の骨粗鬆症患者は男性の3倍というデータがあり、とくに深刻だ。
女性は50歳前後に迎える閉経にともない、骨粗鬆症のリスクが高まる。女性の有病率は50歳代から徐々に上昇し、60歳代の3人に1人、80歳代では2人に1人が罹患しているという調査結果がある。
骨粗鬆症による骨折は、要介護状態や寝たきりの原因になる。患者の身体的・経済的な負担は大きく、家族にも大きな負担をかける可能性がある。また、椎体骨折と大腿骨近位部骨折は、その後の死亡率を上昇させることが報告されている。
関連情報
骨粗鬆症の検査を受けている女性は少ない
ファイザーは、世界骨粗鬆症デーに合わせて、50歳代以上の閉経後女性3,168人を対象に意識調査を行った。それによると、骨粗鬆症に関する認知率は高いが、骨粗鬆症の検査を受けている女性は少ないことが示された。
調査では、ほぼ全ての回答者(99.3%)が、骨粗鬆症について認識しており、約7割(71.7%)は、「どのような病気か詳しく知っている」と回答した。
一方、「糖尿病などの生活習慣病と関連がある」(11.1%)、「放っておくと悪化し寿命が短くなる」(18.9%)、「骨折しても痛みや自覚症状がないことがある」(37.4%)、「治療すると骨折をある程度防ぐことができる」(37.8%)など、骨粗鬆症の認知は十分でないことが示された。
骨粗鬆症に対して非常に不安に思うと回答した割合の高かった項目は、「骨折して寝たきりになること」(66.8%)、「(寝たきりで要介護になり)家族に迷惑がかかること」(65.1%)、「身体に痛みが生じること」(46.1%)だった。
骨粗鬆症に関する知識は、検査を受けたことがある人の方が受けたことがない人よりも全体的に高かった。骨粗鬆症に関する情報の普及とともに、検査を受けることの大切さを伝え、検査受診率を向上させることの必要性が示唆された。
4割弱(38.8%)の人は骨粗鬆症の検査を「一度も受けたことがない」と回答した。50歳代女性では、その割合が5割(55.2%)を超えている。また、身近な人で骨粗鬆症になった人がいても検査を受けたことがない人は3割弱(27.6%)だった。また、骨粗鬆症になった場合に、どの診療科に受診すればよいか分からないと回答した人は2割弱(18.2%)だった。
「閉経後の女性は定期的に骨粗鬆症の検査を」と呼びかけ
「骨粗鬆症になる可能性があると思う」「今はないが、将来骨粗鬆症になる可能性があると思う」と回答した人は74.7%であった。その中で骨粗鬆症の検査を「受けたことがない」と回答した人は42.2%であり、骨粗鬆症の不安を感じながらも検査を受けていない人が多いことが明らかになった。
検査を受けたことがない理由の上位は、「検査を受けに行くきっかけがなかったから」(40.9%)、「気になる症状がなかったから」(39.8%)。
「女性の健康寿命は74.79歳で、平均寿命と健康寿命の差は12.35年にも及ぶ。女性は日常生活に制限のある状態で生活している期間が長い。その原因のひとつが骨粗鬆症だ。しかし、骨粗鬆症は初期では自覚症状に乏しいため、気づかないまま症状が進行しているケースも多くみられる。そのため、少なくとも閉経後の女性は、定期的に骨粗鬆症の検査を受け、骨の健康状態を確認することが推奨される」と、骨粗鬆症財団理事、国際医療福祉大学教授、山王メディカルセンター・女性医療センター長の太田博明氏は調査結果について解説している。
「今回の調査では、閉経後の女性が定期的に骨粗鬆症の検査を受けている割合は1割強にとどまり、一方で検査を一度も受けたことがない人が約4割に上った。検査を受けたことがない理由は、"検査を受けに行くきっかけがなかったから""気になる症状がなかったから"がともに約40%であり、自覚症状が乏しい骨粗鬆症に対する一般の方々への更なる情報提供の必要性を感じさせる結果となった」としている。
骨粗鬆症の診断基準は骨密度の評価指標であるYAM値が70%以下となっている。太田氏は、65歳まではこのYAM値を80%以上に保つことを目標とする「65-80(ろうごをハッピーに)」運動を展開しているという。医療従事者が情報提供を行うとともに、骨検診の受診を勧奨することが重要だという。
ファイザーによる骨粗鬆症マネージャーサポートプロジェクト(医療従事者向け)
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.


「保健指導リソースガイド」に関するニュース
- 2025年01月27日
- 保健指導や健康教育に役立つ!「資材・ツール」一覧をリニューアルしました【サイト情報】
- 2024年12月19日
- 2024年度版【保健指導アトラス】を公開!保健指導に携わる人が知っておきたい法律・制度
- 2024年09月12日
- 【専門職向けアンケート】メタボ・肥満者への保健指導に関する実態調査(ご回答者にAmazonギフトコード500円分)【受付終了】
- 2024年01月18日
-
【アンケート:抽選でAmazonギフト500円プレゼント】
「健康課題」と「健康管理システム/健康支援サービス」の活用について - 2023年11月27日
- 2023年度版【保健指導アトラス】を公開!保健指導に携わる人が知っておきたい法律・制度
- 2023年10月20日
-
インスリン・フォー・ライフ(IFL)グローバル
最近の活動と取組みについて(アリシア・ジェンキンス代表) - 2023年09月15日
- 2023年インスリン・フォー・ライフ(IFL)のウクライナ支援(IDAF)
- 2023年09月12日
- 期間限定40%オフ!「健診・予防3分間ラーニング」DVDセール開催中!2023年10月13日(金)まで
- 2023年07月12日
- 【アルコールと保健指導】「飲酒量低減外来」についてのインタビュー/面談時に30秒でできるアルコール指導ツールの紹介
- 2023年07月04日
- 健康経営の推進に!課題解決に合ったものを探せる「健康管理システム」一覧をリニューアルしました【サイト情報】