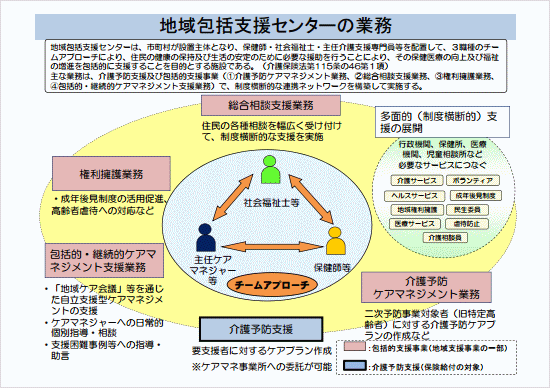今日、介護離職の問題が毎日のように取り上げられ、様々な介護サービスの使い方が紹介されています。在宅介護の現場にカメラが入り「やっぱり家がいいな。気を使わなくていいし…」と寝たきりの高齢者がインタビューに応えています。しかし、高齢者や家族が思うことのひとつに、最期まで自宅で暮らし続けることができ、安らかな死を迎えることができるのかという不安です。

写真:某施設の部屋。病院より落ち着きます。
1. 介護が必要となれば
2000年に始まった介護保険制度は3年毎の見直しで、より利用しやすい制度へと改定されながら運用されています。介護に関する総合的な相談は、各市町村が支援する地域包括ケアセンターで無料で受けつけています。介護について困っている場合は、まず地域包括支援センターに相談すれば、そこから様々な制度や支援に繋がっていきます(図)。要は自分一人で抱えるのではなく、まずは専門家に相談するというステップを踏むことが大切だと思います。
2. 家族の役割
多くの人は病状が急変したときに医療機関を訪れます。そこで必ず家族が呼ばれ、病状の説明や治療の内容が告げられます。日本人は一般的に家制度の名残から、家族の絆を尊重するため、家族の価値観や意思を大切にする風潮があります。これは、個人を前提とした西洋の考え方とは大きく異なります。がんの急変時の延命処置などを決定する際に、医療従事者は家族に状況を説明し、家族の判断を仰ぐことが殆どで、患者の意思だけで十分と考える医療機関は非常に少ないです。
患者の意思だけで判断すると、家族から不満や訴訟が起きることを懸念するからです。しかし反対に家族や親族の意向がまとまらないために、本人の意思が尊重されず適切な医療やケアが選択されないことがあるのも事実です。
本人がリビングウィル(生前の意思)を残していれば、それに従い治療やケアを選択できるので判断がしやすくなると考えます。また、正式な書面が無くても日常の会話の中から、本人の意思を推し量ることができるので、ふだんから出来るだけ兄弟姉妹などの親族と本人がリビングウイルについて話せる状況をつくっておくことが大切です。
3. 親だからこそ迷い苦しむもの
多くの人は、自分を生み育てくれた親の死期が近づいていることを悲しく残念に思いながらも、「なぜご飯が食べられなくなったのか、納得がいかない・・・」という思いも聞きます。
人には生きている限り役割があると感じます。子供を見守り、支えになっているのは90歳を過ぎても同じであり、年を重ねるごとにその存在は大きく大切さが増してきます。当たり前に生きているだけはなく、長く生き続けていられることへの感謝の気持ちを親と子の双方に感じることができるからでしょう。しかし、自然に逆らっては生きていけないのも事実であり、寿命を全うしなければなりません。
4. 経験から学んだこと
私は87歳の母をグループホーム(以下、ホーム)で看取ることができました。ホームに入って約半年ほどで持病の心臓の発作が出現し、夜間に救急車で病院に運ばれました。当直の医師は血圧が非常に低く、助かる見込みは少なく、あと数時間かもしれないと聞きました。ところが自然に命を取り戻し、そこから約2か月の終末期ケアをホームの職員と行うことになりました。
医療としてはかかりつけ医の往診と訪問看護ステーションのケアのみで、点滴などの治療や検査は一切せず、ただ苦痛のない穏やかな日々を送れるよう見守りました。私が仕事帰りに立ち寄ると、母はしばらくしてから「大丈夫だから、早く帰りなさい・・・」と手を振ってくれました。一緒には暮らせなかったのですが母にとっては安心できる場所であったと思います。
最期のときが近づくと、1日の大半を目を閉じて、眠っているような時間が続きます。血圧を測ると拡張期血圧は100を切ることが多く、尿の量が減っていきます。母は、時々目を開けて周りを見回し、今いる場所、おかれている状況を確認しているかのように見えました。家族はただそっと手を握ったり、さすったりすることだけしかできませんでしたが、孫や子供たちに看取られて、最期は呼吸が止まっているのを介護職員に見とどけていただきました。
担当の介護職員は初めてのことで、不安もあったと思いますが、枯れるように穏やかな終末期ケアを経験したことで、他の入所者の方もホームで看取りたいという気持ちになったと聞きます。
5. 地域での看取り
地域包括ケアシステムの構築が目指すものは、住み慣れた地域で最期まで安心して暮らすことです。最期は自宅であれ、地域の住まいであれ、病院ではない生活の場で自分らしく、尊厳のある日々を過ごすことが望まれます。
自宅であれば生活音、料理の臭い、家族の話し声、全てが本人に安心感とやすらぎを与えます。いつも通りの生活の延長線上にこそ死があるのではないかと思います。
一人暮らしの在宅死と言えば孤独死と捉えられていますが、最期まで自宅に居たいと願っている高齢者の意思を尊重することができるシステムの構築が望まれているのではないでしょうか。地域全体で「如何に死にたいか、どのように死を迎えたいか」を考えることがタブーでなくなるような社会を目指さなくてはならないと考えます。
<参考文献>
1)上野千鶴子「ケアのカリスマたちー看取りを支えるプロフェッショナル」亜紀書房2015
2)村上紀美子「ともに老い、看取る地域のつくりかた」特集「「老衰」で家で最期まで―超高齢化社会における在宅終末期医療のあり方を考える」訪問看護と介護 Vol20.No10医学書院2015
■共同著者
栗岡 住子(保健師、産業カウンセラー、MBA、医学博士)
詳細はこちら≫(オピニオン連載)
公衆衛生看護に必要なマネジメント