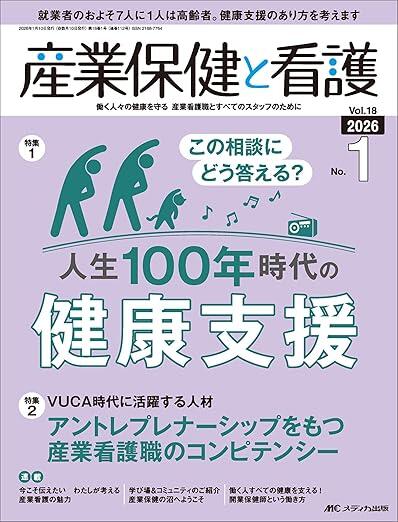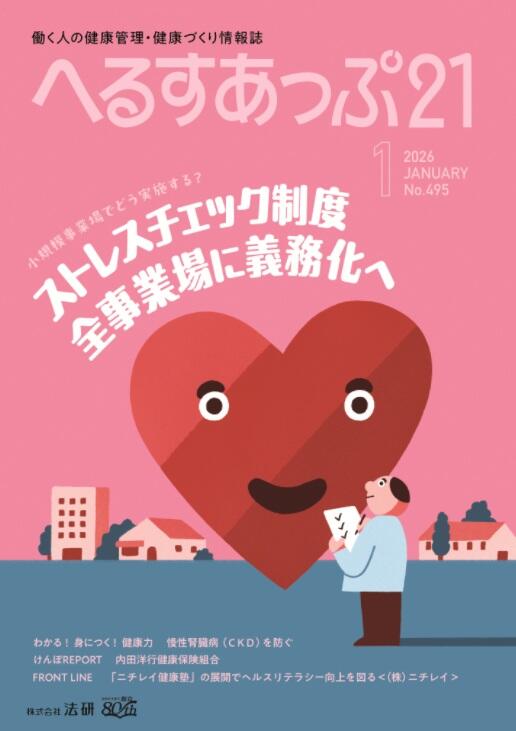ニュース
「妊娠」「出産」に対する正しい理解を 晩産化と少子化に教育の充実で対策
2015年12月16日
高校生や大学生に「妊娠」や「出産」に対する正しい知識をもってもらおうと、厚生労働省の研究班はこのほど教育用DVDを製作した。
研究班の調査では「30歳を過ぎると妊娠する能力が衰えていく」ことを知っていた高校生では男性14%、女性22%にとどまった。「不妊や妊孕力、不妊治療などに関する適切な教育が必要」と研究班は指摘している。
研究班の調査では「30歳を過ぎると妊娠する能力が衰えていく」ことを知っていた高校生では男性14%、女性22%にとどまった。「不妊や妊孕力、不妊治療などに関する適切な教育が必要」と研究班は指摘している。
科学的なデータで妊娠や不妊を解説
DVDを製作したのは「若い男女の結婚・妊娠時期計画支援に関するプロモーションプログラムの開発に関する研究」班(代表:山本眞由美・岐阜大学保健管理センター教授)。
DVDでは、科学的なデータをふまえて妊娠や不妊を解説している。不妊・妊娠についての若者へのインタビューを交えながら、妊娠のタイミングについて「男女2人の問題として考えることが必要」などと呼びかけている。
世界保健機関(WHO)による不妊の定義を説明し、「女性は年齢とともに妊娠しにくくなり、流産や妊娠中の体のトラブルのリスクも高まる」「最新の医療でも妊娠可能年齢が劇的には上がっていない」「不妊の原因は男性にもある」といった知識を紹介している。
画面をクリックすると動画の再生がはじまります
「30歳を過ぎると妊娠能力が低下」 高校生の認知率は男性13.7%、女性22.3%
日本では晩婚化・晩産化を伴う少子化が進行しており、2013年の合計特殊出生率は1.43だった。晩婚化は妊娠適正年齢を逃すことによる不妊の増加を、晩産化は母体の高齢化によるハイリスク妊娠の増加をもたらす。
"晩婚化、晩産化を伴う少子化"の現象にはさまざまな社会的要因が関与しているが、高齢化が進む傾向にある不妊治療の現場で、「もっと若い時期に、妊娠時期などの人生設計について考える機会をもてれば、結婚や妊娠の時期をもっと早く迎えていたかもしれない」という思いを持つカップルが少なくない。
研究班は昨年4~6月、全国の高校生1,866人と大学生1,189人に妊娠に関する意識調査を行った。
「女性の妊娠する能力が30歳を過ぎた頃から少しずつ低下すること」を、「よく知っていた」と答えたのは、高校生で男性13.7%、女性22.3%、大学生で男性30.0%、女性41.9%だった。高校生の男性では、「全く知らなかった」と答えた者が36.1%いた。
「不妊治療を受けていても女性の妊娠する能力は年齢とともに少しずつ低下すること」について「よく知っていた」と答えたのは、高校生で男性8.0%、女性14.1%、大学生で男性19.4%、女性31.0%だった。
"子育て"をもっと身近に体験できるアプローチが必要
日本では晩婚化少子化が進んでいるが、高校生・大学生は、結婚・挙児を希望する者が大多数であり、結婚をしたい年齢も、高校生と大学生で男女ともに25歳前後だった。この年代では、年齢が上がるにつれ、結婚・挙児希望が下がるわけではないことも判明した。
一方で、高校生・大学生ともに、結婚や挙児を希望する者が大多数であるにもかかわらず、自分の人生における「子育て」の優先度が低く、多くの高校生・大学生が、将来の「子育て」に対して経済的不安や知識・情報不足による不安を抱いているものが多かった。
挙児希望に影響を与える背景は、高校生では「実家経済力」、大学生でも「将来の経済不安」「実家経済力」「健康状態」「健康への関心」の影響を強く受けることが示された。少子化や晩婚化に対するアプローチの視点としては、「経済」と「健康」であることが重要であることが示唆された。
「高校生・大学生がもっていないことが、日本では高校生・大学生が子育ての現場に接する機会が少ないため、子育てのイメージをもてないのではないか。高校や大学のカリキュラムや実体験学習の場で、小児に触れる機会を増やし、"子育て"をもっと身近に体験するようなアプローチが必要だ」と、山本教授は言う。
文部科学省によると、不妊について詳しく説明している高校生の保健体育の教科書は少ない。国の少子化対策でも、妊娠に関する教育の充実が指摘されている。
厚生労働科学研究費補助金 政策科学総合研究事業「若い男女の結婚・妊娠時期計画支援に関するプロモーションプログラムの開発に関する研究」報告書(全国大学保健管理協会)
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2026 SOSHINSHA All Rights Reserved.


「健診・検診」に関するニュース
- 2025年08月21日
- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告
- 2025年07月07日
- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市
- 2025年06月27日
-
2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%
過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日
-
【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ
対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日
- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】
- 2025年05月20日
-
【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築
―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日
- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善
- 2025年05月16日
- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少
- 2025年05月12日
- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要
- 2025年05月01日
- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】