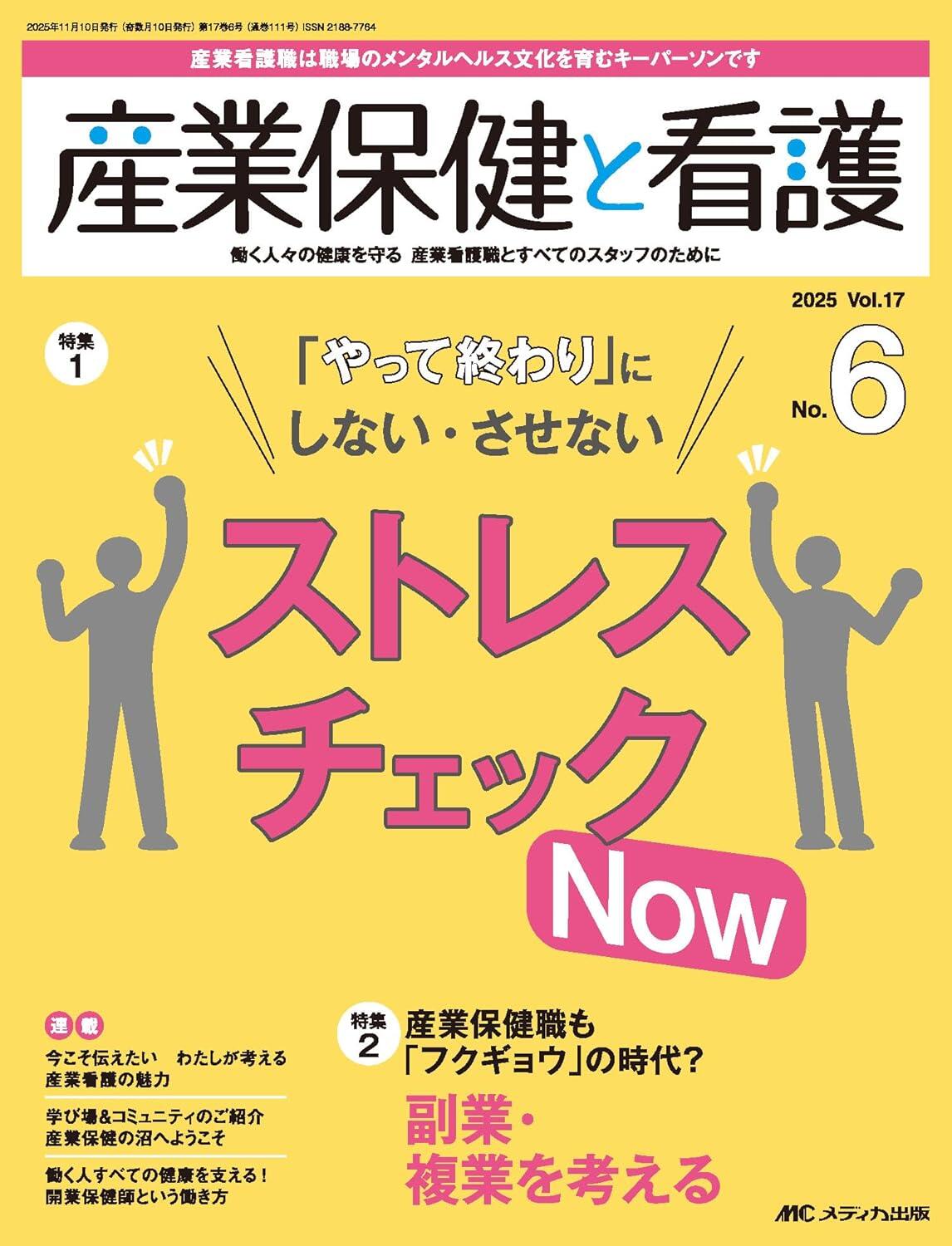ニュース
3月8日は「国際女性デー」 女性の健康を守るための10の課題とは
2017年03月08日

3月8日は「国際女性デー」だった。国連(UN)が女性の権利のために、1977年に「国際女性デー」を定めてから、今年で40年目になる。世界保健機関(WHO)は「女性の健康 10項目の課題」を公開している。
女性が自覚をもって健康問題に取り組むべき
1995年に北京で開催された「世界女性会議」では、「すべての女性の健康のあらゆる側面、特に自らの出産数を管理する権利を明確に認め再確認することは、女性のエンパワーメントの基本である」と宣言されたが、それから20年を経た現在、女性はいまだ多くの健康上の問題に直面している。
「各国の医療制度を強固にして、資金調達のシステムを整備し、意欲的な医療従事者の数を十分に増やすためにWHOは懸命に取り組んでいるが、まだ十分ではありません」と、世界保健機関(WHO)の家族・女性・子どもの健康局の副長官であるフラビア ブストレオ氏は言う
「現在、多くの国で"女性の地位向上"は、政治家の演説のときの美辞麗句でしかなく、真の意味での実現には遠い。また、身体面でもメンタル面でも、健康を維持し、自分の体を守るための十分な知識を得る機会をもたない女性が世界には非常に多い。女性自身が自覚をもって自分の健康問題に取り組むべきです」と、ブストレオ氏は指摘している。
WHOが公開している女性が直面している健康・医療上の問題は、大きく以下の10項目がある。
1. がん
女性が罹患するがんの中でもっとも多いのは乳がんと子宮頸がんだ。女性がん検診を受けられるようにし、早期発見・治療につなげることは、女性の健康を保持するために必要だ。
世界では子宮がんが原因で亡くなる女性は約50万人、子宮頸がんが原因で亡くなる女性は約50万人に上る。それらの多くは、がんのスクリーニング検査、がんの予防と治療を実施すれば救えた命だ。また、子宮頸がんの予防接種は、低・中所得国を中心に十分に普及していない。
2. 母親としての健康
20世紀に医療は大きく進歩し、女性の妊娠・出産をより安全にケアできるようになった。それでも世界では2013年に約30万人が出産時の合併症が原因で亡くなっている。
もしも家族計画の基本的なサービスへのアクセスが保障されていたのなら、これらの死の大部分は防げたはずだ。女性が安心して子供を産める体制づくりを世界規模で広める必要がある。
3. 非感染性疾患(NCD)
世界で2012年に470万人の女性が、心臓血管病、がん、呼吸器疾患、糖尿病などにより、70歳未満で亡くなっている。うち50%以上は先進国で増えている肥満が原因だ。
年齢が進んでから生活習慣を改善するのは難しいので、より若い世代から保健指導を始める必要がある。
世界的に高齢の女性の死亡の46%は心臓血管疾患で占められ、14%はがん(肺がん、乳がん、大腸がん、胃がん)で占められる。また、心臓血管疾患は男性に多い疾患だと思われているが、世界的に女性でも死因のトップになっている。
非感染性疾患(NCD)は、喫煙、食習慣、運動不足などの日常生活因子、高血圧、高血糖、高脂血症などの身体的因子、うつ病、不安、急性・慢性ストレスなどの社会的・精神的因子との関連が深い。NCDの予防にはこれらの危険因子を取り除くことが重要だ。
4. 慢性疾患の管理
女性では、高血圧・腎臓病・糖尿病などの生活習慣病は、特に若い世代ほど健診を受ける機会が少なく、適切な治療を始めるのが遅れる傾向がある。
特に先進国では、妊娠の高齢化にともなって、妊娠時にすでに高血圧や高血糖がある女性が多くなっている。妊娠を希望する場合には、自身と子供の健康のために、妊娠前からしっかり高血圧や糖尿病を管理(プレコンセプショナルケア)する必要がある。
5. 高齢化
高齢の女性が直面している健康問題の多くは、喫煙、座りがちの生活習慣、不健康な食事など、若年期や成人期の生活スタイルから続くリスク要因によるものだ。
高齢者が身体的や認知機能を低下させる健康問題には、視力低下(白内障など)、難聴、関節炎、うつ病、認知症などだ。男性も多くがこうした病気に苦しんでいるが、多くの国で女性は男性よりも治療や支援を受ける可能性が低い。
家事に従事している専業主婦が高齢になると、男性に比べ、社会保障や健康保険が薄く、社会福祉にもアクセスしづらく、また貧困である傾向がある。加齢に伴い増える生活習慣病や認知症などによるダメージは、貧困な高齢女性でより深刻だ。
また、病気と加齢は両方ともに体のネガティブな変化だが、高齢期には生活習慣病を抑えるのに加え、老化の進行をいかに遅らせるかという視点も必要になる。非感染性疾患(NCD)を予防・コントロールするための保健指導も、高齢期の健康を保証するものでなければならない。
6. メンタルヘルス
女性は男性よりストレスを受けやすく、うつや身体的不調といった症状を経験しやすいことを示した報告は多い。うつ病は女性とってもっとも一般的なメンタルヘルス上の問題で、60歳以上の女性の自殺の主な原因だ。女性のメンタルヘルスを向上させるために、世界的により多くの支援が必要となっている。
女性のうつは、女性ホルモンの変化に運動した「月経前症候群(PMS)の一症状としてのうつ」「マタニティ・ブルー」「更年期障害にともなううつ」などがある。女性が医療にアクセスし、適切な治療を受けやすくする必要がある。
7. 女性に対する暴力
女性はさまざまなかたちで暴力を広範囲に受けやすい。身体的な性的暴力(それがパートナーによるものでも、非パートナーによるものでも)はもっとも痛ましい。50歳以下の女性の3人に1人が、パートナーや非パートナーからの性的暴行を経験しているという調査結果がある。
暴力は女性に身体的・メンタルヘルス的に深刻な傷をもたらす。パートナーから暴力を受けた女性は、うつ病になる可能性が2倍高く、アルコール障害になる可能性も約2倍に上昇する。
暴力を抑止すると同時に、暴力を受けた女性をサポートする体制を整備するために、各国の保健機関が注意を向ける必要がある。警察・病院・児童相談所・婦人相談所・NPOなどへの相談をスムーズにできるようにする仕組みづくりが求められている。
8. 若者への対策
データのある41ヵ国のうち21ヵ国では、15~19歳の若年女性の3分の1以上が貧血と報告されている。もっとも多い鉄欠乏性貧血は、出産中の出血および敗血症のリスクを増加させる。
また、世界では年間に20歳以下の女性が約1,300万人出産している。特に途上国では、妊娠・出産に伴う合併症が、若い女性の死因の上位を占める。性感染症(STI)の予防を含め、若い世代への保健指導は重要だ。
9. リプロダクティブ・ヘルス
性と妊娠・出産の問題は、15~44歳の女性の健康問題の3分の1を占める。世界では2億2,200万人の女性が、必要な避妊処置をしていない。若年者の危険なセックスは特に途上国で深刻な問題になっている。
15~19歳の若年女性では、世界で毎年300万件の安全でない流産が発生しており、永続的な健康問題や妊産婦死亡に大きく影響している。妊娠と出産の合併症は、低所得国と中所得国の15~19歳の若年女性の女児の死亡原因の主なものだ。
10. 感染症(HIVなど)
最初のエイズ(AIDS)流行から30年が経過した。HIV感染の犠牲となりやすいのは女性だ。いまだに多くの若い女性はHIV感染から身を守り、必要な治療を受けようと苦闘している。女性が感染しやすい疾患であるHIVやパピローマウイルス(HPV)について、感染予防の十分な対策を施す必要がある。
感染症では結核についても見逃してはならない。低所得の20~59歳の女性では結核は死因の上位に位置付けられる。
Ten top issues for women's health(世界保健機関 2015年3月)International Women's Day 2017
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.


「健診・検診」に関するニュース
- 2025年08月21日
- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告
- 2025年07月07日
- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市
- 2025年06月27日
-
2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%
過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日
-
【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ
対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日
- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】
- 2025年05月20日
-
【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築
―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日
- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善
- 2025年05月16日
- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少
- 2025年05月12日
- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要
- 2025年05月01日
- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】