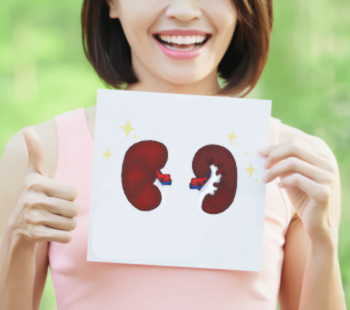ニュース
糖尿病の治療と仕事の両立 連携して治療をサポート 働き方改革に前進
2017年05月25日

働き盛りの世代で糖尿病は増えている。仕事を優先させて糖尿病の治療をおろそかにしないために、医療や労働の環境で実施する具体的な対策が考えられている。
糖尿病の治療を早期開始・継続することが必要
働き盛りの世代で糖尿病は増えている。人間ドックを受けた人の4人に1人は「糖代謝異常」と判定されているという報告がある。糖尿病などの治療を続けながら、仕事もおろそかにしないための具体的な施策が必要とされている。
働き盛りの世代の中心となる40歳代の人で、糖尿病の強く疑われる人のうち治療を継続的に受けている人は、男性で38.7%、女性で42.9%に過ぎず、治療を受けていない人の割合は男性で60.7%、女性で57.1%に上る(2012年国民健康・栄養調査)。つまり、治療を受けないで糖尿病を放置している人が過半数を超えている。
2型糖尿病は初期の段階では自覚症状が乏しく、治療を行わなくとも、働き続けるのが困難になるような問題は直ちには起こらないかもしれない。しかし放置しておくと、10年後、20年後に確実に、深刻な合併症を引き起こす。
糖尿病が進行すると、糖尿病網膜症による視力障害や失明、糖尿病腎症による血液透析の導入、神経障害や足壊疽による下肢切断などが引き起こされる。また、心筋梗塞、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症など動脈硬化症の発症リスクが2〜3倍に増加する。
血糖値が高いことによる代謝失調の状態は、治療を開始し血糖値を正常化したのちも長期にわたり影響が残すことが知られており、「遺産効果」「メタボリックメモリー」と呼ばれている。したがって、治療をより早期に開始し、継続することが重要となる。
治療と仕事の両立 連携して治療をサポート

両立支援モデル事業を開始 「糖尿病両立支援手帳」で連携
就労している糖尿病患者が真摯に治療に取り組むためには、治療と仕事との両立が円滑に行われていることが重要で、その取組みのひとつは、医師~患者~企業連携を推進し、チーム医療として就労患者をフォローしていく仕組みを開発・普及することだ。
中部ろうさい病院は、2014年度より全国12労災病院で、医療機関と職場の連携を推進しその連携マニュアルを作成するための両立支援モデル事業を開始している。
糖尿病のある就労者は、両立支援に関する事業場内のルールなどにもとづいて、支援に必要な情報を収集して事業者に提出する必要がある。
この際、就労者は職場が定める様式などを活用して、仕事に関する情報を主治医に提供した上で、主治医から必要な情報の提供を受けることが求められる。
そこで提唱されているのが、産業保健スタッフや人事労務担当者が、主治医に相互に連絡できる「糖尿病両立支援手帳」を設けることだ。
これにより、仕事の治療の両立の支援を必要とする患者から相談があった場合に、労働者が必要十分な情報を収集できるようになる。
「糖尿病両立支援手帳」を活用すれば、患者自身や、事業場の関係者(事業者、人事労務担当者、上司・同僚、労働組合、産業保健スタッフなど)、医療機関関係者(主治医、看護師、医療ソーシャルワーカーなど)、地域の支援機関などが、互いの情報を共有でき、相互に必要な情報を交換すること可能になると考えられている。
具体的には、糖尿病のある就労者自身に「糖尿病両立支援手帳」を主治医に受診時に提出してもらい、主治医より現在の治療状況、就労に関わる注意点や就業上の制限の必要性などについて記入してもらい、同時に就業のスタɼルに合わせた治療法を検討してもらう。
手帳に記入された返答より必要情報を得て、事業場の関係者は職場での対応を検討する。


両立支援コーディネーターを養成

就労と糖尿病治療の両立の手引きを作成
糖尿病の治療と就労の両立を支援するために、個々の患者などに応じた「オーダーメイド」の対応が求められる。
また、糖尿病患者やその家族だけでなく、産業医をはじめとする産業保健関係スタッフや主治医、職場の上司・同僚や就労支援機関などのスタッフなど、さまざまな立場の人々が接することが多くなる。
そのため、支援の対象者の職場に関することはもとより、病態の理解、障害の程度や機能を評価できる医療知識、両立支援に必要な雇用に関する法律ならびに利用可能な行政サービスなど、幅広い知識が必要となる。
そこで日本糖尿病協会は、就労環境の整備に携わる産業医、産業保健スタッフへの糖尿病教育支援の一環として、e-ラーニングを受講もらえるシステムの構築を行っているという。
e-ラーニングを通して、簡便に現在の糖尿病や治療のエッセンスの知識を業務に役立ててもらう。また、産業医や保健スタッフの整っていない中小企業などへは、日本糖尿病協会から医師やコメディカルスタッフを派遣する出張糖尿病教室も計画中だという。
企業の視点ばかりでなく、患者の視点も重視した「就労と糖尿病治療の両立の手引き」の作成も計画中だ。

治療と職業生活の両立について(厚生労働省)
治療と就労の両立支援マニュアル(労働者健康安全機構)
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.


「健診・検診」に関するニュース
- 2025年06月02日
- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】
- 2025年05月20日
-
【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築
―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日
- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善
- 2025年05月16日
- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少
- 2025年05月12日
- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要
- 2025年05月01日
- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】
- 2025年05月01日
- 【デジタル技術を活用した血圧管理】産業保健・地域保健・健診の保健指導などでの活用を期待 日本高血圧学会
- 2025年04月17日
- 【検討会報告】保健師の未来像を2類型で提示―厚労省、2040年の地域保健を見据え議論
- 2025年04月14日
- 女性の健康のための検査・検診 日本の女性は知識不足 半数超の女性が「学校教育は不十分」と実感 「子宮の日」に調査
- 2025年03月03日
- ウォーキングなどの運動で肥満や高血圧など19種類の慢性疾患のリスクを減少 わずか5分の運動で認知症も予防