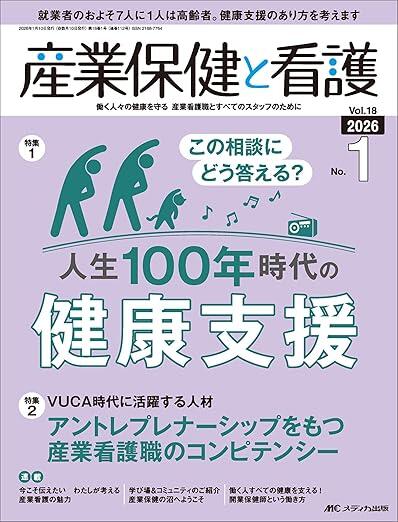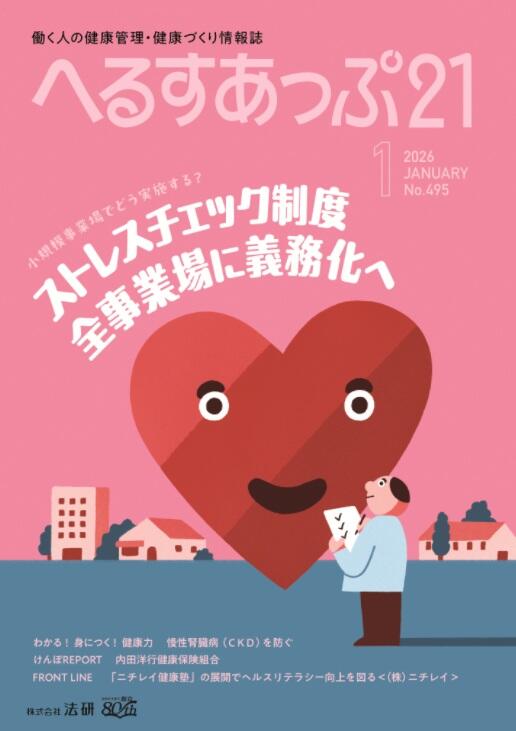ニュース
玄米は苦手? 「もち米玄米」なら大丈夫 血糖値スパイクを抑えられる
2017年06月01日

玄米が健康に良いことはよく知られているが、「硬くて食べにくい」と敬遠する人は少なくない。そんな人でも、「もち米玄米」なら無理なく食べられる。
「もち米玄米」が血糖コントロールを改善するという研究が発表された。食後に血糖値が上昇する「血糖値スパイク」も抑えられることが判明した。米を主食とする日本人にとって嬉しい情報だ。
「もち米玄米」が血糖コントロールを改善するという研究が発表された。食後に血糖値が上昇する「血糖値スパイク」も抑えられることが判明した。米を主食とする日本人にとって嬉しい情報だ。
玄米が糖尿病を改善 血糖値を下げる効果
玄米は、稲の果実である籾から籾殻のみを取り除いたもの。これに対して、ふだんよく食べている精白米は、玄米からぬかと胚芽を取り除いて胚乳のみの状態にしたものだ。
玄米には食物繊維やビタミンB群をはじめ、豊富な栄養成分が含まれている。近年では、低GI(グリセミック インデックス)食品としても注目される。
玄米の外皮は栄養価が高いため、精白米に比べ食物繊維が約6倍、ビタミンB1が約5倍、マグネシウムが約5倍多く含まれる。
ビタミンB1は糖質の代謝に欠かせない栄養素で、ビタミンB群が不足するとエネルギー不足になって疲れやすくなる。しっかりエネルギー消費をしてやせやすい体を作るためにも不可欠な栄養素だ。
また、食物繊維には水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の2つがあるが、玄米にはどちらも含まれている。豊富に含まれる食物繊維は、食後の血糖値の上昇を抑えてくれる。
それに加えて、琉球大学の研究チームは、玄米に含まれる成分「γ(ガンマ)-オリザノール」に、インスリンの分泌を促進し、血糖値を下げる効果があることを明らかにした。この栄養成分が脳の中枢に作用し、食欲を抑えることも解明。玄米を食べると、自然に食事の好みが変化し、食べ過ぎを抑えられるという。
玄米を摂取すると、2型糖尿病の発症予防の効果を得られるという研究も報告されている。
玄米食は「完全食」とも言われており、玄米だけでも十分栄養が取れるほどだ。明治時代に、ビタミンB1を含まない精米された白米が普及し、副食を十分に摂らなかったため、「脚気」(かっけ)が流行した。脚気により多くの患者が出て、「国民病」と呼ばれていた。
脚気の原因はビタミンB1の欠乏だ。当時の海軍軍医だった高木兼寛氏が、食事に玄米食を取り入れ、発症数を大きく減らすのに成功したのは有名な話だ。
「もち米玄米」はおいしく、無理なく続けられる

「もち米玄米」で血糖値が低下 コントロールが改善
聖マリアンナ医科大学代謝・内分泌内科は、16人の2型糖尿病患者を対象に、「もち米玄米」を8週間摂取してもらう研究を行った。
「もち米玄米」を摂取することで、24時間平均血糖値および食後血糖値が改善することが明らかになった。
研究チームは、参加者を精白米を摂取するグループと、「もち米玄米」を摂取するグループに無作為に分けた。
その結果、「もち米玄米」を摂取したグループでは、HbA1cが7.5%から7.2%に改善した。食後30分の血糖値も、193.8mg/dLから172.3mg/dLに改善。
インスリンの分泌の程度を示すCペプチドの曲線下面積の増加分(incremental AUC)も、31.3ng/ml・minから22.1ng/ml・minに改善した。
2型糖尿病患者30人を対象とした別の試験では、「もち米玄米」は24時間の日内血糖変動も改善することが判明。
嗜好性に関するアンケートを行った結果、おいしさを示すスコアは、白米、玄米と比べ「もち米玄米」が最高値を示した。
「もち米玄米は血糖日内変動や食後の血糖値を改善することが明らかになった。食感についても患者の受け入れも良く、長期の継続も可能」と、研究者は述べている。
「もち米玄米」は、玄米よりも食べやすく、血糖値が上がりにくくなり、糖尿病の改善に効果がある。ぜひ「もち米玄米」を試してみてはいかがだろう。
第60回日本糖尿病学会年次学術集会White rice, brown rice, and risk of type 2 diabetes in US men and women(Archives of Internal Medicine 2010年9月13日)
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2026 SOSHINSHA All Rights Reserved.


「地域保健」に関するニュース
- 2025年08月21日
- 令和7年(1月~7月)の自殺者は11,143人 前年同期比で約10%減少(厚生労働省)
- 2025年08月21日
- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告
- 2025年08月13日
-
小規模事業場と地域を支える保健師の役割―地域と職域のはざまをつなぐ支援活動の最前線―
【日本看護協会「産業保健に関わる保健師等の活動実態調査」】〈後編〉 - 2025年08月07日
- 世代別・性別ごとの「総患者数」を比較-「令和5年(2023)の患者調査」の結果より(日本生活習慣病予防協会)
- 2025年08月06日
-
産業保健師の実態と課題が明らかに―メンタルヘルス対応の最前線で奮闘も、非正規・単独配置など構造的課題も―
【日本看護協会「産業保健に関わる保健師等の活動実態調査」】〈前編〉 - 2025年07月28日
- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善
- 2025年07月28日
- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減
- 2025年07月28日
- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由
- 2025年07月28日
- 【妊産婦を支援】妊娠時に頼れる人の数が産後うつを軽減 妊婦を支える社会環境とメンタルヘルスを調査
- 2025年07月22日
- 【大人の食育】企業や食品事業者などの取り組み事例を紹介 官民の連携・協働も必要 大人の食育プラットフォームを立ち上げ