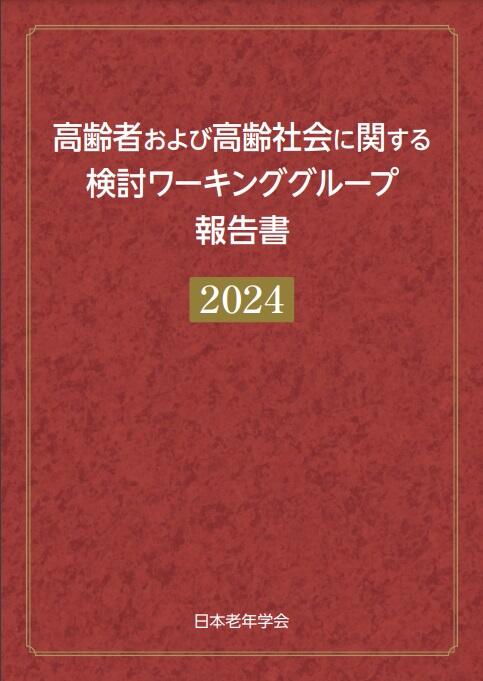老年学など多方面から「高齢者は75歳以上」を検証
『高齢者および高齢社会に関する検討ワーキンググループ報告書2024』より
日本老年医学会は6月13日、『高齢者および高齢社会に関する検討ワーキンググループ報告書2024』を発表した。
同学会および日本老年学会は、2017年に高齢者の定義を「75歳以上」と提言して反響を呼んだが、今回の報告書はそれを医学的な立場から検証してまとめたものである。
2017年に高齢者の定義を「75歳以上」と提言
日本老年学会・日本老年医学会は、2017年3月に『高齢者に関する定義検討ワーキンググループ報告書』を発表し、高齢者の定義を「65歳以上」から「75歳以上」とし、65~74歳を「准高齢者」、90歳以上を「超高齢者」とすべきであると提言した。
その理由として、平均余命が延伸していること、日本人高齢者の若返りが見られること、国民の意識の変化などを挙げていた。
提言から約7年が経過し、その間、新たなエビデンスが蓄積され、日本老年学会の構成学会を中心に、老年学的な見地のみならず、工学的・経済学的見地からも議論を行い、今回の報告書はまとめられた。
ワーキンググループ代表で日本老年学会理事長の荒井秀典氏(国立長寿医療研究センター理事長)は、「年金や定年に関する政府の議論とは無関係であり、今回の報告書ではあくまで医学的な立場から高齢者の定義を検証した」と説明している。
余命を考慮した新たな高齢者基準
国際的にみてみると、国連の報告書『World Population Ageing 2019』では、高齢者の基準を一律65歳として計算する老年人口指数(OADR:Old-Age Dependency Ratio)だけでなく、余命を考慮した新たな高齢者基準の考え方を適用したPOADR(Prospective OADR)を用いた議論が行われている。PODARは、「平均余命が15年と期待される年齢」を老後の始まりとしている。
日本の簡易生命表をもとに平均余命15年の値を算出してみると、2017年:73.5歳、2020年:74.1歳、2021年:73.8歳となり、「2017年に同学会が提言した高齢者定義の75歳以上とほぼ一致している」とされた。

出展:「高齢者および高齢社会に関する検討ワーキンググループ報告書2024」P.15(2024.6)より
本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。