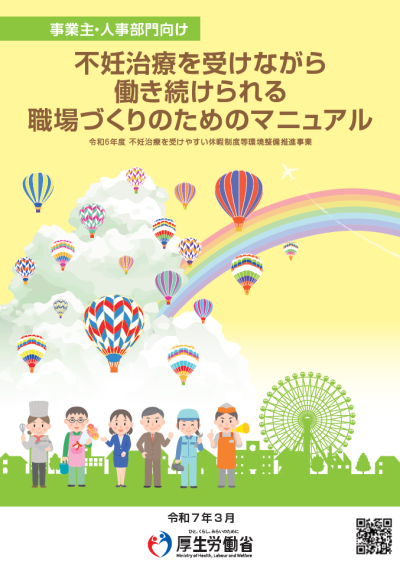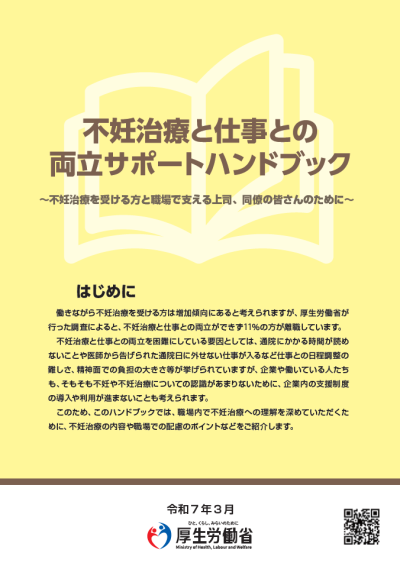不妊治療を受ける人は増加 不妊治療と仕事の両立に理解と支援を-マニュアル・ハンドブックを改訂(厚生労働省)

厚生労働省はこのほど、不妊治療と仕事の両立に対する理解と支援を広げるために作成された「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」と「不妊治療と仕事の両立サポートハンドブック」の2冊を最新版にアップデートした。
不妊治療を受ける人が増加する中、治療を受けながら働き続けられる職場となるよう、意識改革や環境整備を促すのが目的。いずれも厚労省のHPで閲覧できる。
令和5年度厚生労働省「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査」によると、不妊治療をしたことがある人のうち、不妊治療と仕事の両立ができずに仕事を辞めた人は10.9%。そのほかにも「両立できず不妊治療をやめた」が7.8%、「両立できず雇用形態を変えた」が7.4%だった。不妊治療と仕事の両立が困難な現状がうかがえる。
こうした当事者の現状を企業が適切に把握し、十分な支援やサポートを行うには、さらなる啓発が求められる。そのため、厚生労働省は事業主や人事部門向けに「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」を作成。
不妊治療と仕事を両立できる職場づくりによって、離職防止や新たな人材確保といった企業側のメリットにつながる点を伝えながら、支援制度の導入ステップなどを解説している。また、不妊治療と仕事の両立に取り組んでいる企業の事例を25社紹介し、参考にしやすい工夫を凝らしている。
「不妊治療と仕事の両立サポートハンドブック」は、同じ職場で働く上司や同僚向けに作成された。不妊治療への理解を深めてもらうことを目的に、不妊治療の概要や職場で配慮すべきポイントなどをまとめている。
たとえば「データでみる不妊治療と仕事との両立」として、グラフや図表を多用し、最近の調査結果をもとに不妊治療の実態を解説。2021年の調査結果では、夫婦全体の約4.4組に1組(22.7%)が実際に不妊の検査や治療を受けたことがある(または現在受けている)と回答している。4割近い夫婦が「不妊を心配したことがある」とも答えており、いずれの割合も年々上昇している。
しかし前述のとおり、不妊治療と仕事の両立が「できていない」と回答した人は4人に1人以上にのぼる。
両立できずに仕事や不妊治療をやめた、または雇用形態を変更した理由としては、「待ち時間など通院にかかる時間が読めない」「医師から告げられた通院日に外せない仕事が入るなど、仕事の日程調整が難しい」(49.3%)、「精神的な負担が大きい」(44.8%)、「体調・体力面での負担が大きい」(40.3%)といった回答が多かった(複数回答)。
背景には、不妊治療中の社員が利用できる支援制度を導入している企業が、全体の4分の1(26.5%)にとどまっているという現実がある。うち「制度化して実施している」企業は10.6%にすぎない。
一方で、不妊治療を受けていることを職場に「一切伝えていない(伝える予定がない)」人は47.1%と、半数近くを占める。職場で伝えない理由としては、「伝えなくても支障がない」が最も多かったが、「周囲に気遣いをしてほしくない」「不妊治療がうまくいかなかったときに職場に居づらい」「不妊治療をしていることを知られたくない」といった理由も一定数を占めていた。
こうした結果から、不妊治療がいかにデリケートな問題であるかがうかがえる。そのため、本人から相談や報告があった場合でも、プライバシー保護には十分な配慮が必要だ。ハンドブックでは、「上司(管理職)編」「同僚編(職場全体で配慮すべきこと)」の2部構成で、具体的な配慮のポイントをまとめている。
不妊治療を受けながら安心して働き続けられる職場環境の整備が求められる中、厚生労働省はWebページ「不妊治療と仕事との両立のために」を設けている。
令和4年4月からは、不妊治療と仕事の両立がしやすい環境整備に取り組む企業を認定する「くるみんプラス」などの制度を新設。その紹介のほか、研修会・セミナーのお知らせ、マニュアルや助成金に関する情報を集約している。
厚生労働省は今後も、マニュアルやハンドブックの周知、各種情報提供を通じて、職場での理解促進と事業主による取り組みの促進を図り、不妊治療と仕事が両立できる職場環境の整備を進めていく。
不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック(厚生労働省/2025年3月) 不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル(厚生労働省/2025年3月) 不妊治療と仕事との両立のために(厚生労働省)本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。