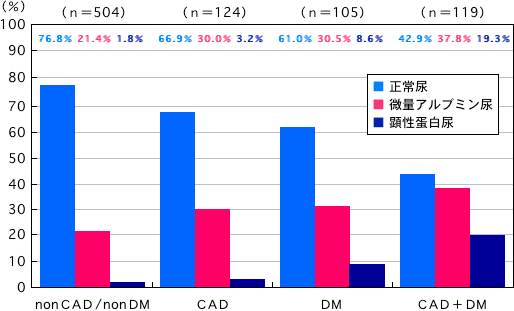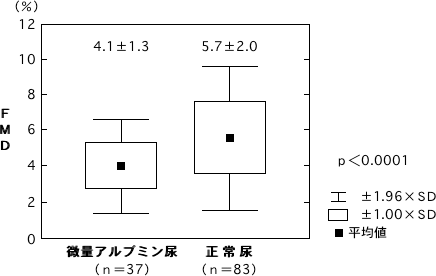ニュース
CADでは非糖尿病でも微量アルブミン尿出現率が高く、FMD低下と関連
2013年05月08日
尿中アルブミン定量検査は保険診療上、糖尿病腎症の場合でのみ算定が認められているが、冠動脈疾患患者では非糖尿病であっても糖尿病患者と同程度の微量アルブミン尿発現率を示すこと、また、微量アルブミン尿の存在はFMDで評価した血管内皮機能の低下と関連があることが、第110回日本内科学会講演会(4月12~14日、東京)で報告された。香川井下病院内科の松村憲太郎氏、井下謙司氏の発表。
冠動脈疾患と糖尿病の有無で4群に分け、微量アルブミン尿やFMDを検討
研究の対象は、同院の午前の外来患者のうち、空腹時尿中アルブミン定量検査を実施した852名(男性389名、女性463名、平均年齢73±12歳)。透析患者、ネフローゼ症候群、急性腎不全、急性感染症、脳血管性認知症、意識障害症例は除外した。
この対象を、冠動脈疾患・糖尿病のいずれもない「nonCAD/nonDM群」504名、冠動脈疾患のみの「CAD群」124名、糖尿病のみの「DM群」105名、冠動脈疾患と糖尿病のある「CAD+DM群」119名の4群に分け、微量アルブミン尿の出現頻度、血管内皮機能等を検討した。
なお、尿中アルブミンは、0~29mg/g・Crを正常(585名、69%)、30~299mg/g・Crを微量アルブミン尿(222名、26%)、300mg/g・Cr以上を顕性蛋白尿(45名、5%)とした。また血管内皮機能は、前腕を5分間駆血し駆血解除後の血流依存性血管拡張反応(Flow Mediated Dilation,FMD)により評価した。
CAD群の微量アルブミン尿出現頻度はDM群とほぼ同等
結果だが、まず、尿中アルブミン≧30mg/g・Cr以上(微量アルブミン尿+顕性蛋白尿)の頻度を各群ごとにみると、nonCAD/nonDM群23.2%、CAD群33.1%、DM群39.0%、CAD+DM群57.1%の順に高かった。これを、顕性蛋白尿を除外し微量アルブミン尿のみで比較すると、同順に、21.4%、30.0%、30.5%、37.8%となり、CAD群でもDM群とほぼ同等の微量アルブミン尿出現率が示された(図1)。冠動脈疾患患者では糖尿病の有無にかかわらず尿中アルブミンを測定する必要性が示唆される。
|
なお、顕性アルブミン尿を除外した上で4群の患者背景を比較し、有意な群間差がみられた因子を挙げると、CAD群およびCAD+DM群において男性の比率と年齢が他の2群より高く、HDL-Cが低かった。また、DM群およびCAD+DM群はTGが他の2群より高かった。CAD+DM群では心拍数、収縮期血圧が他の3群より高く、eGFRが低かった。BNPはnonCAD/nonDM群のみ他の3群より低値だった。
微量アルブミンを呈するCAD患者の内皮機能は、正常尿CAD患者より有意に低下
次にFMDによる血管内皮機能の検討結果をみると、正常尿症例(n=466)の6.1±3.5%に対して微量アルブミン尿症例(n=173)は5.4±3.1%で、有意に低下していた(p=0.0185)。
続いて、先に示した4群でFMDを比較すると(顕性蛋白尿症例は除外)、nonCAD/nonDM群6.2±3.5%、CAD群5.1±3.0%、DM群5.9±3.0%、CAD+DM群5.0±3.0%で、CAD群およびCAD+DM群はnonCAD/nonDM群に比し有意に低値だった(それぞれp=0.0036,p=0.0055)。
さらにCAD群を微量アルブミン尿と正常尿に二分しFMDを比較すると、微量アルブミン尿例(n=37)のFMDは4.1±1.3%で正常尿例(n=83)の5.7±2.0に比べて有意に低く(p<0.0001)、冠動脈疾患患者においても微量アルブミン尿を有する場合は血管内皮機能がより高度に障害されている可能性が示された(図2)。
|
本研究の結語として松村氏は「糖尿病のない冠動脈患者の微量アルブミン尿発現率は糖尿病患者と同程度で、冠動脈疾患患者における潜在的腎症の合併が示唆される。また、微量アルブミン尿の存在は血管内皮機能障害を反映し、微量アルブミン尿を呈する冠動脈疾患患者の血管内皮機能(FMD)は低下している」とまとめた。
◇FMD関連情報(糖尿病ネットワーク):
- ■CADでは非糖尿病でも微量アルブミン尿出現率が高く、FMD低下と関連
- ■上腕動脈IMT・FMDの同時計測で、冠動脈疾患リスクの層別化が可能
- ■DPP-4阻害薬の食後高脂血症改善を介した血管内皮保護作用
- ■禁煙により酸化ストレスが低下し、血管内皮機能が有意に改善
- ■糖尿病細小血管障害とFMD値が相関。短期加療による改善も評価可能
- ■血管内皮機能は体温日内変動と相関するが、糖尿病ではその関係が破綻
- ■心不全患者の心リハ。急性期のADL改善にも血管内皮機能が関与
- ■糖尿病患者の冠疾患スクリーニングにFMDが有用
- ■食事由来コレステロールよりはTGとアポB48が血管内皮機能に影響
- ■直接レニン阻害薬の多面的効果 透析患者での血管内皮機能を改善
- ■DPP-4阻害薬の変更による血管内皮機能改善の上乗せ効果
- ■塩分の多い食事は、食直後から血管内皮機能(FMD)を低下させる
- ■血管内皮機能は血糖変動と逆相関し鋭敏に変化する
- ■大豆イソフラボンがTGを低下させ、FMDを改善
- ■「血管内皮機能検査」が診療報酬改定で新設される(厚生労働省)
- ■ミグリトールは冠動脈疾患併発糖尿病患者の血管内皮機能を改善する
- ■FMD低値は糖尿病発症の予測因子。ドックなどでは精密検査を
- ■肥満2型糖尿病では、精神的ストレス軽減が血管内皮機能改善につながる
- ■網膜症のある女性糖尿病患者は血管内皮機能(FMD)低下ハイリスク
- ■HDL-Cの血管内皮機能(FMD)保護作用は糖尿病で相殺される
- ■仮面高血圧合併2型糖尿病では血管障害(FMDやPWV)が高度に進展
- ■DPP-4阻害薬は血管内皮機能(FMD)を改善する
- ■脳や心臓の血管が詰まる前に。血管の若返りがわかる検査指標「FMD」
- ■動脈硬化が早期にわかるFMD検査装置
- ■血管内皮機能、FMD検査のユネクス
- ■一般向けサイト 動脈硬化の進展を知る「FMD検査.JP」
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.


「健診・検診」に関するニュース
- 2025年08月21日
- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告
- 2025年07月07日
- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市
- 2025年06月27日
-
2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%
過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日
-
【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ
対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日
- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】
- 2025年05月20日
-
【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築
―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日
- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善
- 2025年05月16日
- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少
- 2025年05月12日
- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要
- 2025年05月01日
- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】