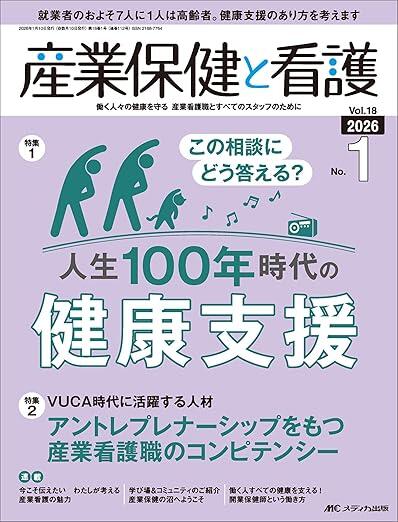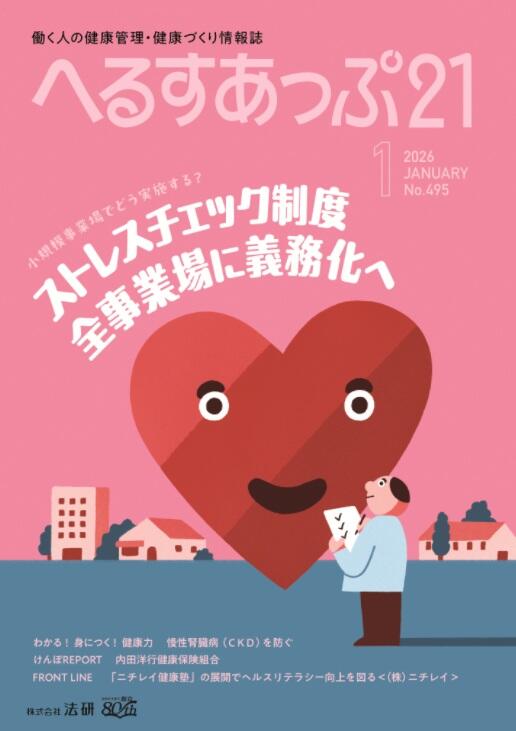ニュース
「慢性疲労症候群」が血液検査で診断可能に バイオマーカーを発見
2016年11月09日

原因不明の疾患である「慢性疲労症候群」のバイオマーカーを発見したと大阪市立大学などの研究チームが発表した。実用化できれば、治療法が確立していない慢性疲労症候群の検査を一般の医療機関でもできるようになり、医療システムの整備につながると期待されている。
慢性疲労症候群でよくみられる症状
「慢性疲労症候群」は、日々の暮らしが困難になるほどの疲労感に突然襲われ、微熱・頭痛・筋肉痛・関節痛・睡眠障害・思考力低下などの症状が、6ヵ月以上続く疾患。人によっては症状が何年も続き、社会生活が困難になる。
聖マリアンナ医科大学・難病治療研究センターが厚生労働省の委託を受けて2014年度に実施した調査では、患者の30%が「身の回りのことができず、常に介助が必要で終日寝たきり」「身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上が寝たきり」と回答した。
現在働いていない人は95%、家事のあとに症状が悪化する人は99%で、少しの活動で体が衰弱し、症状が悪化する状態であることが明らかになった。全国に30万人の患者がいると推定されるが、明確な診断基準がなく、重症患者は通院することすら困難なため、厚労省も正確な患者数をつかんでいない。
通常の診断や従来の医学検査では、慢性疲労症候群に特徴的な身体的異常をみつけることができず、治療法も確立していない。その原因として、ウイルスや細菌の感染、過度のストレスなどの複合的な要因が引き金となり、神経系・免疫系・内分泌代謝系の変調が生じて、脳や神経系が機能障害を起こすためと考えられているが、発症の詳細なメカニズムはわかっていない。
米国疾病予防管理センター(CDC)が1988年に、慢性疲労症候群に関する報告を行って以降、そのメカニズムの解明、バイオマーカーの探索、治療・予防法の開発を目的にさまざまな研究が行われている。これまでに、ウイルスの活性化や自律神経機能異常を指標としたものなどがバイオマーカーとして提案されてきたが、病態のメカニズムに則したものではなかったり、専門医でないと診断が難しいなど問題があった。
バイオマーカーを確立すれば医療施設で診断できるようになる
そのため、慢性疲労症候群の病態メカニズムを反映し一般の医療施設でも診断できるようにするバイオマーカーの確立が望まれていた。そこで大阪市立大学などの研究チームは、慢性疲労症候群の患者の血漿成分中に特徴的な代謝物質があることを、メタボローム解析(代謝物質の網羅的解析)により明らかにした。
これらの代謝物質を詳しく分析した結果、慢性疲労症候群の患者では細胞のエネルギー産生系および尿素回路内の代謝動態に問題があることや、血中の代謝物質の濃度が疲労病態を反映していることが明らかになった。
さらに、代謝物質のうちピルビン酸/イソクエン酸、オルニチン/シトルリンの比が患者では健常者と比べて有意に高いことから、これらが診断に有効なバイオマーカーとなりうることが分かった。
今後は、新たに発見した代謝物質の比により、慢性疲労症候群の患者群と健常者群の判別を、異なる背景(人種など)をもつ集団にも適用できるかを検討するという。また、慢性的な疲労の自覚がある人のサンプルを用いて解析を行い、詳細な疲労病態の解明に向けて、さらに研究を進めるとしている。
慢性疲労症候群の診断バイオマーカーが確立すれば、一般の医療機関でも検査できるようになり、医療システムの構築につながる。また、今回の研究によって判明した代謝病態を改善するような食薬の開発も期待できると、研究グループは述べている。
この研究は、大阪市立大学医学研究科システム神経科学の山野恵美特任助教、理化学研究所ライフサイエンス技術基盤研究センターの渡辺恭良センター長と片岡洋祐チームリーダー、関西福祉科学大学健康福祉学部の倉恒弘彦教授、慶應義塾大学先端生命科学研究所らのグループによるもの。研究成果は、英国のオンライン科学雑誌「Scientific Reports」に発表された。
大阪市立大学大学院医学研究科システム神経科学Index markers of chronic fatigue syndrome with dysfunction of TCA and urea cycles(Scientific Reports 2016年10月11日)
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2026 SOSHINSHA All Rights Reserved.


「健診・検診」に関するニュース
- 2025年08月21日
- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告
- 2025年07月07日
- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市
- 2025年06月27日
-
2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%
過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日
-
【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ
対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日
- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】
- 2025年05月20日
-
【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築
―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日
- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善
- 2025年05月16日
- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少
- 2025年05月12日
- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要
- 2025年05月01日
- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】