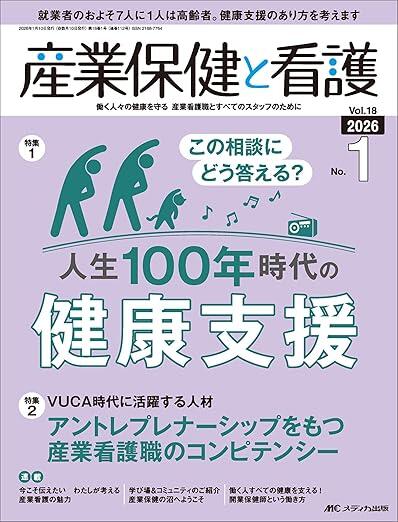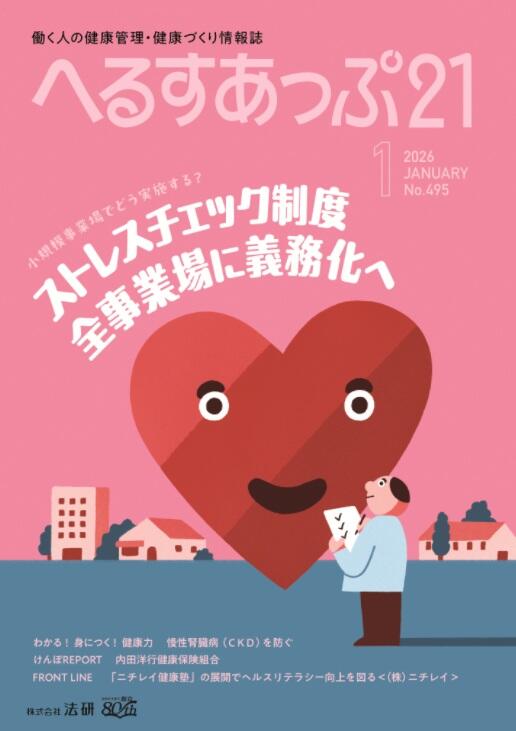ニュース
大気汚染で「胎盤早期剥離」リスクが上昇 大気汚染が母子を危険に
2016年12月15日

妊娠中に胎盤が子宮からはがれてしまう産科救急疾患である「常位胎盤早期剥離」(早剥)と大気汚染は関連があるという研究を、九州大学が発表した。大気汚染物質、二酸化窒素の濃度が上昇すると、早剥のリスクが高まるという。
大気汚染が妊婦とお腹の子どもの健康に影響
大気汚染は、肺がんや心筋梗塞などの原因になるだけでなく、最近の研究では、妊婦が大気汚染に曝露されることで、妊婦自身の健康、お腹の子どもの健康に影響する可能性が指摘されている。
「常位胎盤早期剥離」(早剥)は、通常は子どもが生まれた後に子宮壁からはがれてくるはずの胎盤が、子どもが生まれる前にはがれてきてしまう状態で、発生頻度は全妊婦の0.6%ほどだ。
母体については、出血が多くなったり、胎盤がはがれることが引き金になり、場合によっては「播種性血管内血液凝固症候群」(DIC)(血液が固まりにくくなる状態)になるおそれがある。
胎児については、胎盤を通した酸素・栄養供給が絶たれるおそれがある。母子母児ともに命の危険にさらされる産科救急疾患だ。
いまのところその発生機序ははっきり分かっていないが、もともと形成不全のある胎盤に血流障害や炎症が起こると子宮と胎盤の間に出血が生じて、貯留した血のかたまりによって子宮の壁から胎盤がはがれてくると考えられている。
二酸化窒素濃度が上昇すると早剥が1.4倍に増加
研究グループは、妊婦の大気汚染物質曝露が早剥と関連するのではないかと考え、疫学的に検討した。
具体的には、日本産科婦人科学会(周産期委員会)が実施している周産期登録事業により提供を受けた九州沖縄地域内28病院での2005~2010年のデータから、単胎妊婦(4万7,835人)の中で早剥と診断された821人を対象に、出産した病院に一番近い一般環境大気測定局(24局)で測定された大気汚染物質濃度を解析した。
この研究で評価した大気汚染物質は、二酸化窒素(NO2)、浮遊粒子状物質(SPM)、光化学オキシダント(Ox)と二酸化硫黄(SO2)。
今回の研究で関連を認めたNO2は、燃焼(自動車、工場、ビル、家庭、自然界など)にともない排出される一酸化窒素(NO)が大気中で酸化されて発生する大気汚染物質だ。
大気汚染の影響を受けて胎盤に影響がおよぶまで約1日、早剥発生から出産まで1日以内と見積もり、その前後(出産1~5日前)の大気汚染について、その前後(出産1~5日前)の大気汚染について、特に出産2日前の大気汚染に着目して解析した。
その結果、大気汚染物質の中で二酸化窒素(NO2)が早剥と関連しており、濃度が10ppb上昇すると早剥の発症が1.4倍程度に増加する(95%信頼区間1.1~1.8)ことが明らかになった。
母子の状態によっては、早産にならないように出産を先延ばしにした可能性がある妊娠35週未満の出産例を除いた解析でも、1.4倍(95%信頼区間1.0~2.0)に増加した。
大気汚染と早剥との関連性を示した世界初の研究
まれにゆっくり進行する早剥もあるため、急激に進行して緊急対応したと考えられる緊急帝王切開での出産例にしぼった解析でも、10ppb上昇に対して1.4倍(95%信頼区間1.1~1.9)に上昇した。
母子の状態によっては、早産にならないように出産を先延ばしにした可能性がある妊娠35週未満の出産例を除いた解析でも1.4倍(95%信頼区間1.0~2.0)という結果だった。
今回の研究で使用した周産期登録データは、個人が特定できないように匿名化されており、妊婦の自宅住所情報(里帰り出産の場合の実家情報を含む)がないため、出産した病院の所在地から早剥を起こした妊婦が曝露されていた大気汚染物質濃度を推定した。
そのため、実際にその妊婦が曝露されていた大気汚染物質濃度とは差がある可能性がある。
「今回の報告は世界ではじめてのものであり、今後、早剥の発症予測や予防を目指して、知見の蓄積を進めていく必要がある」と、研究者は述べている。
この研究は、九州大学環境発達医学研究センターの諸隈誠一特任准教授、同大学大学院医学研究院の加藤聖子教授、国立環境研究所環境リスク・健康研究センターの道川武紘主任研究員らの研究グループによるもの。研究は医学誌「Epidemiology」オンライン版に発表された。
九州大学環境発達医学研究センター
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2026 SOSHINSHA All Rights Reserved.


「健診・検診」に関するニュース
- 2025年08月21日
- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告
- 2025年07月07日
- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市
- 2025年06月27日
-
2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%
過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日
-
【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ
対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日
- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】
- 2025年05月20日
-
【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築
―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日
- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善
- 2025年05月16日
- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少
- 2025年05月12日
- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要
- 2025年05月01日
- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】