ニュース
外傷性高次脳機能障害、じん肺、アスベスト関連疾患の研究概要を紹介
2017年02月27日
独立行政法人 労働者健康安全機構は「労災疾病等医学研究普及サイト」のホームページを開設し、研究の概要を紹介している。平成26年度からは労災補償政策上重要なテーマや新たな政策課題など現代社会の状況に対応するため、研究を3領域に集約。このうち「労災保険給付に係る決定等の迅速・適正化」の領域では、「外傷性高次脳機能障害」、「じん肺」、「アスベスト」の3テーマを掲げ、研究が進められている。
「外傷性高次脳機能障害」のテーマでは、通常の画像診断で異常を認めない高次脳機能障害の病態解明と、その労災認定基準に関する研究を行っている。具体的には「real time functional MRI」または「光トポグラフィー」といった経時的脳血流量観察機器で、高次脳機能障害が評価できるかどうかなど。健常者の高次脳機能を経時的な大脳における血流量変化として捉え、さらに同じ検査を高次脳機能障害患者で行うことによって、高次脳機能障害が経時的な脳血流動態の異常として証明できれば、その診断価値は高いとされる。
また「じん肺」のテーマでは、「本邦におけるじん肺における膠原病、腎症特にANCA関連腎疾患の合併頻度に関する調査研究」、「じん肺ハンドブックの作成に関する研究・開発」、「じん肺続発性気管支炎の診断、治療法に関する研究」といった内容で研究が実施されている。
このうちハンドブックについては、既存のハンドブックに追加された石綿関連肺疾患に関する基準や、新たに作成されたデジタル版のじん肺標準写真が掲載されていないこと、また、日本人のデータを基にした呼吸機能障害の判定基準は追録版として別冊子になっていることから、一冊で情報を網羅したものを作成することを目的としており、平成29年に出版予定である。
最後に「アスベスト」のテーマでは、アスベスト関連疾患の研究・開発、普及を目的とし、「石綿肺癌診断における石綿繊維と種類に関する研究」や「石綿肺の適正な診断に関する研究」、「石綿健康管理手帳データベースにおける肺癌、中皮腫等の発生頻度に関する研究」、「中皮腫の的確な診断方法に関する研究―鑑別診断方法と症例収集―」といった研究を行っている。
例えば、石綿ばく露者に悪性腫瘍である肺癌、中皮腫が高頻度に発生することが知られているが、日本において今後どのような頻度でこれらの悪性腫瘍が発生するかの予測はなされていない。これまでの研究では、石綿健康管理手帳を取得し、定期検診を受診している過去の石綿ばく露労働者に肺癌発生頻度が高いことが報告されてきた。そこで今年度は昨年度までにデータベース化した4,057例(男性3,910例・女性147例)について、肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚例がどのような頻度で発生するかについて研究が進められている。
各テーマの研究概要については、ホームページに詳しい研究計画書を掲載。関連する情報と合わせて閲覧できる。
労災疾病等医学研究普及サイト(独立行政法人労働者健康安全機構)「外傷性高次脳機能障害」
「じん肺」
「アスベスト」 関連する法律・制度を確認 >>保健指導アトラス【産業保健】
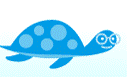 >>保健指導アトラス【じん肺法】
>>保健指導アトラス【じん肺法】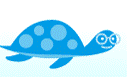
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.


「産業保健」に関するニュース
- 2025年08月21日
- 令和7年(1月~7月)の自殺者は11,143人 前年同期比で約10%減少(厚生労働省)
- 2025年08月21日
- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告
- 2025年08月20日
- 育休を「取りたい」若者は7割超 仕事と育児との両立で不安も 共に育てる社会の実現を目指す(厚生労働省)
- 2025年08月13日
-
小規模事業場と地域を支える保健師の役割―地域と職域のはざまをつなぐ支援活動の最前線―
【日本看護協会「産業保健に関わる保健師等の活動実態調査」】〈後編〉 - 2025年08月07日
- 世代別・性別ごとの「総患者数」を比較-「令和5年(2023)の患者調査」の結果より(日本生活習慣病予防協会)
- 2025年08月06日
-
産業保健師の実態と課題が明らかに―メンタルヘルス対応の最前線で奮闘も、非正規・単独配置など構造的課題も―
【日本看護協会「産業保健に関わる保健師等の活動実態調査」】〈前編〉 - 2025年08月05日
-
【インタビュー】2週間のデトックスで生産性が変わる?
大塚製薬の『アルコールチャレンジ』に学ぶ健康経営 - 2025年07月28日
- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善
- 2025年07月28日
- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減
- 2025年07月28日
- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由




















