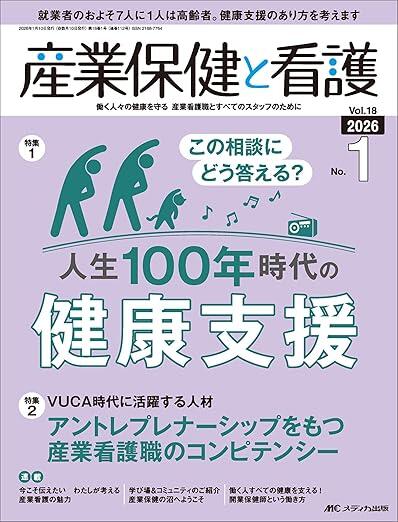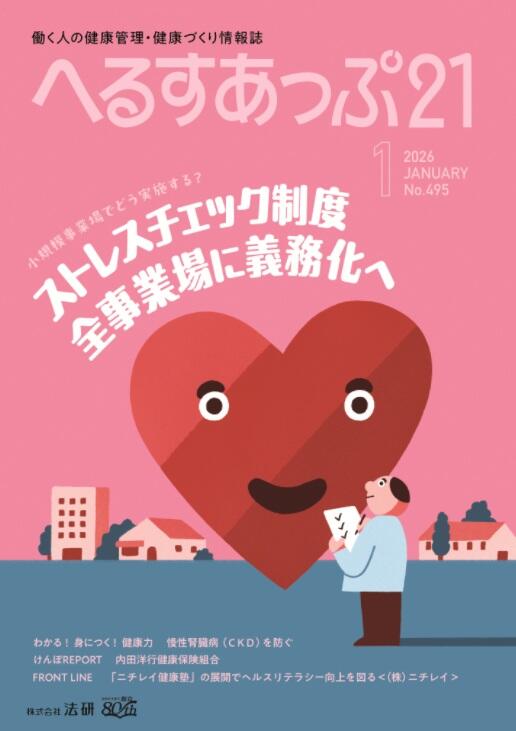ニュース
介護食品は「スマイルケア食」へ 「摂食・嚥下リハビリ」マップも公開
2017年03月23日

農林水産省が、介護食品を新たな視点で見直した「スマイルケア食」の普及を図っている。一方で、食物をうまくのみ込めなくなる「摂食嚥下障害」の患者へのリハビリの促進も求められている。
スマイルケア食 介護食品を新たな視点で
「スマイルケア食」は、農林水産省が2014年11月に発表した、「介護食品」を新たな視点でとらえ直した食品。噛むこと、飲み込むことが難しい人のための食品だけでなく、低栄養の予防につながる食品、生活をより快適にする食品という広い領域としてとらえたものだ。同省は、小売店などで商品を選択する際に活用できる早見表も策定した。
加齢や体の障害のために噛む力や飲み込む力が弱くなると、食べることの楽しさが失われていくことがある。噛む力が弱いために、噛みにくい肉や繊維質の多い野菜を避けてしまったり、飲み込む力が弱いために、食品がのどにつかえたりむせてしまい、食べることが難しくなってしまうことがある。その結果、食べられる食品が偏ったり、食べる量が減ってしまうおそれがある。
また、低栄養はサルコペニア(加齢に伴う筋力の減少、または老化に伴う筋肉量の減少)とも関連が深い。筋力低下・身体機能低下が引き起こされると、活動の程度や消費エネルギー量の減少、食欲低下につながり、さらに栄養不良の状態を促進させるという悪循環のサイクルに陥りやすくなる。

「自分の口で食べる」ことが重要
国立長寿医療研究センターが、在宅療養患者の高齢者を対象に2012年に行った調査によれば、「低栄養」の人が37.4%もおり、さらに「低栄養のおそれあり」も加えた割合は、約7割に上る。低栄養は介護が必要な状態につながりやすい。
健康を保って自立した生活をするためには、「自分の口で食べる」こと、必要な栄養素をきちんと摂ることが重要だ。介護が必要になった場合でもそれは同じで、できるだけ自分の口で食べることが健康の維持につながる。
そこで農林水産省は「スマイルケア食」を、噛むことや飲み込むことなどの食べる機能が弱くなった人、低栄養の人、介護が必要な人などが、自分で食べる喜びを感じながら、必要な栄養素も摂れる食品として考案した。
「青」「黄」「赤」で色分け
「スマイルケア食」では、消費者が状態にあった物を選べるよう、栄養状態が良くない人向けは「青」、かむことが難しい人向けは「黄」、のみ込むことが難しい人向けは「赤」のマークが設けられた。
「青」では、噛むこと・飲み込むことに問題はないものの、健康維持上栄養補給を必要とする人向けの食品として自己適合宣言を認めた。「黄」は噛む力に配慮した食品の日本農林規格(JAS)の取得を、「赤」は嚥下困難な人向け食品を対象に規格を設けた消費者庁の許可制度「特別用途食品」をそれぞれ条件とし、他規格と連動したマークの周知と普及を進めていく方針だ。

農水省の後押しで普及加速へ
製品化されたスマイルケア食の例を挙げると、やわらかいご飯やおかゆ、雑炊、リゾットなどの主食、肉じゃが、焼き魚といった和風の料理から、ハンバーグ、グラタンといった洋風の料理、麻婆豆腐やエビチリといった中華風の料理まで幅広くそろった主菜、煮豆やスープ、漬物などの副菜、ゼリーやプリン、果物などのデザートなど、さまざまなメニューが開発されている。
高齢者の加齢に伴う味覚の変化に対応して、塩分を抑えながらもしっかりと味を感じられるように工夫したものがある。これらは、レトルト食品や冷凍食品などの形態で製品化されており、介護・福祉施設や配食サービス向けの業務用製品のほか、家庭用製品のラインナップも広がってきた。

「摂食・嚥下リハビリ」でQOLを高める
摂食・嚥下障害は、高齢社会の到来とともに大きな問題になりつつある。原因としては、脳卒中、認知症やパーキンソン病などの神経や筋肉の病気、あるいは舌・咽頭・喉頭がんなどがある。
摂食・嚥下リハビリは、栄養摂取の方法を確立することを目指し、食事や栄養摂取のスタイルを確立することが目標となる。
食品を飲み込む時は、気道の入り口である喉頭蓋などが閉じて、飲食物は食道へ送られる。しかし、この動きがうまくいかないと、飲食物が誤って気道に入る「誤嚥」が起こりやすい。
嚥下障害があると、食品や飲料などをうまく飲み込めなくなるだけではなく、誤嚥による肺炎(誤嚥性肺炎)や窒息などの問題が起こる。誤嚥を防ぐためには、食事の工夫以外にも、食べるときのケアや口腔ケアが重要だ。そこで「摂食・嚥下リハビリ」が必要となる。
「摂食嚥下関連医療資源マップ」を公開

業務主任者:戸原 玄(東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野、歯科医師) 関連する法律・制度を確認 >>保健指導アトラス【高齢者の医療の確保に関する法律(老人保健法)】
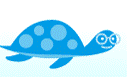
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2026 SOSHINSHA All Rights Reserved.


「栄養」に関するニュース
- 2025年08月21日
- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告
- 2025年07月28日
- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減
- 2025年07月22日
- 【大人の食育】企業や食品事業者などの取り組み事例を紹介 官民の連携・協働も必要 大人の食育プラットフォームを立ち上げ
- 2025年07月18日
- 日本人労働者の3人に1人が仕事に影響する健康問題を経験 腰痛やメンタルヘルスなどが要因 働きながら生産性低下を防ぐ対策が必要
- 2025年07月18日
- 「サルコペニア」のリスクは40代から上昇 4つの方法で予防・改善 筋肉の減少を簡単に知る方法も
- 2025年07月14日
- 適度なアルコール摂取は健康的? 大量飲酒の習慣は悪影響をもたらす お酒との良い関係
- 2025年07月14日
- 【コーヒーと健康の最新情報】コーヒーを飲んでいる人はフレイルや死亡のリスクが低い 女性では健康的な老化につながる
- 2025年07月08日
- 「大人の食育」を強化 人生100年時代の食育には地域や職場との連携も必要-令和6年度「食育白書」より
- 2025年07月07日
- 日本の働く人のメンタルヘルス不調による経済的な損失は年間7.6兆円に 企業や行政による働く人への健康支援が必要
- 2025年07月07日
- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市