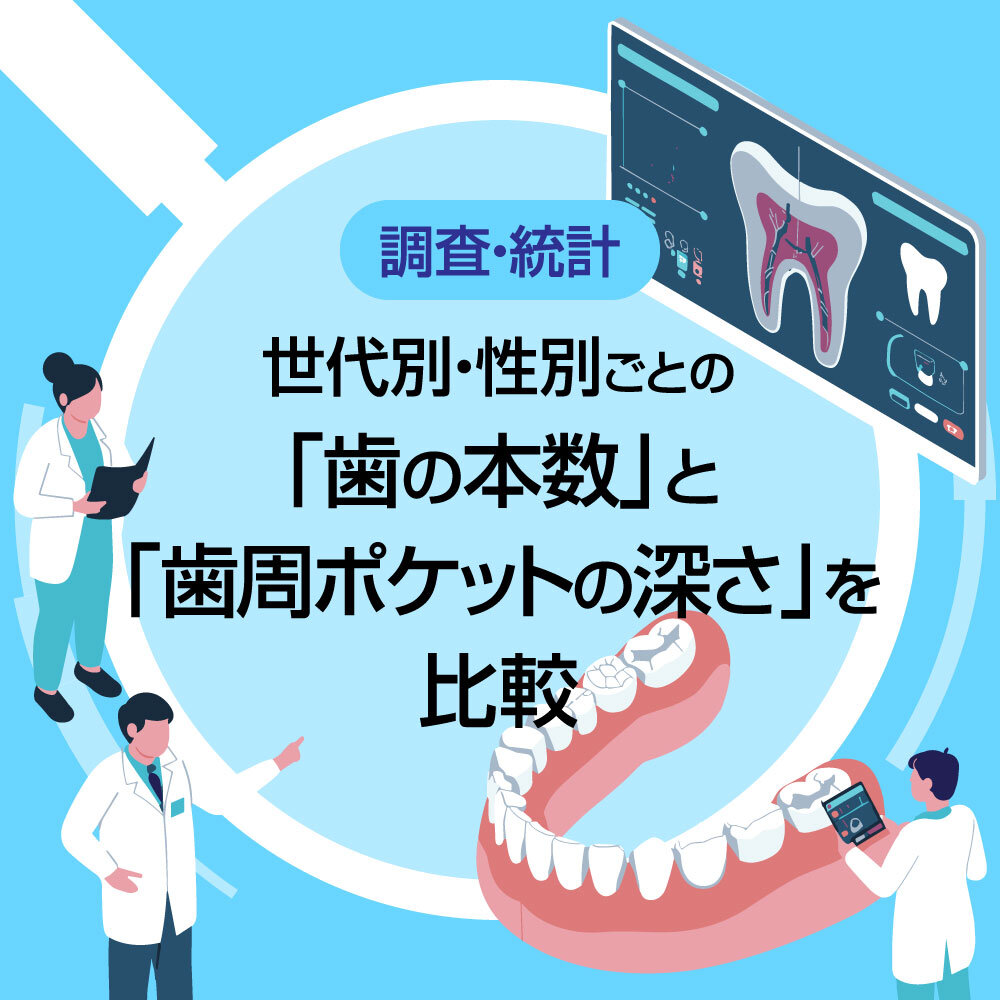ニュース
高血圧・高血糖・高血中脂質 3つが連鎖する「トリプルリスク」の危険性
2018年03月07日

「高血圧」「高血糖」「高血中脂質」の3つが連鎖する「トリプルリスク」。1つだけ数値が高いだけでも危険だが、2つ3つと要因が重なるとさらに危険性が増し、動脈硬化が進行しやすくなる。「トリプルリスクを考える会」は、「トリプルリスク」への注意を喚起する活動を展開している。
1つが該当すると他の2つも悪くなる可能性が
「メタボリックシンドローム」(メタボ)が提唱されてから10年以上経ったが、生活習慣病の患者数は「高血圧」1,011万人、「糖尿病」1,000万人、「脂質異常症」206万人と、いまもなお増加している。3つの疾患は、初期の段階では自覚症状が乏しく、検査を受けないと体の状態が分かりにくいという共通点がある。
2型糖尿病などの生活習慣病により動脈硬化が進行すると、心疾患や脳卒中など命に関わる重篤な病気を発症する危険性が増大する。代表的なリスク要因である「高血圧」「高血糖」「高血中脂質」の1つでも該当すると、他の2つも悪くなる可能性があるというのが「トリプルリスク」という考え方。1つだけ数値が高いよりも、2つ3つと要因が重なると重篤な疾患を起こすリスクが高くなる。
「トリプルリスクを考える会」は、血圧・血糖・血中脂質の3つを同時にケアする必要性について啓発する活動をしている。同会が30~60歳代の男女1,200人を対象に実施した調査によると、「1つ以上ケアしている」と答えた人は32%と3人に1人だったが、「3つともケアしている」という人はわずか11%だった。
ふだんの食生活について、摂り過ぎを気にしているもののワースト3は「1位 糖分」「2位 塩分」「3位 脂肪分」で、これらの摂り過ぎを1つ以上気にしている人は7割以上に上った。しかし、「3つとも気にしている」という人は47%にとどまった。
メタボは単なる見た目の問題ではない
調査を総評した岡部クリニック院長の岡部正氏は、「健康診断では空腹時など条件が限定されていることもあり、"隠れ高血糖"や"早朝高血圧"、"食後高脂血症"などが発見できない可能性があります。たとえ異常なしと言われても油断せずに血圧・血糖・血中脂質、そしてそれらに影響を及ぼしやすい塩分・糖分・脂肪分の3つを同時にケアすることが大切です」と指摘している。
岡部氏によると、「メタボ(メタボリックシンドローム)=太っていること」と勘違いしている人が多いという。メタボを単なる見た目の問題と安易に捉えるのは危険だ。
「本来、メタボとは、内臓脂肪の蓄積が原因で高血圧・高血糖・高血中脂質などが重なっている状態を指し、心筋梗塞や脳梗塞など重篤な疾患を予防するために定められたものです。見た目はあくまでもひとつの指標に過ぎません。血圧・血糖値・血中脂質の3つのリスク要因について日頃から意識することをお勧めします」とアドバイスしている。

インスリン抵抗性が3つの症状の共通の要因
「トリプルリスクを考える会」が2月に東京で開催したキックオフイベントでは、参画メンバーである岡部氏が「高血圧・高血糖・高血中脂質3つが連鎖するトリプルリスクの危険性」をテーマに講演した。
高血圧・高血糖・高血中脂質の3つの症状には「インスリンの働きが悪くなる」という共通の要因があるという。血糖値を下げるインスリンの働きが悪くなると、それを補うために膵臓で沢山のインスリンが分泌される。その結果、腎臓がナトリウムの再吸収を促進し、血圧が上がる。また、肝臓で中性脂肪の合成が盛んになって血中脂質が増える。
「高血圧・高血糖・高血中脂質のどれか1つの数値が高い、ということは、他の数値にも影響するインスリンの働きが悪くなっている状態(インスリン抵抗性)である可能性が高いのです。メタボや生活習慣病の先にある重篤な疾患を防ぐためには、高血圧・高血糖・高血中脂質の3つを同時にケアする必要があります」と、岡部氏は強調する。
トリプルリスクを回避するための食事
イベントでは続いて、管理栄養士で料理研究家の岩崎啓子氏が講演。トリプルリスクを回避するには、意識的に塩分・糖分・脂肪分を3つ同時にケアする必要がある。副菜を追加するなど、お皿を増やすことで、品目数を増やし全体的にボリュームダウンする工夫が役立つ。単品メニューの場合は、使用する素材品数を増やすことでカバーできるという。
さらに、▽塩・砂糖・塩分をバランス良く使う、3つを摂り過ぎないように注意する、▽調味料はなるべく仕上げに使う、調味料は調理の後半に使った方が味が出やすい、▽素材の味を最大限に活かす、▽風味で料理に変化を加える、お酢・香辛料・ハーブをうまく活用し、酸味・辛味・清涼感をプラスする、▽食感を演出する、異なる複数の食感を加えて、歯ごたえのある食事を心がける――といったことに注意すると健康的な食事になるという。


掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.


「特定保健指導」に関するニュース
- 2025年07月28日
- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善
- 2025年07月28日
- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減
- 2025年07月28日
- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由
- 2025年07月28日
- 【妊産婦を支援】妊娠時に頼れる人の数が産後うつを軽減 妊婦を支える社会環境とメンタルヘルスを調査
- 2025年07月22日
- 【大人の食育】企業や食品事業者などの取り組み事例を紹介 官民の連携・協働も必要 大人の食育プラットフォームを立ち上げ
- 2025年07月22日
- 高齢者の社会参加を促すには「得より損」 ナッジを活用し関心を2倍に引き上げ 低コストで広く展開でき効果も高い 健康長寿医療センター
- 2025年07月18日
- 日本人労働者の3人に1人が仕事に影響する健康問題を経験 腰痛やメンタルヘルスなどが要因 働きながら生産性低下を防ぐ対策が必要
- 2025年07月18日
- 「サルコペニア」のリスクは40代から上昇 4つの方法で予防・改善 筋肉の減少を簡単に知る方法も
- 2025年07月14日
- 適度なアルコール摂取は健康的? 大量飲酒の習慣は悪影響をもたらす お酒との良い関係
- 2025年07月14日
- 暑い夏の運動は涼しい夕方や夜に ウォーキングなどの運動を夜に行うと睡眠の質は低下?