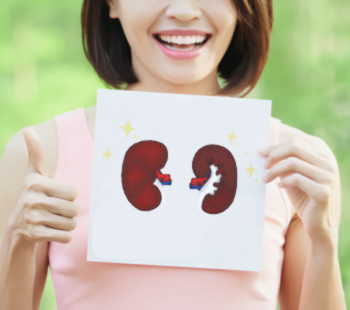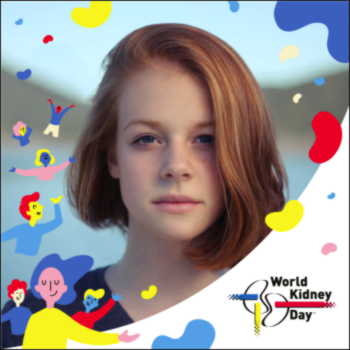3月11日は「世界腎臓デー(World Kidney Day)」だった。世界の成人の10人に1人にあたる8億5,000万人が腎臓病とともに生きている。
腎臓病を予防・改善するための「8つの法則」が公開されている。
腎臓病とともに、より良く生きるために
「世界腎臓デー(World Kidney Day)」は、腎臓病の早期発見と治療の重要性を啓発する国際的な取り組みとして、2006年より国際腎臓学会(ISN)と腎臓財団国際連合(IFKF)により開始された。毎年3月の第2木曜日に実施され、世界各地でイベントが開催されている。
「世界腎臓デー」は、腎臓病の予防・治療、症状管理を改善し、患者の意識を高め、社会参加を促すために実施されている。世界腎臓デー運営委員会は、2021年を「腎臓病とともに、より良く生きる」年と宣言した。
「腎臓病が進行すると、ご自身とご家族の生活、仕事、社会生活、旅行などの日常の活動への参加において、深刻な影響がでてきます。腎臓の働きが低下するまで自覚症状はありませんが、進行すると、だるさ、食欲不振、頭痛、吐き気、むくみ・動悸・息切れ、高血圧、貧血、骨が弱くなる、睡眠障害など、さまざまな症状があらわれるようになります」としている。
腎臓病では糸球体が少しずつ壊れていく。一定程度以上に壊れてしまった糸球体は、正常に戻ることはない。自覚症状のない、いわゆる「隠れ腎臓病」のうちに、早期発見して治療を受けることが重要だ。
透析や移植を受けている患者を含み、腎臓病とともに生きる患者や医療従事者の多くは現在、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により、深刻な打撃を受けている。
成人の10人に1人が腎臓病
腎臓病は早期に発見し治療することで予防・改善が可能だ。この日に「高血圧や糖尿病など、腎臓病のリスクの高い人は、食事や運動などの生活スタイルを見直して、適切な治療を受け、検査を定期的に受けてほしい」と呼びかけられた。
日本を含む世界中で腎臓病は増えている。国際腎臓学会によると、世界の腎臓病の有病者数は8億5,000万人に上り、成人の10人に1人が危険にさらされている。
米国のワシントン大学の研究によると、慢性腎臓病(CKD)により死亡した人は2017年には世界で123万人に上り、腎臓病が原因となった心血管疾患で死亡した人は136万人に上る。透析が必要となった人は1990年から40%以上増えている。
「慢性腎臓病は現在ではありふれていますが、大変に怖い病気です。2017年には世界で死亡者の多い疾患の12位に上昇しました」と、ワシントン大学医学部健康指標評価研究所のテオ ヴォス教授は言う。
日本人の主要な死因でも、腎不全は8位に挙げられている(2019年人口動態調査「年次別にみた死因順位」)。
「予防と治療のための戦略が必要です。適切な治療を行い、透析導入を防いだり遅らせることが、医療費の削減にもつながります。しかし、実際には各国の保健システムは十分な対応をできていません。その結果として多くの方が腎臓病で命を落としています」と、ヴォス教授は言う。
日本人の半数は「慢性腎臓病」を知らない
慢性腎臓病(CKD)は、腎障害を示す所見や腎機能低下が慢性的に続く状態。日本を含む世界中で有病者数が増え続けている。
日本には、慢性腎臓病の人は1,300万人以上いると推測されているが、症状はかなり進行しないとあらわれないため、自覚している人は少ないと考えられている。貧血、疲労感、むくみなどの症状があらわれたときには、病気がかなり進行している可能性がある。
日本腎臓病協会などが2019年に実施した調査によると、日本人の「慢性腎臓病」を知っている人の割合は50.7%で、とくに若年層(20~30歳代)では43.5%と低かった。健康診断を定期的に受けていない人でも認知度は低かった。
「糖尿病や高血圧、高脂血症、肥満症は広く認知されています。慢性腎臓病はこれらの疾患とも関連が深く、20~30歳代といった若年期からの生活習慣が発症に大きく影響しています」と、日本腎臓病協会理事長の柏原直樹氏(川崎医科大学副学長、腎臓・高血圧内科学教授)は述べている。
腎臓を守るためにできること(世界腎臓デー)
腎臓病の検査を受け、早期発見することが大切
腎臓は血液中の不要なものをろ過して尿を作る。腎臓の働きが低下してくると、血液中に不要なものが溜まったり、逆に必要なものが尿に混ざって出てしまう。
タンパクは体にとって必要な構成成分なので、健康であれば尿にはほとんど混ざらない。しかし腎臓の働きが低下すると、ろ過機能をもつ糸球体をタンパクが通過して尿に出るようになる。
健康診断などの血液検査では、「タンパク尿」とともに「クレアチニン」が調べられることが多い。クレアチニンは筋肉で作られる老廃物で、腎臓が正常なら尿に出るが、腎臓の働きが低下すると血液にとどまる量が増える。血液中のクレアチニン値が高い場合は、腎臓の働きが悪くなっているとみられる。
また、腎臓の機能低下は血圧を上昇させる。血圧が高いと糸球体内部の細い血管が傷めつけられる。さらに、糖尿病も腎臓の働きを低下させる原因になる。血糖値が高い状態が続くと、血管が傷みやすくなり、腎臓の働きが低下していく。糖尿病性腎症は、透析療法が必要になる原因の第1位だ。
糖尿病が原因の腎臓病(糖尿病性腎症)では、タンパク尿やクレアチニンの検査だけでは早期発見ができない。多量のタンパク尿が検出される以前から糸球体が壊れはじめることが多いからだ。
そこで「微量アルブミン尿検査」が行われる。糖尿病性腎症の初期にタンパクのひとつであるアルブミンがごく微量、尿にもれるため、それを調べるものだ。
腎臓病を予防・改善するための「8つの法則」
世界腎臓デーには、腎臓病を予防・改善するための「8つの法則」が提案された。
腎臓病は、自覚症状が乏しいうちに病状が進展していく「サイレントキラー」だ。進展すると、生活の質(QOL)が大きく損なわれる。しかし、腎臓病を予防・改善するために、いくつかの方法がある。
腎臓病を防ぐためになによりも大切なのは、血圧値と血糖値、コレステロール値を良好にコントロールすること。これらが高い状態が長く続くと、心臓に酸素や栄養を供給している冠状動脈の内皮が傷つきやすくなり、同時に腎臓の血管も損傷を受けることになる。
1 生活スタイルをアクティブに
健康的な体重を維持し、血圧を下げ、血糖値を下げることは、慢性腎臓病のリスクを減らすのに役立つ。
2 健康的な食事をする
健康的な食事は、健康的な体重を維持し、血圧を下げ、糖尿病や心臓病など、慢性腎臓病のリスクとなる病気を予防・改善するために必須だ。
塩分摂取量を減らすために(1日に5〜6gが目標)、加工食品やレストランを利用するときは、栄養成分表示も見るようにする。食事のときは、なるべく新鮮な食材を使うようにし、食品になるべく塩を加えない。
3 血糖値をはかり、コントロールする
血糖値が高くなっており、糖尿病である危険性があっても、世界の半数がそのことに気が付いていない。中年以上になったら、健康診査を毎年受けて、血糖もチェックしよう。
糖尿病とともに生きる人の半数に、腎機能障害の危機があるという報告がある。しかし、良好な血糖コントロールを維持し、糖尿病の治療を続けていれば、腎臓病を予防・改善できることも分かっている。糖尿病の人は、医療機関への通院を続け、血液検査と尿検査で腎機能を定期的にチェックしよう。
4 血圧をチェックして、管理する
世界の高血圧の人の半数は、自分が高血圧であることを知らない。高血圧は腎臓にダメージを与える原因になり、これに高血糖、高コレステロールが重なると、腎臓はさらにいたみやすくなる。
血圧は家庭用の血圧計でもはかれる。中年以上になったら、血圧をはかることも習慣にしたい。
もしも血圧が持続的に正常範囲を超えて高い状態になっていたら、食事や運動などの生活スタイルを見直すとともに、医師に相談したうえで、必要に応じて薬物療法を受けることが勧められる。
5 適切な水分補給をする
水をたくさん飲んでも、慢性腎臓病は治らないが、脱水状態になると腎機能は低下するので、適度な水分補給は必要だ。とくに気温が上昇する時期には、水分を小まめに補給するようにしよう。
ただし、心不全やむくみのある人、慢性腎臓病が進展している人は、水をたくさん飲むことを避ける必要が出てくる。かかりつけの医師に、ご自分の体の状態に適した水分摂取量について相談しよう。
6 喫煙をしない
喫煙は腎臓への血流を悪くする。腎臓にいきわたる血液が少なくなると、腎臓が正常に機能する能力が低下する。喫煙は、腎臓がんのリスクも50%上昇させる。
タバコを吸う人は、いますぐ禁煙を試みて、吸わない人も、他人が吐き出したタバコの煙を吸わないようにしよう。
7 腎臓の検査を定期的に受ける
下記のような腎臓病のリスク因子が1つでもある場合は、検査を定期的に受け、腎機能をチェックすることが大切だ。
▼糖尿病がある、▼高血圧がある、▼肥満がある、▼腎臓病の家族歴がある(遺伝因子がある)。
8 抗炎症/鎮痛剤に注意
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)や一部の鎮痛剤は、定期的に服用すると腎臓に害を及ぼす可能性がある。こうした薬は、腎臓病や腎機能の低下した人には害を及ぼすおそれがある。
疑わしい場合は、かかりつけの医師や薬剤師に確認しよう。
世界腎臓病デー
NPO法人 日本腎臓病協会