働く女性の健康管理に役立つIoTおよびアプリの利用に課題-東大ら研究グループが指摘
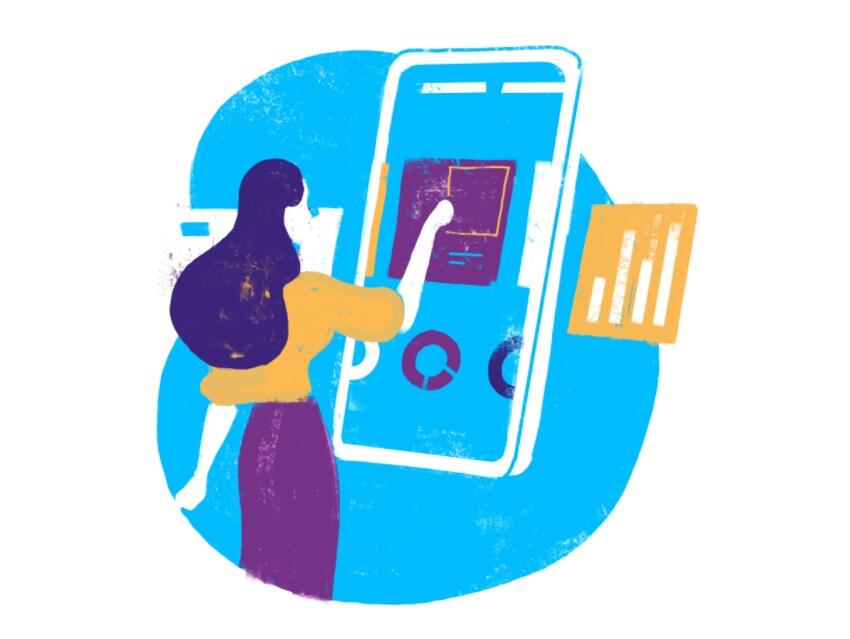
東京大学大学院新領域創成科学研究科の齋藤英子准教授と、聖路加国際大学大学院看護学研究科の大田えりか教授らによる研究グループはこのほど、日本人女性1万人を対象にアンケート調査を実施した。
調査結果から、働く女性の健康管理を目的としたIoTおよびアプリの利用実態が明らかになった。
全国の20歳から64歳の女性1万人を対象にしたインターネット調査の結果をまとめたもの。国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)のヘルスケア社会実装基盤整備事業の支援を受けて実施した。
結果によると、健康管理のためにIoTやアプリを積極的に利用している人は1455人(14.6%)、過去に利用していた人は695人(7.0%)だったが、7850人(78.5%)は利用経験がないと回答した。
IoTやアプリを積極的に利用している1455人のうち、やせ・肥満・むくみ・ダイエットや栄養障害の症状を抱えているのは249人(17.1%)。実際にこれらの症状を改善するIoTやアプリを利用している、と答えた人は405人(27.8%)だった。
一方、同様に積極的に利用している人の中で、月経関連の症状や疾患を抱えている人は401人(27.6%)、PMS(月経前症候群)は356人(24.5%)。
しかし月経関連の症状や疾病を改善するためにIoTやアプリを利用している、と答えた人は249人(17.1%)、PMSは173人(11.9%)にとどまった。
これらのことから、女性特有の健康問題の認識と、IoT やアプリの利用目的には乖離があることが分かる。
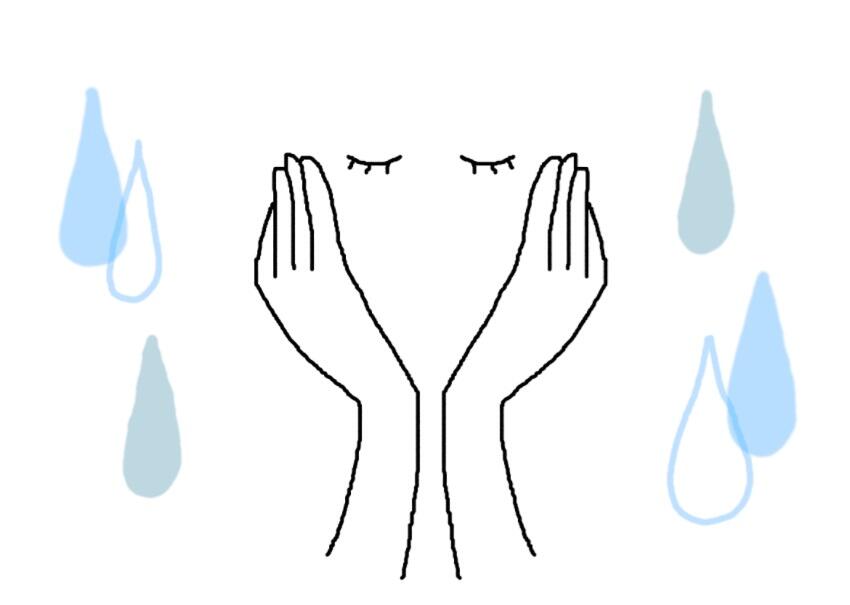
さらに「女性の健康をサポートするフェムテック機器(女性特有の健康課題をテクノロジーで解決することを試みる商品やサービス)が開発されたとしても、その機能を表示するためには、医療機器として承認を受ける必要がある」点も課題としてあげた。
一方、女性特有のデリケートな問題も含むため「データ利用においてはIoTやアプリにおけるプライバシー保護の枠組みを整備していくことが求められる」としている。
働く女性の健康管理を目的としたIoTおよびアプリの利用実態が明らかに-日本人女性1万人にアンケート調査を実施-(東京大学大学院新領域創成科学研究科/2024年8月1日)本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。

