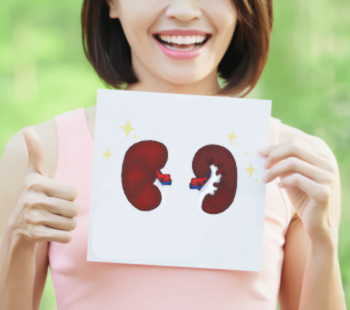日本医療政策機構(HGPI)は、政策提言「労働世代における慢性腎臓病(CKD)対策の強化にむけて~健診スクリーニング、医療機関受診による早期発見、早期介入の重要性~」の公開を開始した。
「患者の生活の質(QO)向上の必要性はさることながら、公的医療負担の抑制の観点からも、糖尿病や高血圧の重症化予防を含むCKDの予防・早期発見・早期介入が強化されるべきです」と強調している。
慢性腎臓病(CKD)は新たな国民病
労働世代に求められる現実的なCKD対策を提言
日本医療政策機構(HGPI)は、政策提言「労働世代における慢性腎臓病(CKD)対策の強化にむけて~健診スクリーニング、医療機関受診による早期発見、早期介入の重要性~」の公開を開始した。
慢性腎臓病(CKD)は、成人の7人に1人が罹患しており、有病者が増加していることから、新たな国民病とされている。初期のCKDは自覚症状がほとんどないが、進行すると腎機能が低下していき、透析や腎移植が必要となることも少なくない。
CKDを発症する背景因子として、糖尿病や高血圧などの生活習慣病が挙げられる。CKDは心筋梗塞などの心血管疾患(CVD)合併の頻度も高く、国民の健康を脅かしている。
同機構は、2022年度に「腎疾患対策推進プロジェクト」を開始し、慢性腎臓病(CKD)の予防と早期介入の必要性、多職種や多機関連携の重要性、自治体の好事例の横展開の必要性、患者・当事者視点にもとづいた腎疾患対策の推進の必要性などを提言してきた。
「CKD対策は、わが国において、関係者の努力により着実な進展をとげ、普及啓発、地域における医療提供体制の整備、診療水準の向上、人材育成、研究開発の推進といった個別施策において、相応の進展がみられています。一方で、透析患者数の増加(新規患者の増加と有病率の上昇)には依然歯止めがかかっておらず、今後とも高齢化の進展がこれを押上げていくことが見込まれています」と、同機構では述べている。
「CKDは労働世代においても無縁ではない疾患です。労働世代のなかにも、CKDのある人、ハイリスクな人、人工透析を受ける人は決して少なくないことから、現状の腎疾患対策の課題を正確に理解したうえで、労働世代に求められる現実的なCKD対策やその範囲を検討していく必要があると認識しています」としている。
「人工透析は、1人あたり年間500万円~600万円を要することから、公的医療費負担の面でも課題となっています。早期のCKDでも、1人あたり年間約3万円~19万円の医療費増加と関連があるとされています」として、「患者の生活の質(QO)向上の必要性はさることながら、公的医療負担の抑制の観点からも、糖尿病や高血圧の重症化予防を含むCKDの予防・早期発見・早期介入が強化されるべきです」と強調している。
そこで、同機構では、労働世代でのCKD対策の強化に向けて、産官学民の有識者へのヒアリングと、これまでの議論を調査し、次の通り提言としてとりまとめた。
主な内容
| 提言 1 労働者の健診でのCKDスクリーニングを強化すべき |
|
- 労働者におけるタンパク尿によるスクリーニングを強化しCKD患者とそのリスク群を早期発見するとともに、糖尿病・高血圧などの基礎疾患のある人への血清クレアチニンの測定にもとづく腎機能評価を徹底すべきである。
- タンパク尿や血清クレアチニンの異常値は個人差があるという特性を考慮しながら、誰がスクリーニングをしても、その個人にとって適切なタイミングで医療へ接続できるような基準を設定するとともに、血清クレアチニンの測定対象の拡大も視野に入れた更なる検討を進めるべきである。
- 健診結果の適切な活用方法を検討し、治療が必要な人が円滑に医療へ接続され、継続的な管理を受けられるように体制を構築していくべきである。
|
| 提言 2 スクリーニングからCKDリスク群への医療受診勧奨、保健指導を強化すべき |
|
- 労働者における経年的な健診データを活用して、事業者、保険者、かかりつけ医が連携して、効果的に医療受診勧奨、保健指導を実施すべきである。
- 労働者の医療受診から治療開始までの確率を上げるため、企業が近隣のクリニックから提携先を選定し、精密検査を行う医師と産業医や企業による円滑な連携体制の構築や、受診した者が確実に治療にたどり着くよう医療者への教育やフォローアップ体制の構築を行うべきである。
- 労働者におけるCKDの実態把握や早期スクリーニングの意義などについて、腎疾患の専門医、疫学や公衆衛生学の専門家と密に連携を取りながら、より強固なエビデンスを確立すべきである。
|