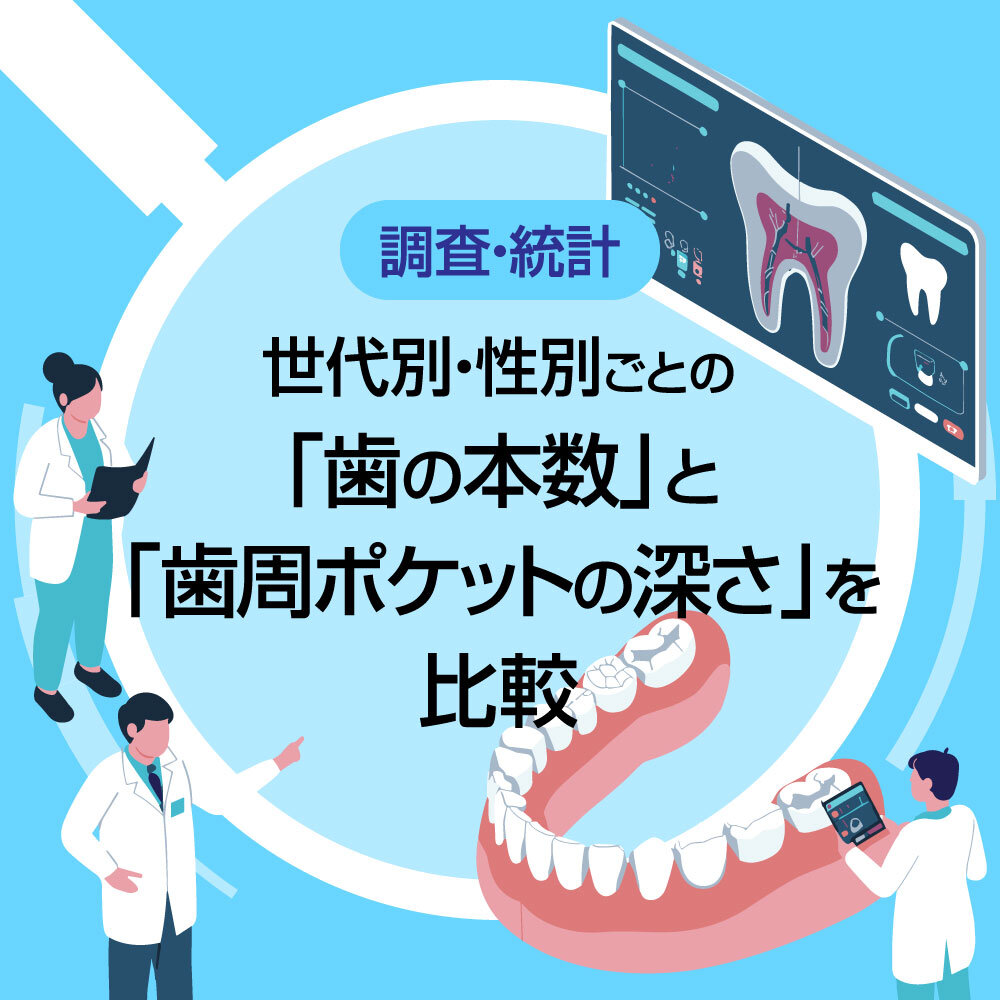ニュース
「バーンアウト」(燃え尽き症候群)を防ぐ対策 仕事と家庭の環境が影響
2015年02月17日

モチベーションを高く保っていた人が突然やる気を失ってしまう「バーンアウト」(燃え尽き症候群)。バーンアウトにならないためには、ストレスと上手に付き合う対策が必要だ。
仕事と家庭の環境がバーンアウトに影響
「バーンアウト」(燃え尽き症候群)は、それまで人一倍活発に仕事をしていた人が、なんらかのきっかけで、あたかも燃え尽きるように活力を失ったときに示す心身の疲労症状をいう。
心身の疲労や消耗感、人と距離をとり感情的接触を避けたり、達成感が低下するなどの症状がみられるときは、バーンアウトが疑われる。エネルギッシュで高い理想をもって仕事に取り組む性格の人に比較的多いとされる。
カナダのモントリオール大学が行った調査で、職場環境に加え、生活環境もバーンアウトに大きく関わっていることが分かった。調査には63の職場から1,954人の従業員が参加した。
研究チームは基礎的な背景となる家庭環境、世帯収入、社会的活動、性別、年齢、自分の現状に対する満足度などについて情報収集を行った。そして、そうした背景と精神的な疲労や不適切なストレス管理との関連を探り、どのような環境がバーンアウトに影響するかを分析した。
その結果、燃え尽きやすい人は一般的に仕事熱心で有能な人が多く、職場環境が大きく影響していることが分かった。職場でサポートを受けやすい人、求める職場のイメージと実際の状態が近い人では、心の問題を抱える割合が低かった。
「仕事が原因で心身の不調を来すケースには、多くの要因が関わっています。上司から依頼される仕事の役割や仕事の量、仕事の進め方の指示や裁量度、仕事のやりがい、上司への相談しやすさ、同僚のサポートや支援の状況、困ったときにプライバシーが守られる相談窓口はあるかといった、多くの要因が関連していると考えるべきです」と、モントリオール大学のスティーブ ハービー教授は述べている。
さらに職場環境に加えて、プライベートな生活環境もメンタルヘルスに強く影響していることが分かった。同居するパートナーがいる人、小さな子供がいる人、世帯収入が高い人、仕事と家庭とのバランスが取りやすい人、社会的なサポートへアクセスしやすい人は、心の健康度が高いと示された。
「メンタルヘルスを考えるときには、プライベートな生活を含め、その人を取り巻く社会全体に目を向けることが大切です」と、ハービー教授は指摘している。
質の良い睡眠と休息をとりバーンアウトに対策
スウェーデンのカロリンスカ研究所の調査によると、「睡眠」と「休息」を適切にとれていない人では、バーンアウトの予兆があらわれやすいという。
調査は、管理職など責任の重い職務に就いている女性146人が参加して行われた。9年間に及ぶ追跡期間中に12.9%の女性がバーンアウトの状態に陥った。
職務上の責任が重い女性ほどバーンアウトの割合が高く、家族や親しい人の死や離別、仕事や健康など大切なものの喪失、人間関係のトラブル、家庭内のトラブル、職場や家庭での役割の変化などの要因も大きく影響することが判明した。
バーンアウトの度合いが高い人では、睡眠障害も多く報告された。睡眠不足から、疲労度も高くなるという悪循環に陥る人も少なくない。睡眠以外でも、休息を適切にとれていないと、メンタルヘルスの問題につながりやすいという。
研究チームでは、睡眠や休息の状況の変化からバーンアウトへの影響を早期に推測して、対処できるのではないかと指摘している。
不規則な生活やストレスが続くと、体の活動時や昼間に活発になる「交感神経」と、安静時や夜に活発になる「副交感神経」のバランスに乱れが生じる。この2つの神経のバランスを整えるのに必要なのが「睡眠」と「休息」なのだ。
例えば、会議で発表をするような場面では、交感神経が優位になり心身のコンディションをアクティブなモードに、反対に、家でくつろいだり眠ったりする場面では副交感神経が優位となり、リラックスしたモードへと切り替わる。
ところが、ストレスが慢性化したりすると、この切り替えが上手くいかず、家に帰っても緊張や興奮が続き不眠などの症状が起こりがちだ。自律神経系を調整し、良好な睡眠や休息する習慣を得るための対策が必要となる。
「仕事に追われた頭と体をより良く休ませるためには、計画的・積極的に休暇をとることも必要です。忙しくストレスの多い生活であればなおさら、心の落ち着きを得られる時間をしっかり確保する必要があります」と研究者は指摘している。
Burnout caused by more than just job stress(モントリオール大学 2014年9月16日)Development of Burnout in Middle-Aged Working Women: A Longitudinal Study(Journal of Women's Health 2013年1月10日)
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.


「地域保健」に関するニュース
- 2025年08月21日
- 令和7年(1月~7月)の自殺者は11,143人 前年同期比で約10%減少(厚生労働省)
- 2025年08月21日
- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告
- 2025年08月13日
-
小規模事業場と地域を支える保健師の役割―地域と職域のはざまをつなぐ支援活動の最前線―
【日本看護協会「産業保健に関わる保健師等の活動実態調査」】〈後編〉 - 2025年08月07日
- 世代別・性別ごとの「総患者数」を比較-「令和5年(2023)の患者調査」の結果より(日本生活習慣病予防協会)
- 2025年08月06日
-
産業保健師の実態と課題が明らかに―メンタルヘルス対応の最前線で奮闘も、非正規・単独配置など構造的課題も―
【日本看護協会「産業保健に関わる保健師等の活動実態調査」】〈前編〉 - 2025年07月28日
- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善
- 2025年07月28日
- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減
- 2025年07月28日
- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由
- 2025年07月28日
- 【妊産婦を支援】妊娠時に頼れる人の数が産後うつを軽減 妊婦を支える社会環境とメンタルヘルスを調査
- 2025年07月22日
- 【大人の食育】企業や食品事業者などの取り組み事例を紹介 官民の連携・協働も必要 大人の食育プラットフォームを立ち上げ