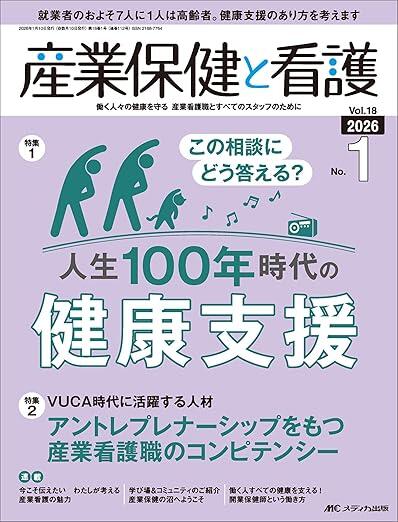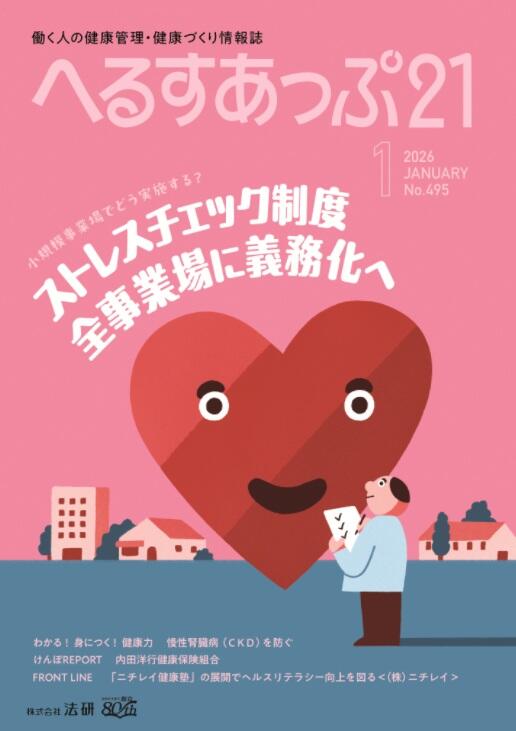ニュース
働く女性の4割が「育児休業を断念」 マタハラに関する意識調査
2015年09月16日

日本労働組合総連合会(連合)は、「マタニティハラスメント(マタハラ)に関する意識調査」の結果を発表した。過去5年間に働きながら妊娠した女性の約40%が、育児休業を取得したくても取れなかったことが判明した。
マタハラを経験した女性は28.6%
調査の対象は、過去5年以内の在職時に妊娠経験がある20~40代の女性654人。働く女性の実態に合わせて、回答者の約4割(261人)を正社員、約6割(393人)を非正規社員の女性としている。年齢分布は30~34歳がもっとも多く32.1%、次いで25~29歳(26.3%)、35~39歳(25.2%)、40~44歳(9.6%)、20~24歳(5.2%)と続く。
「女性が働くことと子育て」について聞いたところ、「働きながら子育てをしたい」と回答した女性は88.3%にのぼり、「仕事をやめて子育てをしたい」7.0%を大きく上回った。
「マタニティハラスメント(マタハラ)」とは、働く女性が妊娠・出産を理由とした解雇・雇止めをされることや、妊娠・出産にあたって職場で受ける精神的・肉体的なハラスメントを意味する。
「マタハラ」という言葉についても尋ねたところ、認知している人は93.6%に上った。実際にマタハラを経験した女性は28.6%で、非正規社員に比べ正社員の方が多く被害に遭っている傾向が示された。
「休業・復帰しやすくなる制度」を求める女性が半数
「仕事をしながら妊娠が分かったときの心境」について尋ねたところ、「嬉しかったが、同じくらい不安を感じた」は40.4%、「嬉しかったが、それ以上に不安を感じた」は9.2%、「不安しか感じなかった」が6.3%。合わせて55.9%が不安を感じており、「嬉しくて素直に喜べた」44.2%を上回った。
マタハラを経験したという人は28.6%に上った。雇用形態別に見ると、正規が34.9%、非正規が24.4%となっている。具体的なマタハラの内容としては「妊娠・出産がきっかけで、解雇や契約打ち切り、自主退職への誘導などをされた」(11.5%)がもっとも多く、他には「妊娠を相談できる職場文化がなかった」(8.6%)、「妊娠中や産休明けなどに心無い言葉を言われた」(8.0%)、「妊娠中・産休明けに残業や重労働などを強いられた」(5.4%)が続いた。
「マタハラが起こる原因は何だと思うか」という問い対し、もっとも多かったのは「男性社員の妊娠・出産への理解不足、協力不足」(67.3%)で、以下「職場の定常的な業務過多、人員不足」(44.0%)、「女性社員の妊娠・出産への理解不足、協力不足」(39.1%)、「フォローする周囲の社員への会社の評価制度整備や人員増員などのケア不足」(37.6%)などが続いた。
マタハラが起こらないようにするための対策については、「休業・復帰しやすくなる制度や会社にとっての負担軽減、または制度に関する会社の理解促進」(50.3%)、「育児に携わった女性のマネジメント・経営陣への登用(理解者を増やす)」(48.3%)、「行政による保育園や学童保育制度の改革」(46.6%)、「職場での適切な人員補充」(42.8%)、「育児に携わった男性のマネジメント・経営陣への登用(理解者を増やす)」(39.8%)などの回答が並んだ。
保育園の入園条件の緩和を求める女性が7割
働きながら子どもを育てるためには、"子どもを預ける環境"が必要になる。「保育園や学童保育など子どもを預ける環境が仕事選びやキャリア形成に影響すると思いますか?」という質問では、「影響がある」と答えた人が93.4%。具体的な影響としては「時短制度など働き方に変化があった」(50.2%)、「仕事を辞めざるをえなかった」(32.6%)、「雇用形態を変えざるをえなかった」(30.1%)が多かった。
保育園の入園審査については、現状では母親の労働時間や月の勤務日数などの点数で評価されるため、フルタイムではないパートなどでは入園に不利になりやすい。これについて「保育園がなければ働けないので、フルタイムの勤務でなくても入園に不利にならないようにしたほうが望ましい」と答えた人が69.9%と大多数を占めた。
産休・育休は正社員だけの権利だと思われがちだ。しかし実は、パートや契約社員など、有期契約で働く労働者でも、ある条件をクリアした場合には育休が取得できる。その条件とは、「育休開始時において同じ会社に1年以上雇用されており、さらに子が1歳の誕生日以降も引き続き雇用が見込まれ、子の2歳の誕生日の前々日までに雇用契約が満了し、更新されないことが申し出時点で明らかになっていない場合」だ。
このことを知っているか尋ねたところ、75.3%が「知らない」と回答していた。この条件について「不公平。有期契約でも育休を取れるように条件を緩めるべき」(41.1%)という声が多く、「現実的な条件ではない」(29.7%)を合わせると70.7%が条件の緩和を求めていることが分かった。
女性だけに働くことと家事・育児の両立を求める風潮に疑問
最近は「女性活用」の議論が活発になってきているが、「それについてどう感じているか」という質問に対し、もっとも多かったのは「女性だけに働くことと家事・育児の両立を求める風潮に疑問」(55.7%)。他にも「現場の声が届いていない、机上の空論」(45.1%)、「非正規社員の女性の働き方にも目を向けてほしい」(41.6%)、「制度だけでなく現場の理解が高まればいいと思う」(40.4%)、「女性だけでなく、男性にもっと当事者意識を持ってほしい」(39.1%)といった意見が多く、いずれも約4割上がった。
連合は9月17日、女性が妊娠・出産を経ながら働き続けられるように、「マタハラに負けない!! 産休・育休なんでも労働相談」を実施する。産休・育休を経験した女性弁護士や社会保険労務士などが対応する。電話相談の受付時間は午前10時~午後8時で、フリーダイヤル0120-3919-25。
日本労働組合総連合会
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2026 SOSHINSHA All Rights Reserved.


「健診・検診」に関するニュース
- 2025年08月21日
- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告
- 2025年07月07日
- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市
- 2025年06月27日
-
2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%
過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日
-
【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ
対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日
- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】
- 2025年05月20日
-
【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築
―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日
- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善
- 2025年05月16日
- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少
- 2025年05月12日
- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要
- 2025年05月01日
- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】