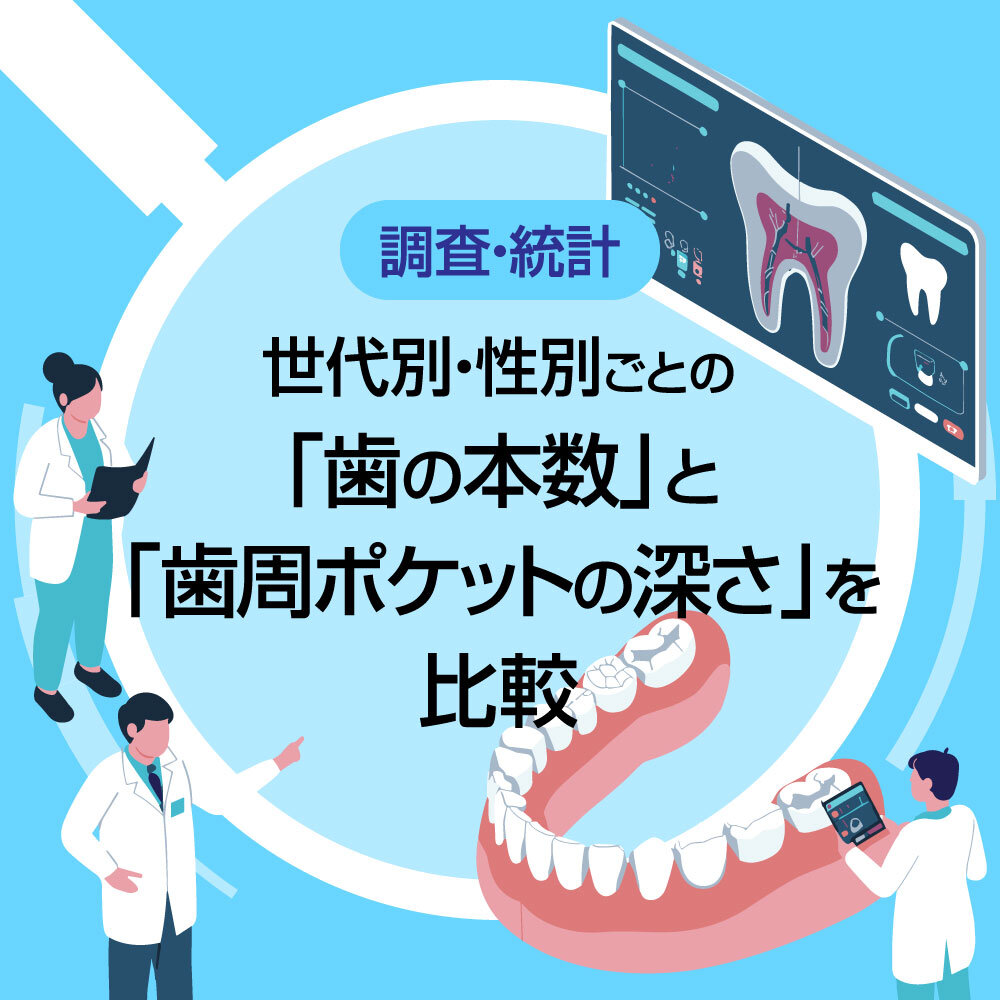ニュース
今後の特定健診のありかたを議論 第1回健康診査等専門委員会レポート
2015年11月20日
第1回健康診査等専門委員会
第1回厚生科学審議会健康診査等専門委員会(委員長:辻一郎・東北大学大学院公衆衛生学教授)が11月18日に開催された。今後の健診のあり方や健診項目に関するエビデンスの収集・分析結果について議論が交わされた。
第1回厚生科学審議会健康診査等専門委員会(委員長:辻一郎・東北大学大学院公衆衛生学教授)が11月18日に開催された。今後の健診のあり方や健診項目に関するエビデンスの収集・分析結果について議論が交わされた。
委員会では、健康診査の実施に関する指針の趣旨をふまえて、健康増進事業実施者が事業を適切に実施する際の参考にするため、研究班や有識者による専門的な検討を行い、健診のあり方や健診項目に関するエビデンスを収集・分析結果をとりまとめる。2016年半ばをめどにエビデンスをとりまとめ、2017年半ばまでに同指針の見直しに関する報告書を作成する予定。
「健診」と「検診」の区別は明確ではない
委員会の冒頭で示された資料によると、「健診」と「検診」には一部重復する部分はあるものの、内容は「主に将来の疾患のリスクを確認する検査」と「主に現在の疾患自体を確認する検査」に分かれる。
健診において行われる検査項目には、測定値などにより疾患リスクの確認と疾患自体の確認の両方の性質をもつものがある。委員からは「健診に携わる者にとって両者の区別は明確とはいえず、検査ごとに健診か検診かを区別するのは困難」との意見が出された。


健診の科学的評価を行う必要がある
第1回となった今回の会議では、福井次矢氏(聖路加国際大学理事長)、磯博康氏(大阪大学公衆衛生学教授)、永井良三氏(自治医科大学学長)の3人の参考人が、日本で行われている健康診査の現状と今後の展望について解説した。
福井氏は健診の評価の国内外の現状を解説し、「日本では、基本健康診査を含む各種保健事業について、厳密な科学的評価はほとんどなされてこなかった。とくに一部市町村および医療保険の保険者などでは、各種保健事業・健康づくりについて独自に企画されてきたものもあるが、その評価はほとんどなされていない」と指摘した。
検診項目とされるための要件として、(1)症状発現後の治療に比べて、早期発見後の治療がより効果的である、(2)検査性能が優れている、(3)安全である、検査に伴う合併症がない、軽微なものが低頻度、(4)安価である、費用対効果が高い、(5)(検者と受診者にとって)手間がかかり過ぎない、(6)頻度が高い疾患である――を挙げた。
同氏によると、世界保健機関(WHO)は「検診計画のWilson-Jungner基準」を定め、科学的知見の蓄積に伴い内容の見直しを行っているほか、カナダや米国でも個別の健診項目を定期的に評価し、エビデンスレベルや推奨度を改訂しているという。

生活習慣が変化する時期の一貫したデータ収集が必要
磯氏は医学分野のスクリーニングの定義はこの数十年で大きく変わっていると説明し、スクリーニング検査を適用するための要件として、(1)疾患・前状態の早期、あるいは無症状での把握ができること、(2)スクリーニング後に確定診断する適切な方法があること、(3)効果的な治療・介入手段があること、(4)スクリーニング導入による費用対効果が見込めること、(5)適切で継続的な運用・評価と精度管理が行えること――を挙げた。
ライフコースの観点からみた健診は「母子保健」「学校保健」「産業保健」「成人・老人保健」に大きく分かれ、それぞれ母子保健法、学校保健法、健康増進法、高齢者医療確保法などにもとづき実施されているが、「スクリーニングとして実施すべき検査項目と医療として実施すべき検査項目は必ずしも一致しない」と指摘。健診を生涯にわたり切れ目なく実施することが重要で、生活習慣病予防の観点からは「出生から成人初期も重要時期」と強調した。

現在の特定健診では多くのハイリスク者が見逃されている
永井氏は生活習慣病の自然史をよく理解して、どの段階で何を予防することを目的として健診を行うかを明確にする必要があると指摘。「特定健診は心血管病のリスクを見つけ、早期に対応することが目的。がん検診との違いに注意する必要がある」と述べた。
脳・心血管疾患の予防のためのスクリーニングの特徴として、(1)脳・心血管疾患そのものをスクリーニングするのではない、(2)健診でスクリーニングするのは、将来、脳・心血管疾患を発症する確率が高いハイリスク者である、(3)コホート研究により、その集団におけるハイリスク者の定義が必要である、(4)ハイリスクたらしめている要因(危険因子)に対する介入研究(無作為化比較対照試験)によって、要因の除去や軽減で脳・心血管疾患の発症率(死亡率)が減少するというエビデンスが必要、(5)ハイリスク者への介入が伴わないとスクリーニングとしての健診を行う意味がない。ポピュレーションアプローチだけでなく、要医療(主に薬物治療)、保健指導などハイリスク者への介入方法を選定するための健診をより重視すべき――と説明した。
脳・心血管疾患のリスクの高い日本人1万人を対象とした研究で、高血圧の人の血圧値を降圧治療で10mmHgを下げるとリスクは30%減少し、高LDLコレステロール血症の人のLDLコレステロール値をスタチンで30mg/dL下げるとリスクが30%リスク低下した例を挙げ、「ハイリスク者スクリーニングの脳・心血管疾患予防効果は健診受診率と介入実施率によって大きく影響される」と強調した。
その上で「企業の特定健診の分析では、肥満者は非肥満者よりも心血管病のリスクは相対的に高いが、非肥満者でも多くの発症が存在する。現在の特定健診後の介入では多くのハイリスク者を見逃している」と指摘し、「生活習慣病の自然史をよく理解して、どの段階で何を予防することを目的として健診を行うかを明確にする必要がある」との見方を示した。



腹囲基準の妥当性についての議論は続いている
特定健診の現行の腹囲基準が妥当性については、これまでも厚労省検討会で議論が行われている。検討会委員や参考人からは「腹囲により肥満者を判定し、他のリスクと併せて階層化して保健指導を行う現行の枠組みは妥当といえる。しかし、非肥満でリスク因子を有する者は、循環器疾患のリスクが高いにもかかわらず保健指導の対象とならないため、制度的な対応が必要ではないか」といった意見も出ている。
厚労省事務局によると、健診項目などに関しては必要に応じて検討会を設置し、エビデンスの収集と分析を行い2016年半ばに中間取りまとめ、2017年半ばに最終報告書がまとめられる予定。「特定健診に関しても、一定の意見の取りまとめを行って、同委員会に報告したい」としている。
第1回健康診査等専門委員会(厚生労働省厚生科学審議会 2015年11月18日)
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.


「健診・検診」に関するニュース
- 2025年08月21日
- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告
- 2025年07月07日
- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市
- 2025年06月27日
-
2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%
過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日
-
【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ
対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日
- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】
- 2025年05月20日
-
【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築
―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日
- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善
- 2025年05月16日
- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少
- 2025年05月12日
- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要
- 2025年05月01日
- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】