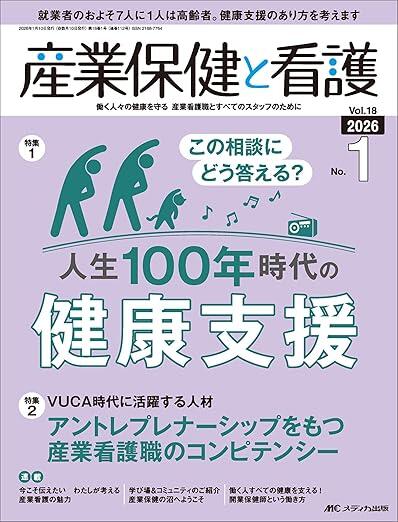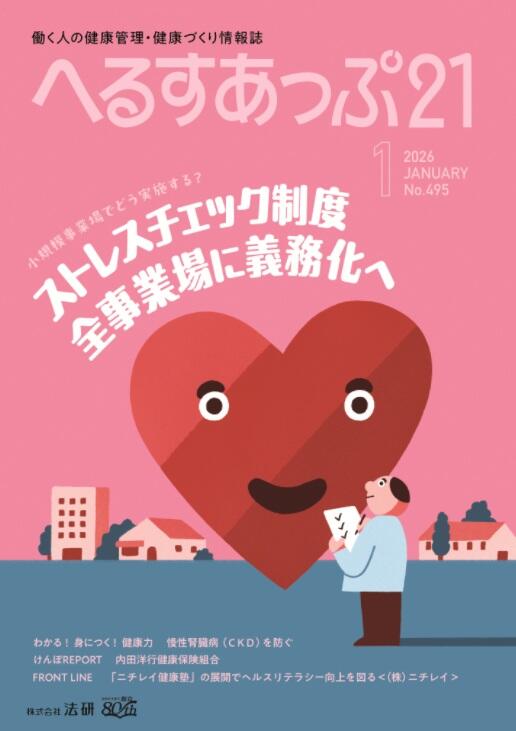ニュース
子どもの健康に家庭の「貧困対策」が大きく影響 4人に1人が「生活困難」
2016年04月28日

東京都足立区は、子どもの健康と家庭の経済状況や生活習慣との関連などを調べる「子どもの健康・生活実態調査」の結果を発表した。家庭環境や生活習慣などの「変えていくことが可能な」要因により、子供の健康は大きく向上するという。自治体が貧困対策を目的にこうした大規模調査を行うのは全国ではじめて。
子どもの6人に1人が貧困状態 貧困対策が必要
「平成26年国民生活基礎調査」によると、子どもの6人に1人が貧困状態にある。足立区は2015年度を「子どもの貧困対策元年」と位置付け、「足立区子どもの貧困対策実施計画」を策定し、全庁をあげた取組みを開始している。
調査は昨年7月と11月、足立区立小学校全69校の1年生5,355人の保護者を対象に、区が学校を通じて無記名のアンケート方式で配布・回収。国立成育医療研究センターが集計・解析した。有効回答は4,291人(回答率80.1%)だった。
調査では、(1)世帯年収300万円未満、(2)生活必需品の非所有(子どもの生活で必要な物品や5万円以上の貯金がないなど)、(3)過去1年間に水道・ガスなどのライフラインの支払いが困難だった経験がある――のいずれかが当てはまる世帯を「生活困難」世帯と定義。
その結果、「生活困難」は4人に1人の24.8%に上り、このうち半数近く(11.6%)は世帯年収が300万円未満だった。
その上で、朝食や運動、読書の習慣、虫歯の有無、家庭の経済状況など17項目について質問したところ、家庭の経済状況や環境が子どもの健康や生活に大きく影響することが判明した。

相談できる相手がいれば子供の健康状態は改善
「生活困難」世帯では、5本以上の虫歯がある割合(19.7%)は、生活困難でない世帯の割合(10.1%)の約2倍。朝食を毎日食べる習慣のない子の割合(11.4%)は生活困難でない世帯の割合(3.5%)の3倍以上に上った。
また、麻しん・風しん混合ワクチンの予防接種(自己負担なし)を受けていない割合(13.4%)も、生活困難でない世帯(7.4%)の約2倍に上った。
子どもの医療費が無料(公費負担)であることをふまえると、経済的な理由だけでなく、保護者が子どもの健康に関心があるか否か、そのための時間を確保できるかどうかなどの要因が影響していると考えられる。
さらに、たとえ生活困難であっても、保護者が困った時に相談できる相手がいれば、子供にはあまり健康問題があらわれないことが分かった。ワクチンを接種していない子どもの割合は、相談相手いる世帯(12.6%)は、相談相手いない世帯(20.4%)より少なかった。

生活困難でも家庭や生活で「変えられる要因」が大きい
自己肯定感や自己制御能力など「逆境を乗り越える力」を測る調査も行った。その力が弱い子供の割合は、「生活困難」世帯では相談相手がいないと31.5%に上ったが、相談相手がいると12.0%に低下した。保護者が困ったとき相談できる相手がいる「生活困難」世帯では、逆境を乗り越える力が育まれることが判明した。
生活困難が子どもの逆境を乗り越える力に与える影響の割合は15%で、このうち生活困難の間接的な影響は94%だった。そのうち割合が大きいのは「親の抑うつ傾向」(11%)、「朝食欠食」(8%)、「運動習慣」(8%)、「読書習慣」(7%)、「相談できる人」(5%)、「スナック菓子の摂取」(5%)だった。
足立区には、区民の健康寿命が都の平均よりも約2歳短いという健康格差があり、その主な要因は2型糖尿病だという。そこで、区民の健康寿命の延伸に向けて、「足立区糖尿病対策アクションプラン」を策定し、糖尿病に重点を置いた取組みを展開している。
2型糖尿病をはじめとする生活習慣病を予防するために、子どもの頃から正しい生活習慣を身につけることが効果的だ。しかし実際には、高学年になるにつれて肥満傾向児の割合が高くなるという。
記者会見した近藤弥生区長は「子どもを取り巻く家庭環境や生活習慣などの"変えていくことが可能な"さまざまな要因がもたらす影響がより大きいことが明らかになりました。つまり、家庭環境や生活習慣などを変えていくことにより、生活困難の影響を軽減し、子どもの健康を守り育てていくことが可能ということです」と述べた。
子どもの健康・生活実態調査(東京都足立区 2016年4月22日)
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2026 SOSHINSHA All Rights Reserved.


「地域保健」に関するニュース
- 2025年08月21日
- 令和7年(1月~7月)の自殺者は11,143人 前年同期比で約10%減少(厚生労働省)
- 2025年08月21日
- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告
- 2025年08月13日
-
小規模事業場と地域を支える保健師の役割―地域と職域のはざまをつなぐ支援活動の最前線―
【日本看護協会「産業保健に関わる保健師等の活動実態調査」】〈後編〉 - 2025年08月07日
- 世代別・性別ごとの「総患者数」を比較-「令和5年(2023)の患者調査」の結果より(日本生活習慣病予防協会)
- 2025年08月06日
-
産業保健師の実態と課題が明らかに―メンタルヘルス対応の最前線で奮闘も、非正規・単独配置など構造的課題も―
【日本看護協会「産業保健に関わる保健師等の活動実態調査」】〈前編〉 - 2025年07月28日
- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善
- 2025年07月28日
- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減
- 2025年07月28日
- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由
- 2025年07月28日
- 【妊産婦を支援】妊娠時に頼れる人の数が産後うつを軽減 妊婦を支える社会環境とメンタルヘルスを調査
- 2025年07月22日
- 【大人の食育】企業や食品事業者などの取り組み事例を紹介 官民の連携・協働も必要 大人の食育プラットフォームを立ち上げ