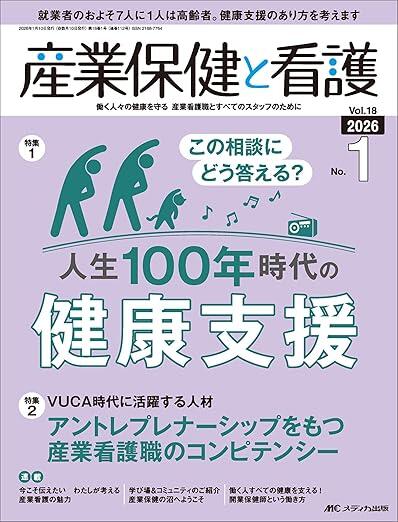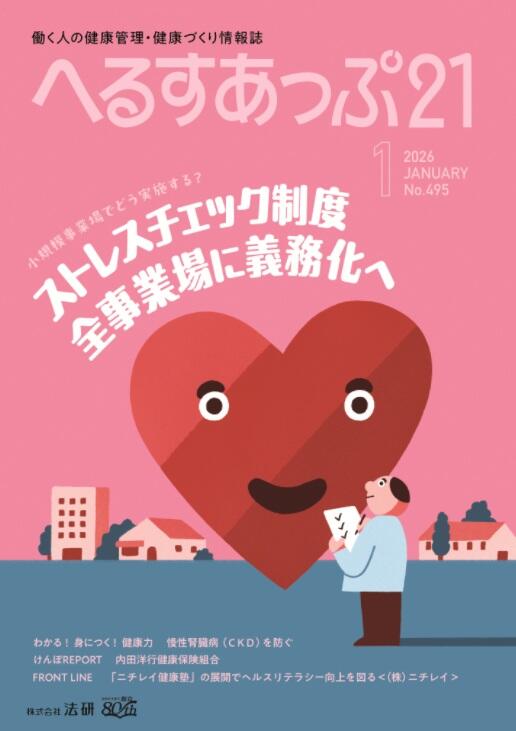これだけ守れば糖尿病は恐くない 糖尿病を改善する「チェックリスト」

国際糖尿病連合(IDF)の発表によると、世界の糖尿病人口は爆発的に増え続けており、2015年時点で糖尿病有病者数は4億1,500万人に上る。有効な対策を施さないと、2040年までに6億4,200万人に増加すると予測している。
糖尿病を発症している可能性が高いにも関わらず、検査を受けて糖尿病と診断されていない人の数は全世界で1億9,300万人(46.5%)に上る。つまり世界の糖尿病有病者のおよそ半分は自分が糖尿病であることを知らない。
適切な糖尿病の治療を続けていれば、脳卒中、失明、腎臓病、足病変といった合併症の多くは予防が可能だが、そのためには早期診断・治療が必要となる。糖尿病は初期段階では自覚症状が乏しい病気なので、1年に1回以上は糖尿病の検査を受ける必要がある。
「成人の11人に1人が糖尿病を発症しています。一度糖尿病を発症すると、治療は生涯続きます。糖尿病の医療は進歩していますが、治療の中心となるのは患者自身が自己チェックするセルフケアです。悩みや疑問をもっている人は、医師や医療スタッフに相談することを勧めます」と、英国糖尿病学会のエグゼクティブチームの責任者であるサイモン オニー氏は述べている。
定期的に検査をして血糖値が高くなっていないかどうかを調べることが必要です。血糖値が高い状態が続くと、目・腎臓・神経の病気、脳梗塞・心筋梗塞などの合併症が引き起こされますが、血糖値のコントロールを良好に維持すれば、これらを防ぎ問題なく普通の生活をおくれます。
HbA1c値は過去1?2ヵ月の血糖の状態を示す値です。年に一度は医療機関で検査を受け、測定値やコントロール目標について医療スタッフとよく相談しましょう。
血糖値と血圧値が高いと、動脈硬化や心筋梗塞などの危険性が高まります。血圧値は年齢によって変わっていき、目標となる血圧値があります。
家庭用血圧計も入手しやすくなっているので、1ヵ月に1回以上はかりましょう。血圧をコントロールして目標値に近付けるためにどうすればよいか、主治医や医療スタッフとよく相談しましょう。
コレステロール値にも、血糖値と血圧値と同じように、あなたに合ったコントロール目標があります。目標値の設定について医療スタッフと相談しましょう。
悪玉のLDLコレステロール、善玉のHDLコレステロール、中性脂肪は食事や運動の影響を受けやすく、値が高いと薬による治療が必要となる場合があります。
網膜症は糖尿病患者さんに多い合併症です。糖尿病と診断されたときから定期的な眼科の検査を受け、糖尿病と眼科の適切な治療を続けていれば、失明を防げます。糖尿病の医師と眼科の医師の連携も大切です。1年に1回以上、眼の検査を受けましょう。
血糖値のコントロールがうまくできず、糖尿病を悪化させると、合併症が起こり、障害が進むと足に潰瘍や壊疽が起こりやすくなります。検査を受けずにいて発見が遅れ、症状が悪化するケースが多くみられます。
医療機関が定期的に検査してもらい、自分でも足の状態をチェックし、問題が起きていれば医師や医療スタッフに相談しましょう。
腎臓の機能の低下が慢性的に続く「慢性腎臓病」(CKD)は、慢性腎臓病は腎臓の働きが低下していない初期段階であれば完治も可能です。しかし、放置しておくと自覚症状がないまま腎臓の機能が徐々に低下し、進行すると脳卒中、心筋梗塞など、全身の病気にもつながります。
腎機能が低下していないか、年に1回以上は検査を受けるべきです。腎臓の機能の低下を発見するために有効なのが、たんぱく尿検査と血清クレアチニン検査です。治療の基本は生活習慣改善、高血圧など原因となる病気の治療です。
糖尿病や糖尿病予備群と診断されたその日から、多くの場合で食事の調整をしなければならなくなります。しかし、食事療法は「食べたいものを我慢すること」と誤解されやすいのですが、実際は食事のカロリーと栄養バランスを適切にコントロールすることです。そのために管理栄養士のアドバイスが必要です。
食事療法とともに体重をはかることも大切です。体重の増減が大きい場合は、健康に影響を及ぼす要因が隠れている可能性があります。体重コントロールの目標のある人は、ウエスト周囲径もはかり、得られた値について管理栄養士に相談しましょう。

糖尿病は一度発症すると完治することはなく、治療の中心となるのは患者自身の自己管理(セルフケア)です。患者の主体的な取り組みが必要となりますが、これを実行するために大きな感情的負担が伴います。
こうしたストレスを抱えた患者が自己管理を継続できるように心理的にサポートする必要があります。糖尿病を受けとめられず悪戦苦闘している患者が、不満や自分の感情をありのままに受けとめてもらえ、共感してもらえ、糖尿病を自分自身の病気として受け入れられるような援助が必要です。
慢性疾患をもつ患者の心理的サポートについての専門的な治療も進歩しています。患者が治療に取りかかる動機づけを起こさせることも医療の現場の大きな課題です。
糖尿病療養を支援する糖尿病教室は各地で開催されています。糖尿病について分からなかったことを理解する良い機会になります。糖尿病と診断されたら、近辺で開催される糖尿病教室について医療スタッフに聞いてみましょう。
糖尿病の治療に取り組む仲間同士の語らいや情報交換から、治療の助けとなる情報を得られる可能性もあります。
糖尿病の治療では、医師、看護師、管理栄養士、薬剤師、理学療法士、臨床検査技師などか、それぞれの得意分野を受けもって、連携をとりながら対応しています。医師に相談しにくい場合は、他の医療スタッフに相談してみるのもいいかもしれません。
糖尿病の高度な治療が必要がなった場合は、糖尿病専門医に診療をしてもらう必要が出てきます。そうした場合に専門医に紹介してもらえるか、主治医に聞いてみましょう。
糖尿病の人が血糖コントロールが良くない状態が続くと、インフルエンザなどの感染症に対する体の免疫機能が低下している場合があります。糖尿病をもつ人は糖尿病でない人に比べ、インフルエンザにかかる危険性が高いという報告もあります。インフルエンザの流行シーズンが近づいたら、糖尿病患者はインフルエンザの予防接種をお勧めします。
教育入院は、入院で食事管理、運動指導、衛生管理や合併症についてなど、血糖値を良い状態に保つための指導、学習を受けながら治療を行う入院です。糖尿病療養指導士などが院内で開く教育講座にも参加できます。血糖値を低くすることができ、糖尿病の悪化を防ぐことにつながります。
糖尿病が性的な問題を引き起こし、夫婦関係に障害をもたらすおそれがあります。糖尿病の男性にもっとも広くみられる障害は勃起障害で、他の病気の患者の性的能力が減退するのが50歳のころであるとすれば、糖尿病患者の場合には10年早いという報告があります。血糖コントロールが不良であると血管障害や神経障害が起こりやすいことが一因です。
「性機能の低下」を防ぐために必要なのは、糖尿病を早期発見し治療を受けることです。治療をすると性的欲求が戻ってきて、表情にはりが出てきて、糖尿病などの慢性疾患の治療が改善するというケースも少なくありません。
たばこには交感神経を刺激して血糖を上昇させるのに加え、血糖を下げるインスリンの働きを妨げる作用があります。そのため喫煙者は糖尿病にかかりやすくなります。また、たばこを吸い続けると治療の妨げとなるほか、脳梗塞や心筋梗塞、腎臓病などの合併症のリスクが高まります。
もしあなたがタバコを吸っているのなら、なんとしてでもやめましょう。現在は健康保険を適用して、禁煙治療を受けることができます。具体的な禁煙の方法について、医師に相談しましょう。
妊娠をきっかけに血糖値や血圧値が高くなる女性もいます。そうした場合も計画妊娠によって健康な人と同じように妊娠・出産ができます。妊娠糖尿病を経験した人は、そうでない人に比べ、将来糖尿病を発症するリスクが数倍になることが知られています。
妊娠糖尿病の発見が食生活を改善するきっかけになり、安全に出産した人は大勢います。大切なのは、妊娠糖尿病を放っておかないことです。
New 15 Healthcare Essentials Guide(英国糖尿病学会 2016年4月16日)


「特定保健指導」に関するニュース
- 2025年07月28日
- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善
- 2025年07月28日
- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減
- 2025年07月28日
- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由
- 2025年07月28日
- 【妊産婦を支援】妊娠時に頼れる人の数が産後うつを軽減 妊婦を支える社会環境とメンタルヘルスを調査
- 2025年07月22日
- 【大人の食育】企業や食品事業者などの取り組み事例を紹介 官民の連携・協働も必要 大人の食育プラットフォームを立ち上げ
- 2025年07月22日
- 高齢者の社会参加を促すには「得より損」 ナッジを活用し関心を2倍に引き上げ 低コストで広く展開でき効果も高い 健康長寿医療センター
- 2025年07月18日
- 日本人労働者の3人に1人が仕事に影響する健康問題を経験 腰痛やメンタルヘルスなどが要因 働きながら生産性低下を防ぐ対策が必要
- 2025年07月18日
- 「サルコペニア」のリスクは40代から上昇 4つの方法で予防・改善 筋肉の減少を簡単に知る方法も
- 2025年07月14日
- 適度なアルコール摂取は健康的? 大量飲酒の習慣は悪影響をもたらす お酒との良い関係
- 2025年07月14日
- 暑い夏の運動は涼しい夕方や夜に ウォーキングなどの運動を夜に行うと睡眠の質は低下?