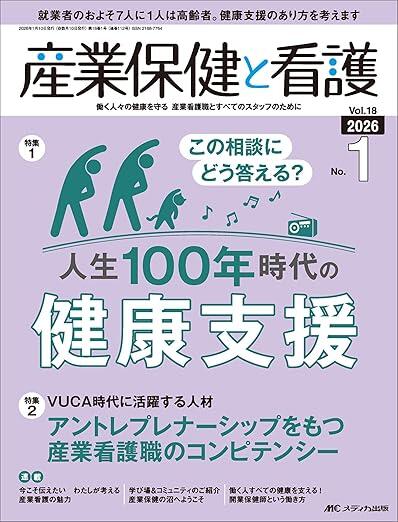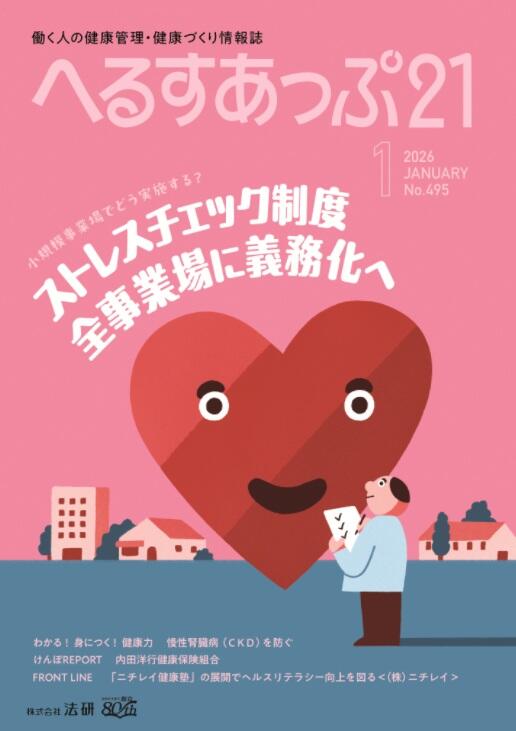ニュース
地球温暖化で気温が上がると糖尿病が増える 脂肪が燃えにくい体に変化
2017年03月23日

地球温暖化の影響で気温が上昇すると、2型糖尿病の発症が増えるという研究が発表された。
気温が1度上昇すると、米国だけで年間に10万人以上、糖尿病の発症数が増えるという。
気温が1度上昇すると、米国だけで年間に10万人以上、糖尿病の発症数が増えるという。
地球温暖化の影響で褐色脂肪細胞が減る
世界的な糖尿病の増加の一因は気温の上昇である可能性があるという研究が、医学誌「BMJ Open Diabetes Research & Care」に発表された。
世界的に2型糖尿病の有病者数は爆発的に増えている。2015年には4億1,500万人だったが、2040年までに最大で6億4,200万人に増えると予測されている。
一方で、世界の年平均気温は、長期的には100年あたり約0.72度の割合で上昇しており、特に1990年代半ば以降、高温となる年が多くなっている。
オランダのライデン大学医療センターのパトリック レンセン教授(血管疾患・代謝学)らは、世界的な気温の上昇が、褐色脂肪細胞の活性を抑制し、グルコース代謝を低下させ、結果として2型糖尿病を発症する人が増えるのではないかと考えている。
褐色脂肪細胞は、脂肪を燃焼させて、体の熱を生成し、体温を維持する働きをする。
ハーバード大学ジョスリン糖尿病センターの研究によると、運動不足により増えた白色脂肪細胞が、運動をすることにより減り、褐色脂肪細胞が増えるという。
さらに、白色脂肪細胞を減らし褐色脂肪細胞を増やすと、代謝そのものが改善し、脂肪を燃焼しやすい体になる可能性がある。
気温の低い環境下に身を置いていると、褐色脂肪細胞が活性化されて、熱を発生する。体が体温を調整するメカニズムは、体重の減少や、インスリンの作用にも影響しており、褐色脂肪細胞の多い人は2型糖尿病になりにくいと考えられている。
気温の変化と2型糖尿病の発症率の関連を調査
ライデン大学医療センターの研究チームは、世界的な規模で、気温の変化と2型糖尿病の発症率、耐糖能異常の有病率について調査した。
米国の50州と3つの領域(グアム、プエルトリコ、ヴァージン諸島)の1996~2009年のデータと、疾病管理予防センター(CDC)の全国糖尿病調査システムのデータをもとに、成人の糖尿病発症率について検証した。
さらに、世界190の国や地域について、世界保健機関(WHO)の国際健康観測オンラインデータベースを使用し、空腹時血糖値の上昇と肥満の有病率について調査した。また、英国のイースト アングリア大学の気象研究の成果をもとに、世界の年間平均気温について資料を作成した。
気温が1度上昇すると糖尿病の発症率が増加
その結果、気温が1度上昇すると、糖尿病の発症率は1,000人当たり0.314人増加し、耐糖能異常の比率は0.17%増加することが判明した。
米国のデータでも、屋外の気温が上昇すると、2型糖尿病と耐糖能異常の発症率がそれぞれ上昇する傾向がみられた。
これらの知見により、研究グループは、気温が1度上昇すると、米国だけでも糖尿病の発症数が年間に10万人以上増えるという予測値を弾き出した。
今回は観察研究によるものなので、原因と結果の因果関係を証明することはできないが、研究チームは米国の州の経線ごとのデータも分析している。
年齢や性、収入、肥満といった因子を考慮しても、気温上昇と糖尿病発症には関連があることが示されたという。ただし、体格指数(BMI)に関するデータはなかったので、BMIとの関連は不明だという。
「米国では2016年に記録的な暖冬が報告された他、各地で温暖化が指摘されています。気温の上昇と2型糖尿病の発症とグルコース代謝の関連については、今後さらに研究を重ねる必要があります」と、研究者は述べている。
運動で褐色脂肪細胞を増やす工夫を
環境問題を個人レベルで取り組めることは少ないが、運動を習慣として行うことで、気温上昇に備えることはできる。
気温が上昇し暖冬になると、暑い夏には注意が必要だが、冬・春・秋にはウォーキングなどの運動をしやすくなる。運動することで褐色脂肪細胞を増やし、脂肪を燃焼しやすい体に変えていくことは可能だ。
また、温暖化をもたらす大きな要因は大気中の二酸化炭素などの増加だ。これは、植物にとって光合成を活発にし、生長を促すという効果もある。たとえば、2~3度ぐらいの気温上昇では、中緯度地域での農作物の収量は増えると予測されている。
気温の上昇により、野菜などの市場価格が下がり、利用しやすくなる可能性もある。栄養バランスの良い食事を摂りやすくなると、糖尿病の食事療法も改善する。
地球温暖化は確実に進んでいる。変化に対応した体調管理と健康増進を心がけたい。
Growing global temperatures could be contributing to rising diabetic numbers(BMJ 2017年3月20日)Diabetes incidence and glucose intolerance prevalence increase with higher outdoor temperature(BMJ Open Diabetes Research and Care 2017年1月)
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2026 SOSHINSHA All Rights Reserved.


「健診・検診」に関するニュース
- 2025年08月21日
- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告
- 2025年07月07日
- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市
- 2025年06月27日
-
2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%
過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日
-
【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ
対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日
- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】
- 2025年05月20日
-
【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築
―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日
- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善
- 2025年05月16日
- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少
- 2025年05月12日
- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要
- 2025年05月01日
- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】