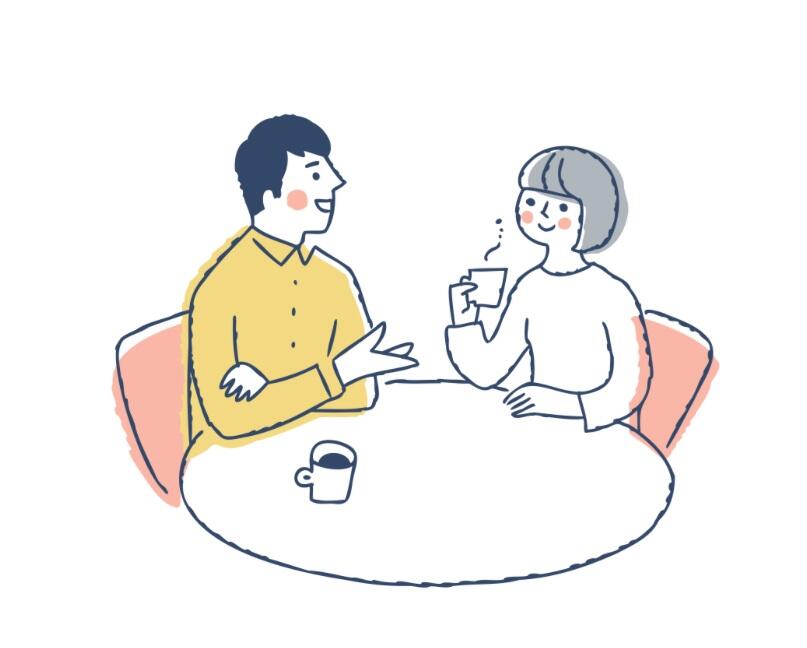ニュース
認知症の原因は「日常生活活動」の低下 日常活動や社会的活動が大切
2018年07月25日

国立精神・神経医療研究センター(NCNP)は、認知症の発症予防を目指したインターネット健常者登録システム「IROOP」を用いた研究の成果を発表した。風呂に入る、洋服を着ることなどの「日常生活活動」が低下することや、抑うつ、がん・糖尿病の既往、聴力損失などが、認知症の危険因子になるという。
身体活動の低下や認知機能の低下を防ぐために、家庭外の社会的活動への参加や気分低下の防止、2型糖尿病などの生活習慣病への介入が認知症予防になることが示された。
身体活動の低下や認知機能の低下を防ぐために、家庭外の社会的活動への参加や気分低下の防止、2型糖尿病などの生活習慣病への介入が認知症予防になることが示された。
認知症予防の日本初のシステム「IROOP」の研究成果
日本では2025年までに認知症人口が700万人まで達するという推計が発表されている。認知症、軽度認知症害(MCI)、とくにアルツハイマー病(AD)に対する対策が急がれているが、根治薬や治療薬の開発には至っていない。治療薬を開発するために臨床治験が必要となる。
そこで、国立精神・神経医療研究センター(NCNP)は2016年に、大規模なインターネット健常者登録システム「IROOP」を開設した。システムの目的は、認知症が発症する前の症状をとらえ、生活習慣の改善などにより発症を予防する因子の解明と、認知機能の改善が期待される薬の開発のための臨床研究や治験の促進だ。
NCNPの研究グループは今回の研究で、「IROOP」に登録されたデータから認知機能へ関連している因子や、半年後の認知機能の変化に影響している因子を探った。
(1)2017年8月までに初回アンケート項目への回答と電話による10単語記憶検査(あたまの健康チェック)を完了した1,038人(平均年齢59.0歳)と、(2)初回アンケート回答から半年経過後の定期アンケートと、(3)2回目の10単語記憶検査を終了した353人(平均年齢60.2歳)のデータを解析した。
認知機能の低下と関連のある項目を分析するため、10単語の記憶検査から得られる記憶機能指数である「MPIスコア」を求めた。認知機能の経時的変化にどのアンケートの項目が影響しているかを検討するため、初回MPIスコアと半年経過後の2回目MPIスコアの差を従属変数とし、各アンケート項目を独立変数として解析した。
認知機能の低下の要因が判明
その結果、初回MPIスコアの結果では、認知機能の低下と関連のあるのは、「年齢」「性別」「教育年数」「毎日行っている活動;自分で風呂に入る、服を着ることの支障の程度」「10年前と比べて予期される出来事に対して前もってスケジュールを調整する計画能力の変化」「糖尿病」「がんの既往」などの項目であることが分かった。
次に、初回MPIスコアと半年経過後のMPIスコアの差に影響しているアンケート項目は、「年齢」「6ヵ月前と比べて毎日の活動力や周囲への興味減少の程度」「外傷性脳損傷」「聴力損失の既往」「痛みの有無」「人生が空っぽと感じるかどうか」であることが判明した。
MPIスコアは0〜100の数値で示され、数値が低くなるほど認知機能の低下をあらわす。初回の分析結果では、「あなたの健康状態により自分で風呂に入る服を着ることにどの程度支障がありますか?」という質問に対して、「全く支障がない」を選んだ人は「かなり支障がある」と回答した人より、約3.8ポイント高いMPIスコアが示された。
同様に、「以下の病気に現在かかっているかまたはかかったことがありますか?−聴力損失−」では、「いいえ」と回答した人では、約2.4ポイント高いMPIスコアが示された。
関連情報
日常生活活動や糖尿病などの治療が重要
これらの結果より、▼風呂に入る、▼服を着る、▼スケジュールを立てるなどの、日常の活動が大切で、それに支障が起こり、気分が落ち込んだり意欲が低下すると、認知機能低下につながることが分かった。さらに、糖尿病、がん、頭部外傷の既往、聴力の損失、慢性的な痛みも認知機能の低下に関連することも判明した。
今回の研究により、日常生活活動の低下が認知機能の低下に関連していることが示された。日常生活活動の低下は家に閉居する要因のひとつとなり、その結果、社会的活動への参加減少、ひいては気分の低下をもたらす。家庭外での社会的活動への参加、また参加できる環境があることが認知症予防になると考えられる。
さらには、糖尿病、がんなども認知機能の低下につながる。これらの疾患の予防への取り組みも必要であることが示された。
「IROOP」システムは、半年毎のアンケートと認知機能の検査を無料で構成され、国民に無料で提供されている。今後さらに経時的なデータの解析を進めていくことにより、認知症を予防する効果的な手段の解明につながると期待される。
国立精神・神経医療研究センター(NCNP)Analysis of risk factors for mild cognitive impairment based on word list memory test results and questionnaire responses in healthy Japanese individuals registered in an online database(PLOS ONE 2018年5月17日)
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.


「健診・検診」に関するニュース
- 2025年08月21日
- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告
- 2025年07月07日
- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市
- 2025年06月27日
-
2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%
過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日
-
【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ
対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日
- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】
- 2025年05月20日
-
【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築
―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日
- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善
- 2025年05月16日
- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少
- 2025年05月12日
- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要
- 2025年05月01日
- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】