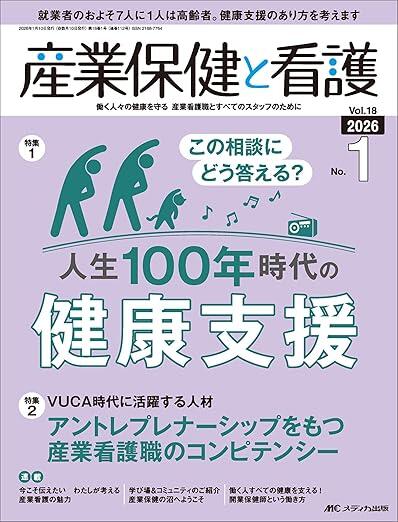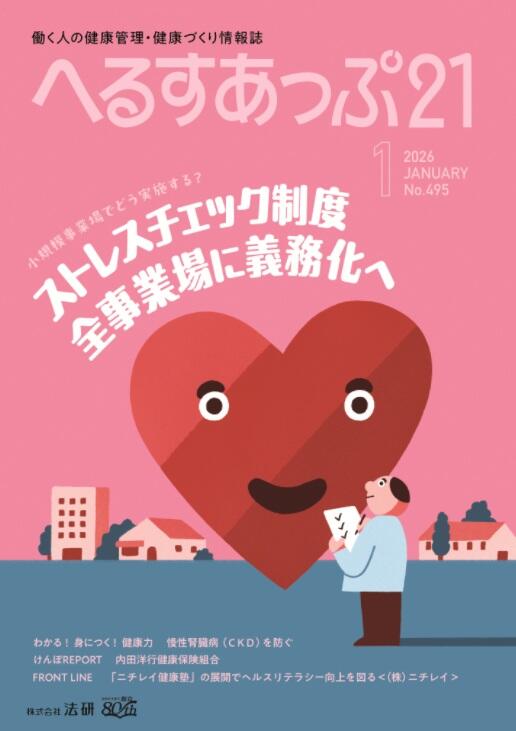ニュース
加熱調理の「アクリルアミド」にがんリスク 食品安全委員会が報告書
2016年02月17日

ジャガイモや野菜などの食材を高温で熱したときに生じる化学物質「アクリルアミド」について、内閣府食品安全委員会の作業部会は「がん発症を増やす懸念がないとは言えない。できる限り量を減らすべきだ」とする評価書案を公表した。
アクリルアミドがんを引き起こす 本格調査を実施
食品は加熱調理する過程でさまざまな化学物質が生成される。その中には、食品を食べやすくする、好ましい風味を醸し出す、保存性を高めるなど有用な効果をもたらすものがある一方で、健康に悪影響をもたらす副産物ができることがある。
炭水化物を含む食品を120度以上の高温で調理した食品に含まれる有害化学物質のひとつが「アクリルアミド」だ。


できるだけアクリルアミドの摂取量を減らす必要がある
内閣府食品安全委員会の作業部会は今回、日本人の食生活におけるアクリルアミドのリスクを5年にわたって検討し、報告書案をまとめた。
それによると、日本人の1日当たりの平均の摂取量は、体重1キログラム当たりおよそ0.2μgで、これは動物実験で発がん性が確認されている量と比べておよそ1000分の1だった。日本は欧州連合(EU)加盟国(0.4~1.9μg)より低く、香港(0.21μg)とほぼ同じだった。
しかし海外のリスク評価機関の中には、1万分の1より多い場合は低減対策が必要だと指摘しているものもあり、動物実験でがんが認められた最少量と日本人の平均推定摂取量が比較的近かった。報告書案では「できるだけアクリルアミドの摂取量を減らす必要がある」と結論している。
委員会は一般からの意見を募った上で最終的な評価書をまとめる。
アクリルアミドを減らすために家庭でできること
食品安全委員会によると、日本人では油で揚げたジャガイモや炒めたモヤシなど野菜からの摂取が多かった。長時間、高温で揚げるなどしないことや、野菜を調理前に水にさらすなどすることで、量を減らすことができる。
農林水産省は、家庭で調理するときにアクリルアミドができにくくする方法をまとめた冊子「安全で健やかな食生活を送るために アクリルアミドを減らすために家庭でできること」を作成し、ホームページで公開している。
それによると、アクリルアミドを減らすために家庭でできる方法として、次のことが効果的だ。
・ 炭水化物の多い食品を、必要以上に長時間、高温で加熱調理しないフライドポテトなどの揚げ物は、油の温度や揚げ時間に注意。じゃがいもや野菜などの炒め物も同様に、あまり焦がさないようにする。過度の加熱は食材の風味や栄養も損なう。 ・ 食品の加熱方法を見直し 煮る、蒸す、ゆでる調理法がお勧め
煮る、蒸す、ゆでるなどの調理法は、揚げ物や炒め物に比べてアクリルアミドが生成しにくい。
また、食品を下ゆでしたり加熱前に水にさらすと、アクリルアミドの原因となるアスパラギン、還元糖(ブドウ糖、果糖など)の量を減らす効果を得られる。
低温で長期保存したジャガイモは糖分が増えているため、加熱時にアクリルアミドができやすくなる。揚げ物や炒め物よりも、煮たり蒸したりする料理がお勧めだ。 ・ 低温で長期貯蔵したジャガイモを高温調理しない
ジャガイモは、低温で保存するとアクリルアミドができる原因となる成分であるブドウ糖と果糖が増える。そのため、低温で長期貯蔵されたジャガイモを、フライドポテトのような高温調理に使用することは避けるべきだ。

食品中のアクリルアミドに関する情報(農林水産省 2015年10月30日)
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2026 SOSHINSHA All Rights Reserved.


「健診・検診」に関するニュース
- 2025年08月21日
- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告
- 2025年07月07日
- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市
- 2025年06月27日
-
2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%
過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日
-
【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ
対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日
- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】
- 2025年05月20日
-
【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築
―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日
- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善
- 2025年05月16日
- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少
- 2025年05月12日
- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要
- 2025年05月01日
- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】