ニュース
内閣府が「アルコール健康障害対策推進基本計画」を策定
2016年06月16日
内閣府はこのほど「アルコール健康障害対策基本法」に基づく「アルコール健康障害対策推進基本計画」を策定した。不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となり、本人の健康はもちろん飲酒運転や暴力、虐待、自殺などさまざまな問題にも密接に関連することから、今後も基本計画に従って総合的かつ計画的にアルコール健康障害対策を推進していく。
国全体のアルコール消費量は減少傾向にあり、飲酒習慣がある成人や未成年者の飲酒割合も全体としては低下傾向にある。しかし、男女ともに多量に飲酒している人の割合は改善されておらず、一部の多量飲酒者が多くのアルコールを消費している現状があり、特に近年は女性のアルコール健康障害対策が重要視されている。
また、ごく普通に飲酒をしている人でも、さまざまなきっかけによってアルコール依存症に陥る可能性はある。さらに飲酒が原因で問題行動を起こすようになれば社会的に非難を受け、さらに追い込まれていく、という悪循環に陥りやすい。そのため、アルコール依存症に関する問題は社会全体の問題と考え、必要な知識や医療、回復のための支援を講ずる必要がある。
2010年には世界保健機関(WHO)が「アルコールの有害な使用を提言するための世界戦略」を採択するなど世界的にも適切な飲酒対策が進んだことから、国も2014年6月に「アルコール健康障害対策基本法」を施行。不適切な飲酒が自身の健康障害を引き起こすのみならず、家族への影響や飲酒運転や暴力など重大な社会問題を生じさせる危険性が高いことを明記した。そのうえで、関連施策と連携して根本的な問題解決を図っていくこと、アルコール健康障害を有する、また有していた人とその家族が円滑に生活できるよう支援することを基本理念としている。
この基本理念を踏まえ、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進するため、同推進基本計画が策定された。計画期間は平成28(2016)年度から平成32(2020)年度までの概ね5年間を対象としている。
【重点課題】
1.飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を徹底し、将来にわたるアルコール健康障害の発生を予防
(1)特に配慮を要する者(未成年者、妊産婦、若い世代)に対する教育・啓発(2)アルコール依存症に関する正しい知識・理解の啓発
(3)アルコール健康障害対策推進基本計画における目標
飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を徹底することにより、
1. 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合を、男性13.0%、女性6.4%まで減少させること
2. 未成年者の飲酒をなくすこと
3. 妊娠中の飲酒をなくすこと
を目標として設定する。
2.アルコール健康障害に関する予防及び相談から治療、回復支援に至る切れ目のない支援体制の整備
(1)アルコール健康障害への早期介入(2)地域における相談拠点の明確化
(3)アルコール健康障害を有している者とその家族を、相談、治療、回復支援につなぐための連携体制の推進
(4)アルコール依存症の治療等の拠点となる専門医療機関の整備
(5)アルコール健康障害対策推進基本計画における目標
アルコール健康障害に関する予防及び相談から治療、回復支援に至る切れ目のない支援体制の整備のために、全ての都道府県において 1. 地域における相談拠点 2. アルコール依存症に対する適切な医療を提供することができる専門医療機関がそれぞれ1箇所以上定められること、を目標として設定する。
【基本的施策】
1.教育の振興等
(1)学校教育等の推進:学校教育においてアルコールが心身に及ぼす影響などを正しく認識させ、未成年では飲酒しない判断力と態度を育てる。大学での啓発や医学・看護・福祉・介護・司法等の専門教育における基本法の周知、自動車教習所での飲酒運転防止のカリキュラムの確実な履行徹底など。(2)家庭に対する啓発の推進:保護者向けの啓発資材を作成し、未成年の飲酒に伴うリスクを保護者に伝える
(3)職場教育の推進:飲酒に伴うリスクの周知を事業者に促す
(4)広報・啓発の推進
2. 不適切な飲酒の誘因の防止
(1)広告:不適切な飲酒を誘引しないよう広告・宣伝に関する自主基準を改正するよう求める(2)表示:酒類と清涼飲料との誤認防止、「酒マーク」の認知向上
(3)販売:未成年者への酒類販売・供与について指導、取り締まりを強化
(3)提供:未成年者への酒類提供禁止の周知を徹底
(4)少年補導の強化
3. 健康診断及び保健指導
(1)アルコール健康障害に関する調査研究:保健指導におけるアルコール使用障害スクリーニングとその評価結果に基づくブリーフインターベンションがどの程度行われているのか、調査研究を行うなど(2)地域におけるアルコール健康障害への早期介入の推進:「標準的な健診・保健指導プログラム【改訂版】(平成25年4月)」の周知など
(3)職域における対応の促進:アルコール健康問題に関する産業保健スタッフへの研修の充実を図る、など
4.アルコール健康障害に係る医療の充実等
(1)アルコール健康障害に係る医療の質の向上:早期発見、早期介入のための専門的な医療従事者向け研修プログラムの開発など(2)医療連携の推進(内科、救急等の一般医療と専門医療の連携)
5.アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等
(1)飲酒運転をした者に対する指導等(2)暴力・虐待・自殺未遂等をした者に対する指導等
6.相談支援等
地域の実情に応じて精神保健福祉センターや保健所などを中心に、アルコール健康障害を有しているものおよびその家族が分かりやすく気軽に相談できる拠点を明確化する、など
7.社会復帰の支援
(1)就労及び復職の支援:アルコール依存症が回復する病気であることを社会全体に啓発するなど(2)アルコール依存症からの回復支援
8.民間団体の活動に対する支援
自助グループの活動に必要な支援を行う、民間団体と連携を進めるなど
9.人材の確保等
*基本的施策1~8に掲げる項目を再掲
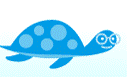
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.


「アルコール」に関するニュース
- 2025年08月05日
-
【インタビュー】2週間のデトックスで生産性が変わる?
大塚製薬の『アルコールチャレンジ』に学ぶ健康経営 - 2025年07月18日
- 日本人労働者の3人に1人が仕事に影響する健康問題を経験 腰痛やメンタルヘルスなどが要因 働きながら生産性低下を防ぐ対策が必要
- 2025年07月14日
- 適度なアルコール摂取は健康的? 大量飲酒の習慣は悪影響をもたらす お酒との良い関係
- 2025年07月07日
-
ノンアルコール飲料の活用が ''減酒支援ツール'' に?
特定保健指導・健康経営での活用法とは【産衛学会レポート公開中】 - 2025年07月07日
- 日本の働く人のメンタルヘルス不調による経済的な損失は年間7.6兆円に 企業や行政による働く人への健康支援が必要
- 2025年07月07日
- 自分の認知症の発症をイメージして不安に 認知症があってもなくてもともに生きられる共生社会が求められる
- 2025年07月01日
- 生活改善により糖尿病予備群から脱出 就労世代の1~2割が予備群 未病の段階から取り組むことが大切 日本の企業で働く1万人超を調査
- 2025年06月23日
- 昼寝が高血圧・心臓病・脳卒中のリスクを減少 ただし長時間の昼寝は逆効果 規則的な睡眠スケジュールが大切
- 2025年06月23日
- 「睡眠不足」と「不健康な食事」が職場のメンタルヘルスに影響 日本の企業のワーク・ライフ・バランス向上のための取り組み
- 2025年06月16日
- 【アルコール健康障害の最新情報】多量飲酒は認知症リスクを高める どんな状況で飲みすぎている? どうすれば飲みすぎを防げる?



















