集中治療における急性腎障害バイオマーカー~L-FABPの可能性~
介入の遅れが治療成績に影響しているのではないか?
急性腎不全の予後が予想以上によくない理由の一つとして治療介入が遅すぎる可能性が考えられ、これまでにも早期介入のための診断基準の作成や新規バイオマーカーの探索が続けられてきた。
例えば急性腎不全「ARF(Acute renal failure)」という言葉に代わり、より軽度な腎障害を含む「AKI(acute kidney injury)」という用語が定着してきているが、この端緒は腎不全に至る以前に的確な早期介入を可能とすることを目指して、国際的な重症度分類「RIFLE基準」が策定されたことにある。
RIFLE基準策定後、その重症度分類が死亡率とよく相関することが実臨床において確認され実用性が裏付けられたが、さらなる予測能の改善が試みられ、AKIN、KDIGOという新たな分類が登場した。ただ、それらはいずれもがクレアチニンと尿量を指標にしていることに変わりはなく、判定に48時間~7日を要する(表2)。
| RIFLE | AKIN | KDIGO | |
|---|---|---|---|
| 診断に用いる基準 | 血清Cr/GFR, 尿量 | 血清Cr, 尿量 | 血清Cr, 尿量 |
| 病期重症度分類 | Risk, Injury, Fallure (7日以内) |
ステージ1, 2, 3 (7日以内) |
ステージ1, 2, 3 (7日以内) |
| 臨床帰結分類 | Loss, ESKD | なし | なし |
| 腎代替療法の扱い | 病期に関係しない | ステージ3とする | ステージ3とする |
| AKI定義 (血清Cr基準) |
基礎Cr値から≧1.5倍増加 | ≧0.3mg/dLの増加 (48時間以内) or ≧1.5倍増加 (48時間以内) |
≧0.3mg/dLの増加 (48時間以内) or 基準Cr値≧1.5倍増加 (7日以内) |
| 基礎Cr値 | MDRD式より推算 | 不要. 48時間で診断可能 | MDRD式より推算. 血清Cr値が速やかに低下した 場合は, その値を基礎値とする |
| 除外項目 | なし | 腎前性. 腎後性の否定 | 腎前性. 腎後性の否定 |
確かにクレアチニンは、院内死亡率との関連を示すデータが多くあり、前値から0.5mg/dL上昇した場合に死亡のオッズ比は6.5に跳ね上がるとの報告もみられ 1)、予後への影響が極めて強い。しかし逆にクレアチニンの上昇を待つがために診断が遅れているのではないかと従来から指摘されている。
AKIのバイオマーカーに求められるもの
よく知られているようにクレアチニンはGFRが50~60%まで低下してからようやく顕著に上昇してくる。つまりクレアチニンには「ブラインド領域」と呼ばれ る時期が存在し、AKIの発症や進行を直ちに把握できない。腎障害、特に腎実質性障害の85%は尿細管障害で占めることが知られている(図1)。このような背景から、腎尿細管障害をクレアチニンの上昇を待たずに把握可能とするバイオマーカーの臨床応用が期待されてきた。
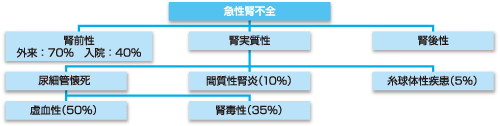
〔N Engl J Med 334:1448-1460,1996〕
虚血や再灌流あるいは薬剤等の負荷によって尿細管上皮細胞が障害される、もしくはストレスを受けるとさまざまな物質、例えばL-FABPやNGALといったものが尿中に分泌されたり再吸収を受けずに排泄される。それらが腎バイオマーカーと称されるものだ。腎バイオマーカーが反応した後さらに上皮細胞障害が進行しGFRが低下すると、クレアチニン等が上昇してくるわけだ(図2)。
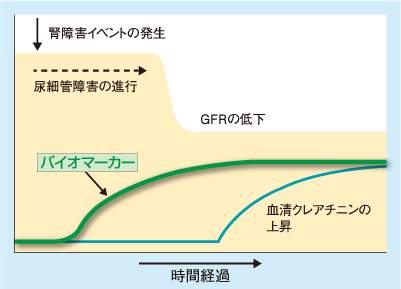
AKIのバイオマーカーには、①早期診断、②重症度判定や予後予測、③原因の鑑別、④血液浄化の必要性判定、⑤治療効果の評価――などが求められる。これらについて、L-FABPとNGALの二つを中心に検討してみたい。


「健診・検診」に関するニュース
- 2025年08月21日
- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告
- 2025年07月07日
- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市
- 2025年06月27日
-
2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%
過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日
-
【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ
対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日
- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】
- 2025年05月20日
-
【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築
―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日
- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善
- 2025年05月16日
- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少
- 2025年05月12日
- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要
- 2025年05月01日
- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】


















