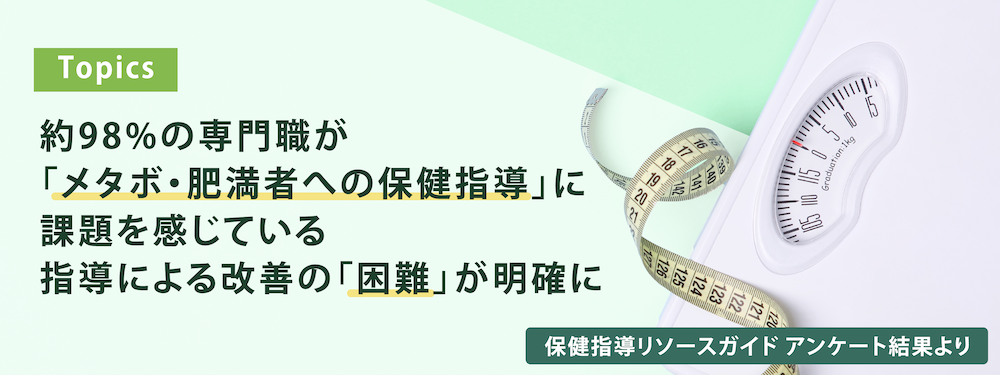糖尿病合併症のバイオマーカー:GAの臨床的意義
糖尿病合併症のバイオマーカー:GAの臨床的意義
久山町研究から考える
認知症と血糖バイオマーカー
地域住民における認知症有病率
久山町研究では、1985年から65歳以上の高齢者を対象に認知症の有病率調査および追跡調査を行っている。
1985年から2012年まで7年間隔で行った有病率調査(受診率90%以上)では、この間、認知症の有病率は6.7%から17.9%に急増した9)。認知症の病型別にみると、アルツハイマー病(AD)の有病率(性・年齢調整)は1985年の1.1%から2012年の7.1%に有意に上昇したが、血管性認知症およびその他の認知症の有病率に明らかな時代的変化は認めなかった。現在、日本の地域社会は認知症(とくにAD)患者であふれているのが実状である。
糖尿病と認知症の関連
AD患者が増加した要因を明らかにするために、60歳以上の久山町住民の追跡調査で耐糖能レベル(WHO基準)とAD発症との関係を検討した。
その結果、ADの発症リスクは糖代謝の悪化に伴い有意に増加した(図1a)10)。近年、国民レベルで糖尿病が急増したことが認知症、とくにADの増加をもたらしたと考えられる。

Cox比例ハザードモデルを用いハザード比を推定(両側検定p<0.05を有意)
調整因子:性、年齢、学歴、高血圧、脳卒中の既往、心電図異常、BMI、WHR、総コレステロール、禁煙、飲酒、身体活動度
血糖レベルと認知症の関連
さらに、血糖レベルとADの発症リスクとの関係を検証した。
その結果、空腹時血糖値とAD発症との間には明らかな関連はみられなかった(図1b)が、糖負荷後2時間血糖値の増加とともにそのリスクが上昇し、すでにIGTのレベル(血糖値140-199mg/dL)と最低値レベル(119mg/dL以下)の間で有意差が存在した(図1c)10)。同様の関連は血管性認知症についても認められる。
この血糖値とADの関連については、久山町のMRIによる画像疫学や剖検脳の病理学検討でもこれを支持する知見が得られている。
久山町では2012年に高齢者1,238人の頭部MRIを撮影した。その検討では、糖尿病患者は非糖尿病者に比べ全脳萎縮の指標である頭蓋内容積に対する全脳容積の比が有意に小さく、とくに短期記憶に関わる海馬の萎縮(海馬容積/全脳容積比低下)が顕著だった(図2)11)。血糖レベル別にみると、空腹時血糖値は海馬萎縮とは関連せず、糖負荷後2時間血糖値が有意な関連を示した(図3)11)。

ANCOVAにより解析
調整因子:性、年齢、学歴、高血圧、総コレステロール、BMI、喫煙、飲酒、運動習慣、画像上の脳血管障害

ANCOVAにより解析
調整因子:性、年齢、学歴、高血圧、糖尿病治療薬、総コレステロール、BMI、喫煙、飲酒、運動習慣、画像上の脳血管障害
さらに久山町の剖検135例について、生前の血糖レベルと剖検脳におけるADの主座と考えられているアミロイドβが 蓄積した老人斑の形成との関連を調べた。その結果、やはり空腹時血糖値と老人斑との間に明らかな関連はみられなかったが、糖負荷後2時間血糖値の上昇は老人斑形成の有意な関連因子だった12)。
以上の成績は、認知症、とくにAD発症を予測するうえで糖負荷後2時間血糖値を評価することの重要性を物語っているといえよう。しかし、糖負荷試験は煩雑であり時間がかかることから、健診ではほとんど行われておらず、日常臨床でもその実施機会が少なくなっている。したがって、糖負荷後2時間血糖値に代わる、簡便に測定可能なバイオマーカーが必要と考えられる。
血糖バイオマーカーとアルツハイマー病の関連
そこで、2007年に設定した久山町の高齢者集団を5年間追跡した成績で、追跡開始時のHbA1c、GA、GAをHbA1cで除した値であるGA/HbA1c比、1,5-AGについてそれぞれを四分位のレベルでわけてAD発症との関連を検討し、バイオマーカーとしての意義を評価した。
その結果、性・年齢調整後のAD発症の発症率は、GAおよびGA/HbA1c比のレベルとともに上昇し(図4)、多変量調節後のハザード比はGA/HbA1c比でのみ有意な上昇を示した(図5)13)。


調整因子:性、年齢、高血圧、総コレステロール、BMIカテゴリー、脳卒中の既往、学歴、飲酒、喫煙、運動習慣
GA/HbA1c比は食後高血糖、あるいは血糖変動の指標と考えられている14, 15)。久山町の上記追跡調査における層別解析で糖代謝異常の有無別にみると、GA/HbA1c比とAD 発症の関係は正常耐糖能者でも認められた(図6)13)。また、食後高血糖の鋭敏な指標である1,5-AGがAD発症と関連しないことからも、GA/HbA1c比は食後高血糖より血糖変動を反映してAD発症と関連している可能性がある。AD発症のバイオマーカーとしてのGA/HbA1c比の意義は、そのメカニズムを含め今後さらに検討する必要がある。



「健診・検診」に関するニュース
- 2025年02月25日
- 【国際女性デー】妊娠に関連する健康リスク 産後の検査が不十分 乳がん検診も 女性の「機会損失」は深刻
- 2025年02月17日
- 働く中高年世代の全年齢でBMIが増加 日本でも肥満者は今後も増加 協会けんぽの815万人のデータを解析
- 2025年02月12日
-
肥満・メタボの割合が高いのは「建設業」 業態で健康状態に大きな差が
健保連「業態別にみた健康状態の調査分析」より - 2025年02月10日
- 【Web講演会を公開】毎年2月は「全国生活習慣病予防月間」2025年のテーマは「少酒~からだにやさしいお酒のたしなみ方」
- 2025年02月10日
- [高血圧・肥満・喫煙・糖尿病]は日本人の寿命を縮める要因 4つがあると健康寿命が10年短縮
- 2025年01月23日
- 高齢者の要介護化リスクを簡単な3つの体力テストで予測 体力を維持・向上するための保健指導や支援で活用
- 2025年01月14日
- 特定健診を受けた人は高血圧と糖尿病のリスクが低い 健診を受けることは予防対策として重要 29万人超を調査
- 2025年01月06日
-
【申込受付中】保健事業に関わる専門職・関係者必携
保健指導・健康事業用「教材・備品カタログ2025年版」 - 2024年12月24日
-
「2025年版保健指導ノート」刊行
~保健師など保健衛生に関わる方必携の手帳です~ - 2024年12月17日
-
子宮頸がん検診で横浜市が自治体初の「HPV検査」導入
70歳以上の精密検査無料化など、来年1月からがん対策強化へ