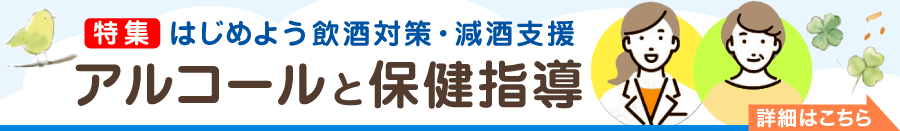【オピニオン公開中】職域でのアルコール指導・減酒支援、多職種・チーム連携

歓送迎会や忘・新年会、取引先との接待など、日本の企業活動では飲酒を伴うコミュニケーションの場が多くあります。「飲み会文化」や「飲酒文化」などと称されるように、親睦やコミュニケーションの機会にアルコールは欠かせないものと考えられがちですが、飲み過ぎによるトラブルや健康悪化の種になっている、という側面もあります。
このような現状を問題視し、AGC株式会社鹿島工場産業医・健康管理センター所長で、神栖産業医トレーニングセンター・統括指導医でもある田中 完先生は、アルコールを伴わない宴席「ノンアルパーティー」を提唱するなどしています。
産業医として従事する中で、アルコール問題への関心を高めてきたという田中先生に、なぜ企業が従業員のアルコール指導や減酒支援に取り組む必要があるのか、またアルコール使用障害同定テスト「AUDIT(オーディット)」(Alcohol Use Disorders Identification Testの略)や減酒支援プログラムの有効性などについて聞きました。
No.1 「飲みニケーション」は有効か?
産業医として見過ごせなかったアルコール問題
――アルコール問題に取り組み始めたきっかけを教えてください。
田中 産業医としてのスタートは、とある製鉄業の企業でした。従事する中で、他のメンタルヘルスの問題と比べても、アルコール依存症が疑われる社員の対応はなかなか大変だという実感を持つようになりました。
アルコール依存症で産業医が留意すべき事柄について詳しく記したものに、産業医科大学の廣 尚典先生らが作った『アルコール依存症例の職場復帰支援マニュアル』があります。マニュアルでは復職にあたっての確認事項の一つとして「本人が断酒の必要性を認識し、かつその時点で継続できていること」と示されています。
しかし、しばらく断酒できても経過観察中に再飲酒してしまい、休職満了に伴って退職に至る事例を見てきました。断酒していたアルコール依存症の人たちが再飲酒することを「スリップ」と言うのですが、他のメンタルヘルスの病気と比べて改善の成果が上がらず、重症例も多いように感じていました。成功例といえば、家族や行政の社会福祉担当者、近所の人まで総出でサポートして、ようやく断酒できたような大変な事例ぐらいです。
No.2 企業はどのようにアルコール問題に取り組めば良いのか
飲酒の習慣化に問題意識を持つ
――企業によるアルコール問題への取り組みで課題と感じているのはどのような点ですか?
田中 アルコール依存の状態になったり、飲酒が原因で健康を害したりするまでは、喫煙と比べてあまり保健指導をされないのが問題だと感じています。さまざまな機会を捉えて啓発活動をする必要があるのですが、タバコに比べると、まだまだアルコールの問題に切り込んでいく企業は少ないと感じています。
――それはどうしてでしょうか。
田中 アルコール依存症になったり、肝硬変や高アンモニア血症などの病気になったりする社員はたしかに問題ですが、少数派です。そのため、企業が社員の健康問題を理由に全社を挙げてアルコール問題に取り組もうという動きにはなかなか結びつきにくいのです。どちらかといえば、飲酒が原因で生じる従業員の問題行動をリスクと考える企業が多いのではないでしょうか。
結局、アルコールを原因とする従業員の問題が企業の中で発覚するのは飲酒運転やハラスメントが起きてから、というケースも少なくありません。その場合は懲戒処分にしたら、企業の対応としては終わりなので、当事者の指導や支援にはつながりません。
No.3 ノンアルパーティーで「飲まなくても楽しい」を実証
全員の満足度が高まるノンアルパーティー
――田中先生が提唱している「ノンアルパーティー」とはどのようなものですか?
田中 全員がアルコールを飲まない宴会のことです。一般的に、職場での親睦会はお酒を飲むのが当たり前だと思います。しかし日本人の44%はお酒に弱い「ALDH2不活型」の体質だという調査結果がありますし、飲酒後のパフォーマンス低下はもちろん、中にはハラスメントや暴力、飲酒運転に至る人もいて、飲酒機会を増やすことは本来、企業にとってリスクが高いはずです。
また費用や参加率の問題もあります。実際に比較してみたところ、ノンアルパーティーの方が、飲酒を伴う通常の宴席より平均して3割は費用が安く済みました。さらに飲酒の前に、飲み過ぎや二日酔いを防ぐためにコンビニエンスストアなどでサプリやドリンクを買っている人がいて、そのような「アルコール対策のための費用」も当然かかりません。
このような理由から、飲み会ではなく、アルコール無しでの食事会にしましょう、という呼びかけを地道に続けています。まだまだ認知度は低いですが、特に国が定める「アルコール関連問題啓発週間」(毎年11月10日から16日まで)に、ぜひ実行してみてほしいです。一度やってもらえれば、意識は大きく変わると思います。
オピニオン回答者ご紹介
田中 完(AGC株式会社鹿島工場 産業医、健康管理センター所長)
名古屋徳洲会総合病院救急総合診療科を経て産業医に
製鉄業専属産業医を経てAGC(株)鹿島工場 健康管理センター長(産業医)、神栖産業医トレーニングセンター 統括指導医
株式会社iCARE 顧問
社会医学系指導医、日本産業衛生学会指導医
労働衛生コンサルタント
茨城県産業保健総合支援センター相談員(産業医学)
産業医学の著書多数
保健指導リソースガイドでは、アルコール指導・減酒支援の情報を集約した特設ページ「アルコールと保健指導」を開設しました。
現場で活躍する専門職へのインタビューや、指導に役立つツールの紹介、また、アルコール指導・減酒支援を実施する際に参照したい基本的な情報や調査・統計などを掲載しています。
この特設ページでは、保健指導の現場で役立つアルコール指導・減酒支援に関する情報を、継続して発信していきます。
本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。