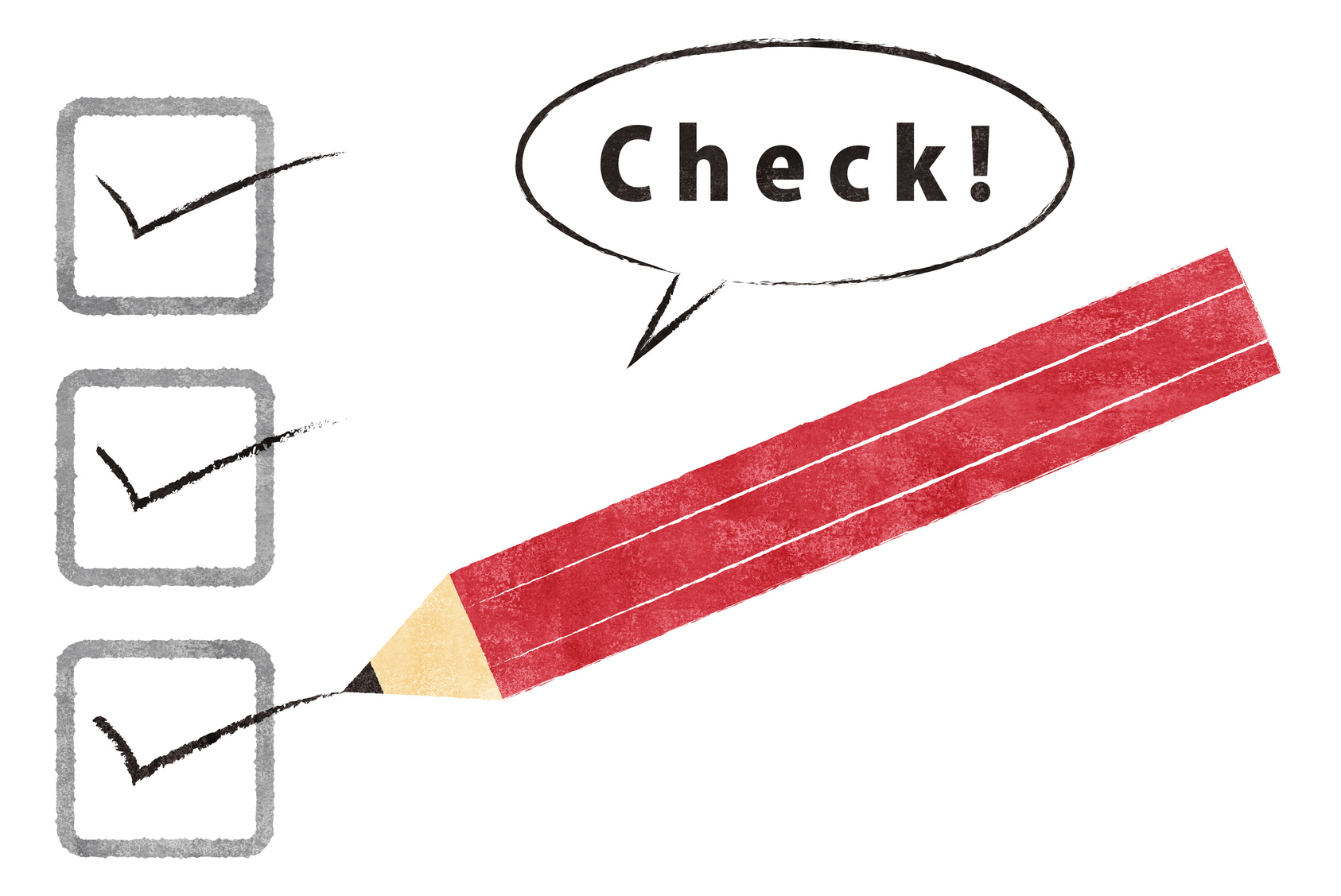病気を伝える順番について

すぐにがんが見つかったことを家族に伝えたかったのですが、普段、がんについて話題にすることがないことと、生死にかかわる病名ということもあり、なかなか日常とのギャップに伝えにくさを感じました。私の場合は、必要に迫られて関係者に順に話していきました。
最初に話したのは生命保険会社の担当の方でした。検診を受ける前日に年1回の生命保険の見直しで話しをしていましたので、健診センターを出た後、すぐに連絡しました。
昨日、彼女と話した時は「最近はがんになる方や心筋梗塞で倒れる方が多いから、3大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳梗塞)の特約保険は子供さんが手を離れるまでは、入っておいた方がいいですよ」と念押しされたのですが、明日の検診が終わったら3大疾病の特約は解約してしまおうと心の中で思っていました。
まさかこんなことになるとは思いもよりませんでした。保険の手続きがあることもありましたが、前日にがんのことを話題にしていたので、彼女と私との間では、がんは身近なものになっていました。そのため、すぐ話すことができたと思います。
近い存在ほど気を遣うように感じる

次に、夫に話しました。朝、検診に行くことを告げていましたので、今日はどうだったと声をかけてくれたおかげで、精査になった事を話すことができました。
健診センターで告知後のケアを受けていたこともあり、少し冷静でいられたように思いますが、これからの生活、子供のこと、職場のことなどを考えると、どこから整理していけばいいのかわかりませんでした。と、同時に日頃向き合わない病気や生死について他の人と共有することは、自分自身の精神状態や相手の精神状態などを考えると簡単にはいかないものだと思いました。
特に親、子供といった近い存在ほど気を遣うように感じましたし、少し時間をかけて、自分自身の気持ちが落ち着いてから話していきました。
病院では、精査を進めていく過程で、主治医や看護師が「病気のこと、今後の治療のことについて家族について話しましたか」と聞いてくださいました。
抗がん剤治療で日常のことができなくなることがあると聞き、「家族に迷惑をかけてしまうな。そもそも家事に加えて私の面倒をみるなんてできるのか。」と憂うつで不安になりました。
子供の年齢に合ったアドバイスがもらえる
「チャイルド・サポート」でのカウンセリング

そんな時、主治医から「お子さんの年齢はいくつ?チャイルド・サポートというのがありますから受けてみませんか。お子さんの年齢に合ったアドバイスをしてくれますよ。」とチャイルド・サポートでのカウンセリングを薦めていただきました。
「自分では精神的に安定していると思うけれど、ひょっとしたら健康的な判断ができていないかもしれない。子供の年齢に合ったアドバイスがもらえるなら。」とチャイルド・サポートを受けることにしました。
チャイルド・サポートでは、チャイルド・ライフ・スペシャリスト(CLS)※が子供に関する様々な相談を受け、母親の療養生活がより安心したものになるようサポートしてくれます。
患者である母親への心のケアや母親の病状や治療などを子供がどのように感じているかを見極め、家族が子供にどのように話していけばよいか支援してくれます。子供と直接会話する場合もあるようで、子供の心の内に抱える感情やストレスを引き出し、子供なりに困難を乗り越えられるように後押ししてくれます。
※チャイルド・ライフ・スペシャリスト(CLS):北米で普及、発展してきた専門資格。医療環境にある子供や家族に心理社会的支援を提供する。Child Life Councilによる認定。
チャイルド・ライフ・スペシャリスト協会ホームページ 参照。
チャイルド・サポートでは、30分くらいのカウンセリングを受けました。まず、私自身の今の気持ちを聞いてもらいました。その後、子供の性格、家での様子や私の病気について気づいているかについて聞かれました。
それらを踏まえた上で「子供には子供の生活があり人生があります。部活に行ったり、友達と遊びに行ったりする時は快く送り出してあげてください。苦しいときに誰かに話すかもしれませんが、それはお子さんが決めると思います。病気のこと、元気になるために治療を受けること。お母さんだって不安なんだという気持ちを素直に話してみてください。」と言われました。また参考になればと冊子、絵本をいただきました。
<参考>
お子さんと“がん”について話してみませんか(冊子)
執筆・編集・発行‐がんの親を持つ子どもの支援プロジェクト‐
おかあさん だいじょうぶ?(絵本)
作‐乳がんの親とその子どものためのプロジェクト
絵‐黒井健 小学館
病気だけれど病人になるかどうかは自分が決めること

子供には子供の人生があると言われ、はっとさせられました。心のどこかに「自分は病気で協力してもらうのが当たり前。」という気持ちがあったことに気づきました。
以前、メンタルヘルス対策に携わっていた時に、担当の臨床心理士さんと「家族の形」について話したことを思い出しました。
「父親には父親の役割、母親には母親の役割、子供には子供の役割がある。自分の役割を果たさず他の役割を果たそうとすると家族の形が崩れやすくなる。」という話でした。
私は「母親を放棄しようとしていたかもしれない。病気と言われたけれど母親であることには変わりない。ひょっとしたら依存の構造になるところだったかもしれないな。」と思いました。同時に「病気だけれど病人になるかどうかは自分が決めることなんだ。」とも思いました。
そして、改めて過信せず専門職に相談することの大切さを感じました。どこの病院にもCLSがいるわけではないかもしれませんが、客観的に見てくれる第3者、心理士や保健師、看護師といった専門職に相談してから子供や身近な人に話していくのが良いと思いました。
子どもに伝える
こうして、私自身としては気持ちの落としどころを見つけることができましたが、子供は子供なりに気持ちの整理をするのが大変だったようです。
子供には検診後2週間ぐらいしてから話しをしました。
「今日は大事なお話があります。この間の検診で乳がんが見つかったの。がんになったのは誰のせいでもないからね。ママは、生きるために治療をするから、少し迷惑をかけることもあるかもしれないけれど協力してね。
でも今までと生活は変わりないからいつものように学校や部活に行ってね。遊びにも行っていいよ。ママはその方がうれしい。ママの病気のことを受け止めるのは、荷が重すぎるだろうから、もしママのことを話せるようなら先生やお友達に話していいんだよ。」
と気持ちを落ち着けて話すようにしました。
子供の頬から涙がぽろぽろとこぼれ落ちました。最後まで私の話を聞いてくれ、「協力するよ。一緒に頑張ろうね。」と言ってくれました。
主治医からの説明が子どもの安心感へつながった

先日、あの時の心境はどうだったの?と子供に聞いたところ、「目の前の元気な母親が、がんだということが信じられなかった。がんが時間をかけてできていくことを聞いてずいぶん苦労を掛けてしまった。私のせいだ。」と申し訳ない気持ちでいっぱいになり、涙がぽろぽろこぼれ落ちたと言っていました。
「正直、母親の病気を受け止めることはできなかったし1週間くらいは嘘でしょ、嘘であってほしいと願っていた。」と言っていました。
その後、主治医から家族への説明を受け、手術に向けての準備が始まる中で、少しずつ自分なりに受け止め、信頼している部活の先生や友人に母親の病気について話すことができたようです。
周囲に励ましてもらいながら、子供なりに気持ちの整理をしていったようです。特に主治医が時間を割いてきちんと説明してくれたことが安心感につながったとも言っていました。
病気について伝える まとめ
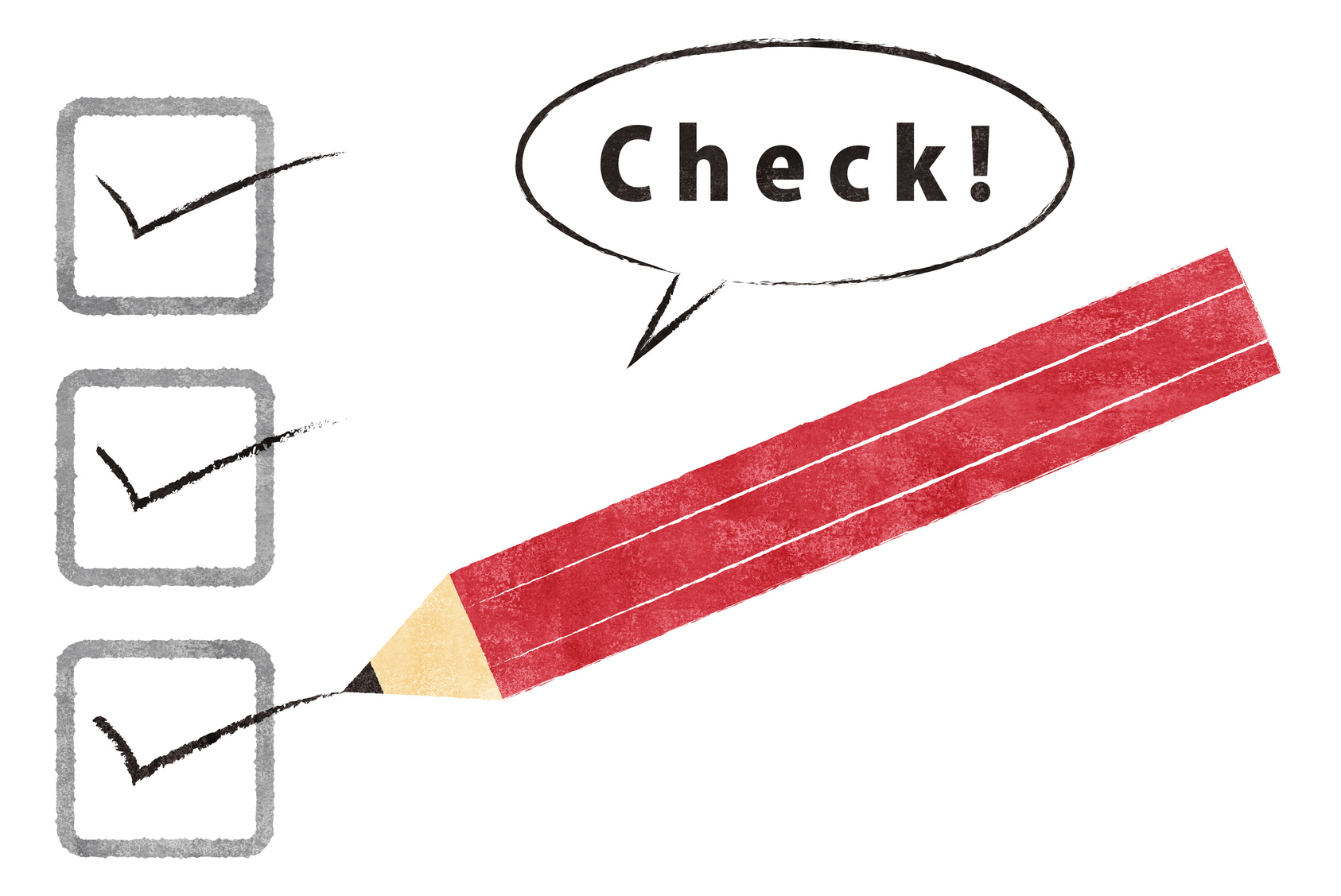
<それぞれの相手に話す時に感じたこと>
・日頃向き合わない病気や生死について自分以外の人と一緒に考えていくということ
・自分の精神状態を過信しない
・サポートを受ける大切さ
・病気だけれど病人になるかは自分が決める
・依存の構造
<がんについて話した相手>
生命保険の担当者:最初に話せた人、保険を通じて「がん」について話しをしていたから
夫:検診に行くことを話していたので話すことができた。検診どうだった?と聞かれたので話すきっかけができた
子供:主治医からのすすめで、チャイルド・サポートを利用する
・性格や年代別の話し方がある
・子供には子供の生活があるということ
・こちらが考える以上に簡単には受け止められないこと
・母親の病気が自分のせいだと思っていた
・子供の気持ちの整理も必要
・先生や友人のサポート
・主治医の説明が安心感につながった